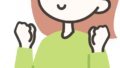- 「学びて時にこれを習う、またよろこばしからずや」 -学んだことを復習し、身につけるのは楽しいことだ。
- 「故きを温ねて新しきを知る」 -過去のことを学び、新しい知識を得る。
- 「過ちて改めざる、これを過ちという」 -間違いを犯しても改めなければ、それこそが本当の過ちである。
- 「三人行えば必ず我が師あり」 -三人集まれば、必ず自分の学ぶべき人がいる。
- 「知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れず」 -知恵のある者は迷わず、仁のある者は悩まず、勇気のある者は恐れない。
- 「己に克ちて礼を為すを仁と為す」 -自分に打ち克ち、礼を尽くすことが「仁」である。
- 「剛毅木訥、仁に近し」 -意思が強く、素朴で口数の少ない人は、仁に近い。
- 「君子は義に喩り、小人は利に喩る」 -立派な人は正義を考え、小人は利益を考える。
- 「人の己を知らざるを患えず、人を知らざるを患う」 -人が自分を理解してくれないことを気にするのではなく、自分が人を理解できていないことを気にせよ。
- 「徳は孤ならず、必ず隣あり」 -徳のある人は孤立しない。必ず共感し合う人が現れる。
- 「巧言令色、鮮なし仁 -口先がうまく、見た目ばかり飾る人には、真心が少ない。
- 「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」 -君子は調和するが流されない。小人は迎合するが調和しない。
- 「道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に遊ぶ」 -人生の目標を持ち、道徳を軸とし、人を思いやり、技を楽しむ。
- 「学ばざれば則ち智なし」 -学ばなければ知恵は得られない。
- 「己の欲せざる所、人に施すことなかれ」 -自分がされて嫌なことは、人にしてはならない。
- 「義を見て為さざるは、勇無きなり」 -正しいことを見て行動しないのは、勇気がないからだ。
- 「知之を知ると為し、知らざるを知らずと為す、これ知るなり」 -知っていることは知っていると言い、知らないことは知らないと言う。それが本当の知である。
- 「千里の行も足下より始まる」 -千里の道も、一歩から始まる。
- 「人の己を知らざることを患えず、人を知らざることを患う」 -人が自分を理解してくれないことを気にするのではなく、自分が人を理解できていないことを気にすべきだ。
- 「士は己を知る者の為に死す」 -志のある人は、自分を理解してくれる人のために尽くす。
- 「吾十有五にして学に志す」 -15歳で学問に志した。学ぶことに遅すぎることはない。
- 「人能く道を弘む、道人を弘むるに非ず」 -人が道を広めるのであって、道が人を広めるのではない。
- 「君子は言に訥にして、行いに敏ならんと欲す」 -立派な人は口数少なく、行動は素早くする。
- 「学べば則ち固ならず」 -学べば偏見にとらわれなくなる。
- 「生まれながらにして知る者は上なり」 -生まれながらの天才は最上だが、努力して学ぶ者も素晴らしい。
- 「徳は本なり、財は末なり」 -徳は根本であり、財はその結果に過ぎない。
- 「人の能く我を弘むるに非ず、我が能く人を弘むるなり」 -自分を成長させるのは他人ではなく、自分の努力である。
- 「工欲善くその事を為さんと欲すれば、必ず先ずその利器を利くす」 -職人が良い仕事をするには、まず道具を整えることが大切だ。
- 「これを知る者は、これを好む者に如かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如かず」 -知っているだけの人よりも、それを好む人が勝っており、好む人よりも楽しむ人がさらに優れている。
- 「みずからを厚くして人を責むること薄ければ、すなわち怨み遠ざかる」 -自分に厳しく、人には寛容であれば、恨みは生まれにくい。
- 「君子は義を先にして利を後にす」 -徳ある人はまず正義を重んじ、利益はその次とする。
- 「われ日に三たびわが身を省みる」 -私は毎日三回、自分の行動を反省する。
- 「士道に志して、悪衣悪食を恥ずる者は、与に議すべからざるなり」 -道を志す者が、みすぼらしい衣食を恥じるようでは、本質を語り合うには足りない。
- 「過ちては則ち改むるに憚ること勿れ」 -間違えたら、すぐに改めることをためらってはならない。
- 「君子は独りを慎む」 -君子(徳のある人)は、人が見ていないときでも正しい行いをする。
- 「怒りを遷さず、過ちを弐たびせず」 -怒りを他人に向けず、同じ過ちは繰り返さない。
- 「君子は坦かに蕩蕩たり。小人は長えに戚戚たり」 -君子は心が広く穏やかであり、小人はいつも不安や心配でいっぱいだ。
- 「君子は求むるは己にあり、小人は求むるは人にあり」 -君子は自分自身に原因を求め、小人は他人のせいにする。
- 「不仁者は以て久しく約に処るべからず」 -仁徳のない者は、長く困難には耐えられない。
- 「居処は恭に、事を執りて敬に、人に与りて忠なるべし」 -住まいでは謙虚に、仕事は丁寧に、人には誠実に。
- 「其の身正しければ、令せずして行わる」 -自らが正しければ、命じなくても人は従う。
- 「立つこと未だ立たざる者を立たしめ、達すること未だ達せざる者を達せしむ」 -自分がすでに達成したことを、他人にも促して共に高め合う。
- 「性相近し、習い相遠し」 -人の生まれ持った性格は似ているが、学びによって大きく差がつく。
- 「敬して失うこと勿れ」 -常に敬意を持って人と接し、失礼がないようにせよ。
- 「知者は楽しみ、仁者は寿す」 -知恵ある者は人生を楽しみ、仁徳のある者は長く生きる。
- 「憤せずんば啓せず、悱せずんば発せず、一隅を挙ぐるに、三隅を以つて反せずんば、則ち復びせざるなり」 -強く知りたいと望まなければ教えず、言いたくてたまらない状態でなければ助けない。
- 「忠告して善くこれを道き、不可なれば則ち止む。自ら辱しむること無かれ」 -忠告して善導しても聞かない人には、それ以上関わらない。
- 「不義にして富み且つ貴きは、我に於いて浮雲のごとし」 -正義に反して得た富や地位は、私には浮雲のようなもの。
- 「朝に道を聞かば、夕に死すとも可なり」 -朝に真理を知ることができれば、夕方に死んでも悔いはない。
- 「与に善を同じうして之を悪しきとせず、与に悪を同じうして之を善きとせず」 -一緒に良いことをしてもそれを悪いと言わず、一緒に悪いことをしても良いとは言わない。
- 「君子は九思あり」 -君子には九つの深い思慮がある(視・聴・色・貌・言・事・疑・忿・得)。
- 「学びて思わざれば則ち罔し、思いて学ばざれば則ち殆し」 -学ばなければ危うい。
- 「人にして遠き慮り無ければ、必ず近き憂いあり」 -先のことを考えなければ、目の前の心配に苦しむことになる。
- 「歳寒くして、然る後に松柏の彫むに後るるを知る」 -困難のときにこそ、本物の力を持った者がわかる。
- 「忠信を主とし、己に如かざる者を友とすること勿れ」 -忠実と誠実を大切にし、自分より劣った人を友としてはいけない。
- 「其の身を正しくして人に正しきを求む」 -まず自らが正しくあり、他人にもそれを求める。
- 「位無きを患えずして、立つ所以を患う」 -地位が高くないことを心配するより、徳が高くないことを心配せよ。
- 「文を以て友を会し、友を以て仁を輔く」 -学問を通じて友を得、その友と共に仁を養う。
- 「義を好む者は、其の言必ず信」 -義を重んじる者は、必ず言葉にも信がある。
- 「過ちを憚らず」 -過ちを恐れて行動をためらうべきではない。
- 「質、文に勝てば則ち野、文、質に勝てば則ち史。文質彬彬として、然る後に君子なり」 -中身ばかりで飾りがなければ野暮、飾りばかりで中身がなければ軽薄。両立してこそ君子。
- 「小人は怨を懐く」 -徳のない者は、いつまでも恨みを忘れない。
- 「士にして志無くんば、亦何を以てか立たん」 -志のない者に、人としての立脚点はない。
- 「己の立たんと欲して人を立たしむ」 -自分が立ち上がりたいと思うなら、まず他人を支えよ。
- 「義を以てこれを制す」 -全ての行いは、義(正しさ)に基づくべきである。
- 「学は以て已むべからず」 -学ぶことは一生やめてはいけない。
- 「忠信行えば、義に至らん」 -忠と信をもって行動すれば、やがて義に至る。
- 「礼を知らざれば立つことなし」 -礼儀を知らなければ、人として立っていけない。
- 「巧言は徳に似たり」 -巧みな言葉は、一見徳があるように見えるが、実際はそうとは限らない。
- 「志を立てて道に向かい、恥を知って止まる」 -志をしっかり立てて正しい道に進み、恥を知る心を持って行動を止める。
- 「知者は水を楽しみ、仁者は山を楽しむ」 -知者は変化する水のように賢く、仁者は不動の山のように穏やかである。
- 「義に過ぎて行えば、害を招く」 -正しいことも度を越せばかえって害になる。
- 「恵を以て政を為すは、譬えば北辰の其の所に居りて、衆星のこれに共うが如し」 -仁徳ある政治は、北極星のように動かずとも自然に人々が従う。
- 「礼をもって和を貴しと為す」 -礼儀をもって調和を重んじることが大切である。
- 「能く礼を用うるは、争うこと無し」 -礼儀を正しく使えば、争いは起こらない。
- 「君子は器に拘らず」 -君子は役割に縛られず、臨機応変に対応できる人である。
- 「人にして信無くんば、其の可なるを知らず」 -人に信頼がなければ、その人がどうあっても信用できない。
- 「学を好む者は、賢に近し」 -学問を愛する者は、賢人に近づいている。
- 「君子は諸を己に求め、小人は諸を人に求む」 -君子は自分に原因を探すが、小人は他人に責任を押しつける。
- 「其の以て自ら多能とする者は、則ち難きかな」 -自分を有能だと過信する者は、困難に陥りやすい。
- 「義に死するは、得て免るべからず」 -正義のために命を賭けることは、避けられないこともある。
- 「人にして学ばざれば、其の志も亦小なり」 -学ばなければ志も小さくなる。
- 「君子は誨を以て人を導く」 -君子は教え導くことで人を育てる。
- 「君子は徳を尊び、学を尚ぶ」 -君子は徳を最も大切にし、学問を重んじる。
- 「志士仁人は、生を求めて以て仁を害すること無し」 -真に志を持つ人は、命を惜しんでまで仁を損なうことはしない。
- 「仁遠からんや、我仁を欲すれば、すなわち仁至る」 -仁は遠くない。自ら求めれば、すぐにそこにある。
- 「賢を見ては斉しからんことを思い、不賢を見ては内に自ら省みる」 -賢い人を見たら自分もそうなりたいと思い、そうでない人を見たら自分を省みる。
- 「道を行うに非ざれば、行わず」 -正しい道でなければ、実行してはならない。
- 「終わりを慎み、遠きを追えば、民徳厚きに帰す」 -物事の終わりを大切にし、祖先を敬えば、人々の徳は厚くなる。
- 「君子は本を務む。本立ちて道生ず。」 -君子は物事の基本を大切にする。基本がしっかりすれば、道(人生のあり方)は自然に生まれる。
- 「人、能く礼を致して敬せざるは無し」 -礼を尽くして接すれば、必ず相手の敬意を得られる。
- 「君子は泰にして驕らず」 -君子は落ち着いていても驕らない。自信があっても傲慢にならない。
- 「躬自ら厚くして、人を責めること薄くすれば、怨み無し」 -自分には厳しく、他人には寛容であれば、恨まれることはない。
- 「忠恕を道と為す。己の欲せざる所、人に施すことなかれ」 -誠実と思いやりが道の根本である。自分がされたくないことは他人にもしない。
- 「朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」 -朝に真理を聞くことができれば、その日死んでも本望である。
- 「君子は敬して失わず、与えて奪わず、これを行えば遠きも必ず至る」 -敬意を失わず、与えたものを奪わず、これを実行すればどんな遠くの目標にも届く。
- 「君子は其の言に恥ずること無きを欲す」 -君子は自分の言葉に恥じることがないように心がける。
- 「仁に居て仁を好まず、知と為すこと無きなり」 -仁(思いやり・誠実)のある立場にいながら、それを好まない者は本当の知者ではない。
- 「仕えて道に遇えば、亦た仕えざる可からず」 -仕える立場で道(正義や理想)に出会ったなら、それを行わずにはいられない。
- 「士は以て弘毅ならざるべからず。任重くして道遠し」 -志ある者は、心が広く意志が強くなければならない。責任は重く、道のりは遠いのだから