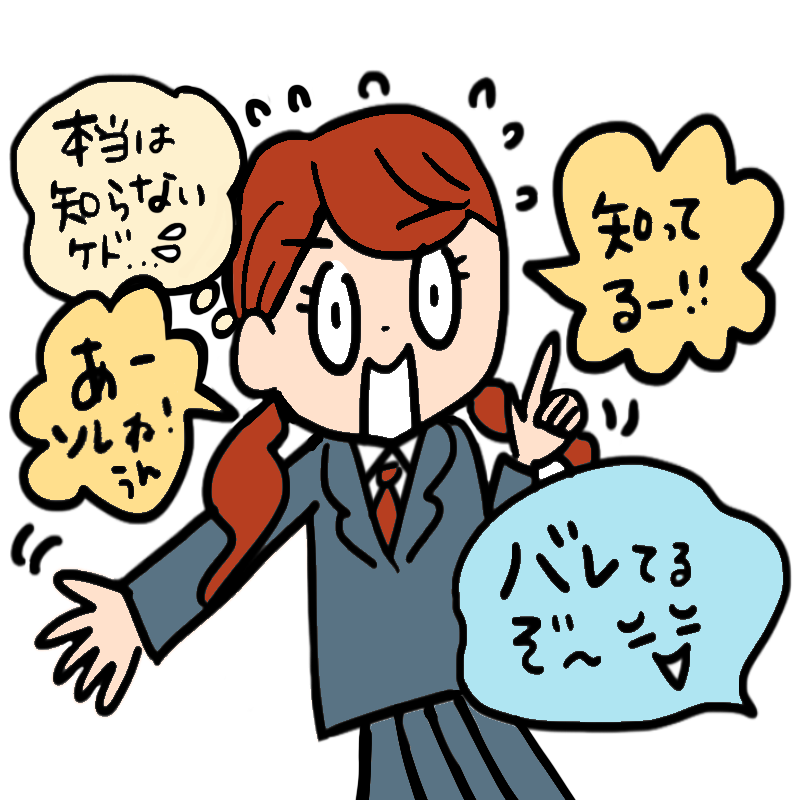
こんにちは!
今日は『論語』の中から、知識についての大切な考え方を紹介します。
今回取り上げるのは――
「知らざるを知らずと為す、これ知るなり」
…なんだか漢文のままだと難しそうですよね。
でも、意味が分かるととてもシンプルで、今の私たちの生活にも役立つ考え方なんです。
さっそく、わかりやすく解説していきます!
この言葉の意味
この言葉は、現代語にすると次のような意味になります。
「知っていることを『知っている』と認め、知らないことを『知らない』と認めることが、本当の知恵である」
つまり、「知ったかぶりをせずに、正直に自分の知識の限界を認めることが大事」ということです。
意外とシンプルですよね!
でも、これができる人は意外と少ないものです。
たとえ話
〈たとえ話①:医者の診察〉
あなたはお腹が痛くて病院へ行きました。
A先生:「うーん、おそらく胃腸炎でしょう。薬を出しますね。」
B先生:「これはちょっと分かりませんね。詳しく調べる必要があります。」
さて、どちらの先生が信用できると思いますか?
一見、A先生のほうが頼りがいがありそうですが、もしA先生が間違っていたら?
本当は別の病気だったら?
実は、B先生のように「わからないことを正直に認める人」のほうが、結果的に正しい判断をしてくれることが多いんです。
〈たとえ話②:テストでの出来事〉
テストの答え合わせの時間。
先生がある問題の解説をしていると、友達のA君が言いました。
A君:「あー、それ知ってたよ。でも、ちょっと間違えちゃっただけ。」
でも、実際にはA君は答えを知らなかったのです。
一方で、B君はこう言いました。
B君:「この問題、よく分からなかったんだけど、今説明を聞いて納得した!」
どちらのほうが、次のテストで成長できるでしょうか?
もちろんB君ですよね!
知らないことを「知らない」と認めることで、しっかりと学ぶことができるのです。
この言葉の起源
この言葉は、中国の思想家 孔子の教えを記した『論語』の「為政」という章に登場します。
孔子は、「知ったかぶりをするのではなく、本当に学ぶ姿勢が大切だ」と弟子たちに教えました。
これは、現代の学習や仕事の場面でも通じる大切な考え方ですね!
まとめ
今回の言葉 「知らざるを知らずと為す、これ知るなり」 から学べることは、
✅ 「知ったかぶりをしないこと」
✅ 「わからないことは素直に認めること」
✅ 「そうすることで本当の学びが得られること」
です!
私たちも、わからないことを正直に「知らない」と言える素直な心を持ちたいですね。
それでは、また次回の論語の言葉でお会いしましょう!