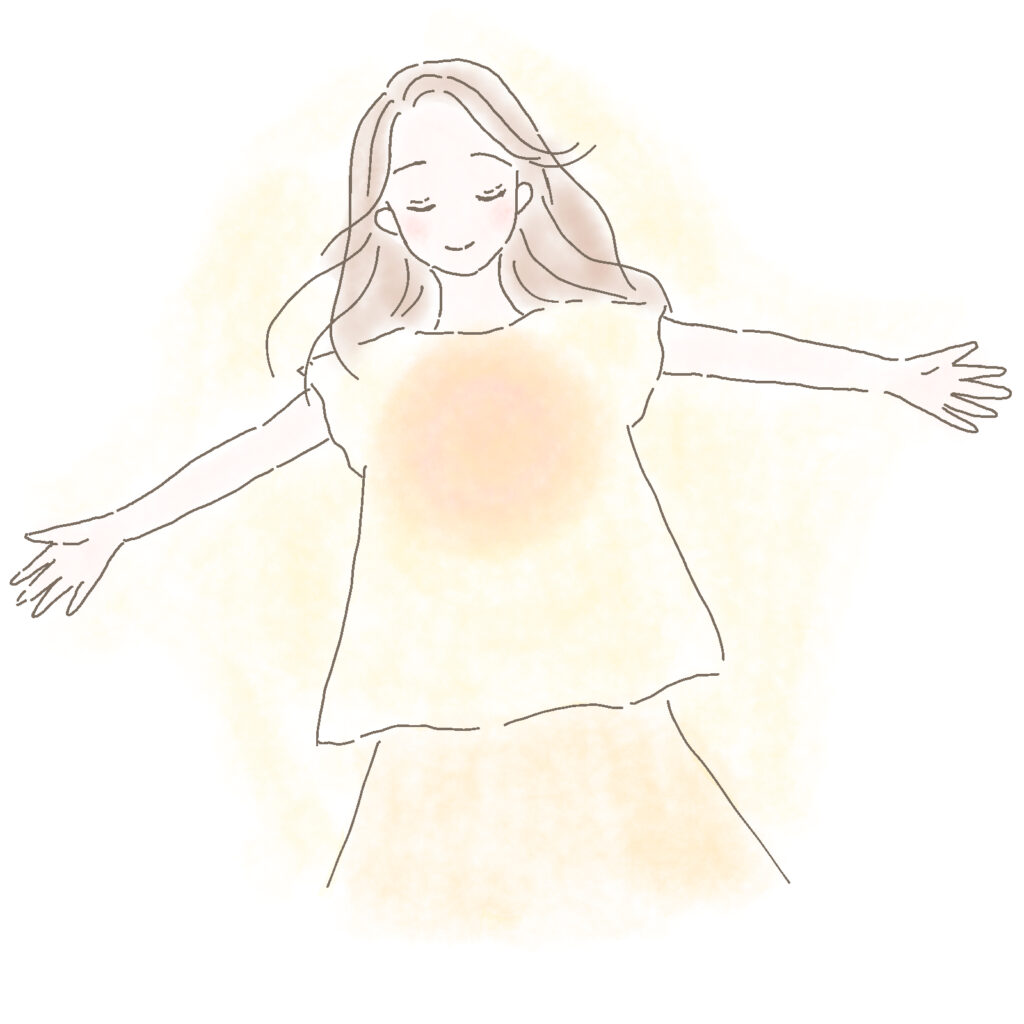
「いつまでも根に持つ人」と「水に流せる人」の違いとは?
人間関係でちょっとしたトラブルがあったとき、すぐに気持ちを切り替えられる人もいれば、いつまでもそのことを引きずってしまう人もいますよね。
「あのとき、あんなこと言われた…」
「まだ許せない…」
そんな風に、ずっと“怨み”のような感情を抱えてしまうと、自分自身がどんどん疲れてしまうものです。
今回ご紹介するのは、そんな人間の弱さに対して、孔子が放った一言。
「小人は怨を懐く」
シンプルだけど、心にグサッとくる深い言葉です。
たとえ話
たとえば、あなたが友達にちょっとした冗談を言ったとします。
それが相手には傷つく言葉だったらしく、謝ってもずっと無視されてしまう…。
「もういいって言ってくれたけど、まだ怒ってる…?」
「そろそろ水に流してくれても…」
そんなとき、感じるのが“気まずさ”や“しんどさ”ですよね。
孔子が言う「小人」は、まさにそういう“いつまでも根に持つ人”のことを指しています。
言葉の意味
この言葉は『論語』の憲問篇に登場します。
君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず。君子は義に喩り、小人は利に喩る。君子は怨を懐かず、小人は怨を懐く。
つまり:
- 君子(くんし)…品格のある人、思慮深い人は、怨みを心にとどめない
- 小人(しょうじん)…器の小さい人、自分のことばかり考える人は、怨みを抱き続ける
「小人」は身長が低いという意味ではなく、心が狭く、利己的で感情に流されやすい人という意味で使われています。
現代へのメッセージ
この言葉は、「君子になれ!」というよりも、「怨みを持ち続けるのは、自分のためにならないよ」という孔子の忠告として受け取るのが良いでしょう。
- 小さなことを気にしすぎて関係が悪くなる
- 怒りや嫉妬で自分の心が苦しくなる
- いつまでも過去のことに囚われて前に進めない
そんな状態から抜け出すには、「もういいか」と自分で線を引く勇気が必要です。
おわりに
怒りや悔しさ、傷ついた心を抱えながらも、それを手放す。
それは、簡単なようでとても難しいことです。
でも、それができる人こそが「君子」に近づくのだと、孔子は教えてくれています。
人とのすれ違いがあったとき、「ああ、今の自分、小人になってないかな?」とふと立ち止まってみるのも、自分を成長させるきっかけになるかもしれません。
