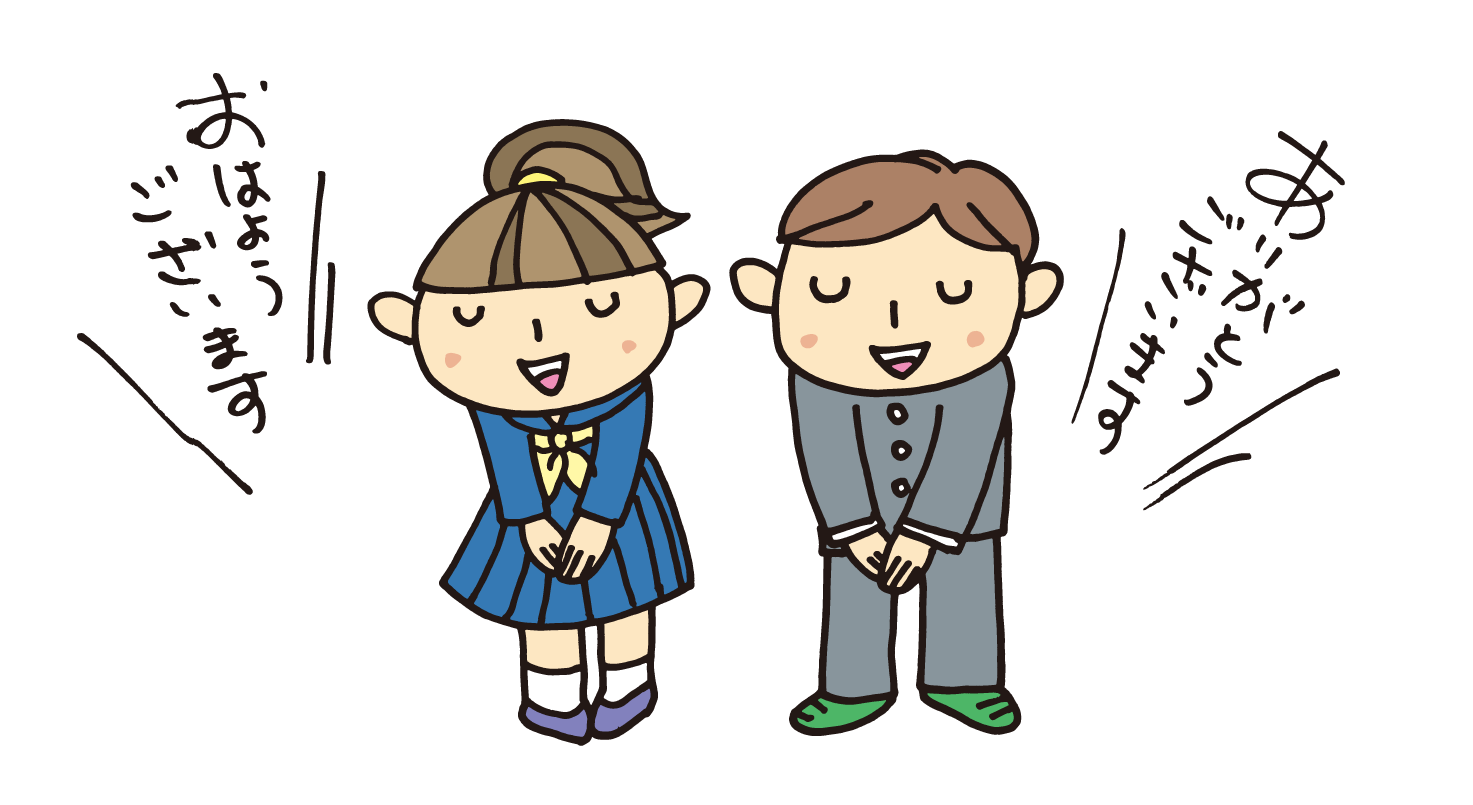「礼儀を知らなければ、人としての土台が築けない」
「礼儀正しい人」と聞くと、あなたはどんな人を思い浮かべますか?
丁寧な言葉遣い、相手を思いやる態度、公共の場でのマナー…。
実はそれらすべて、古代中国の思想「礼(れい)」に通じています。
孔子はこう言いました。
礼を知らざれば立つことなし
意味は、「礼儀(礼)を知らなければ、人として世の中に立つことはできない」ということ。
つまり、知識や才能よりもまず、「人としての基本=礼儀」がなければ信用されないし、社会の中で生きていけないという厳しくも温かい教えです。
たとえ話
ある会社に、新人が2人入りました。
Aさんは頭の回転が速く、仕事も飲み込みが早いけれど、挨拶をしなかったり、上司への言葉遣いがぞんざい。
Bさんはまだ仕事に不慣れだけれど、笑顔で挨拶し、周囲への気配りも忘れません。
最初はAさんの方が注目されましたが、数ヶ月後、信頼されていたのはBさんの方でした。
周囲が安心して協力したくなるのは、「礼儀がある人」だったのです。
これはまさに、「礼を知らざれば立つことなし」の現代的な例ですね。
出典と意味
この言葉は『論語』の季氏篇に登場します。
子曰く、礼を知らざれば以て立つことなし。
ここで孔子は、国や組織を治める者に向けて「礼を知らなければ、人として立つことも、国を治めることもできない」と説いています。
この「礼(れい)」は、単なる作法や形式ではありません。
相手を敬う心、秩序を守る意識、社会で共に生きるための知恵としての礼なのです。
現代に活かすヒント
現代社会でも、「礼儀正しい人」は信頼されやすく、チャンスが巡ってきます。
- 丁寧なメールやLINEの返信
- 目上の人への敬語
- お店で「ありがとう」と言うひとこと
こうした小さな行動の積み重ねが、「この人は信頼できる」と思ってもらえる土台になります。
反対に、どれだけ能力があっても、無礼な態度ひとつで信用を失うことも…。
おわりに
「礼儀正しい」というと、形式ばったものに思えるかもしれません。
でも孔子が伝えた「礼」とは、相手への敬意をもって自分を律する心の姿勢なのです。
礼を知らざれば立つことなし。
それはつまり、
「人としての根っこを大切にしてこそ、本当の意味で“立つ”ことができる」
という人生の土台を教えてくれる言葉です。