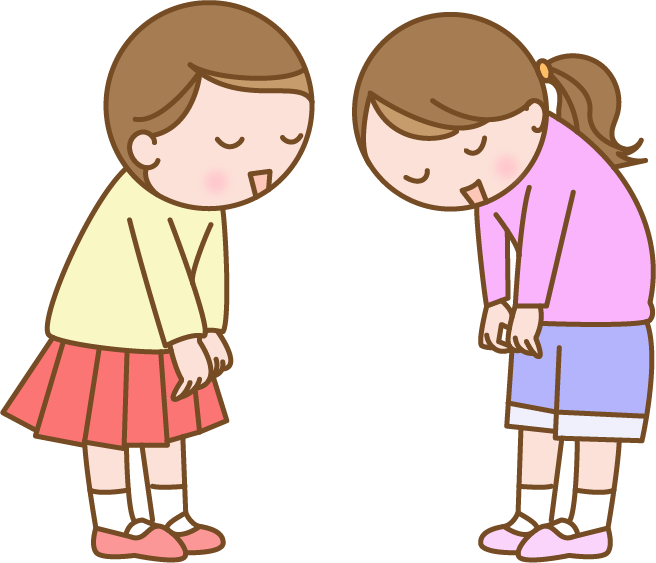
「仲良くすることが大事だよ」と、子どものころによく言われたかもしれません。
でも、大人になってからはどうでしょう?
“仲がいい”というだけでは、うまくいかない場面も増えてきます。
実は、2500年前の中国でも、「和を大切にする」という考えは重視されていました。
しかし孔子は、そこに一つ、大切な条件をつけていたのです。
■ 論語の一節
「礼をもって和を貴しと為す」
(学而篇より)
■ 意味をやさしく言うと…
- 礼(れい):人として守るべきルールや礼儀、けじめ
- 和(わ):人との調和、仲良くすること
- 貴しと為す(とうとしとなす):大切なものと考える
つまり、「ただ仲良くすればいい」のではなく、「礼(ルール・節度)」に基づいて仲良くすることが本当に大切なんだ、という教えです。
たとえ話
ある職場に、とても仲のいい同僚グループがありました。
仕事終わりに飲みに行ったり、LINEで毎日やり取りしたり、まるで家族のよう。
でもある日、ひとりが大事な会議の資料を忘れたときに、他のメンバーは
「まぁいいよ、気にしないで~」と笑って済ませてしまいました。
するとその後も、遅刻やミスが増え、だんだん仕事が回らなくなってきました。
仲がいいことは素晴らしい。
けれど、それだけではチームはうまくいきません。
「礼=けじめ」や「ルール」を守ることがあってこそ、本当の“和”が保たれるのです。
出典と背景
この言葉は『論語』の最初の章「学而篇」に出てきます。
孔子は、調和を大切にしながらも、「ただのなあなあ」や「八方美人」になることには警鐘を鳴らしていました。
当時の中国では、家族・村・国といったあらゆる共同体で「和」を重んじていましたが、孔子は「和さえあればよい」とは考えませんでした。
だからこそ、「和を重んじることは大切だけど、それは“礼”によって調整されるべきだ」と説いたのです。
現代にどう生かせる?
職場や学校、家庭でも「人間関係の良さ」はとても大切です。
でも、その関係が“ルールをゆるめるための口実”になってしまっては、信頼も崩れてしまいます。
孔子のこの言葉は、「仲良くする」ことと「きちんとする」ことの両立が必要だと教えてくれます。
お互いに気持ちよく過ごすためには、思いやりと同時に、けじめも大切なんですね。
まとめ
「ただ仲がいい」だけじゃダメ。
「礼」によって守られた「和」こそが、本当の調和。
それが、孔子の教える“人とのつながり”の理想の形です。
現代の人間関係にも活きるヒントが、2500年前のこの一言に詰まっているのです。