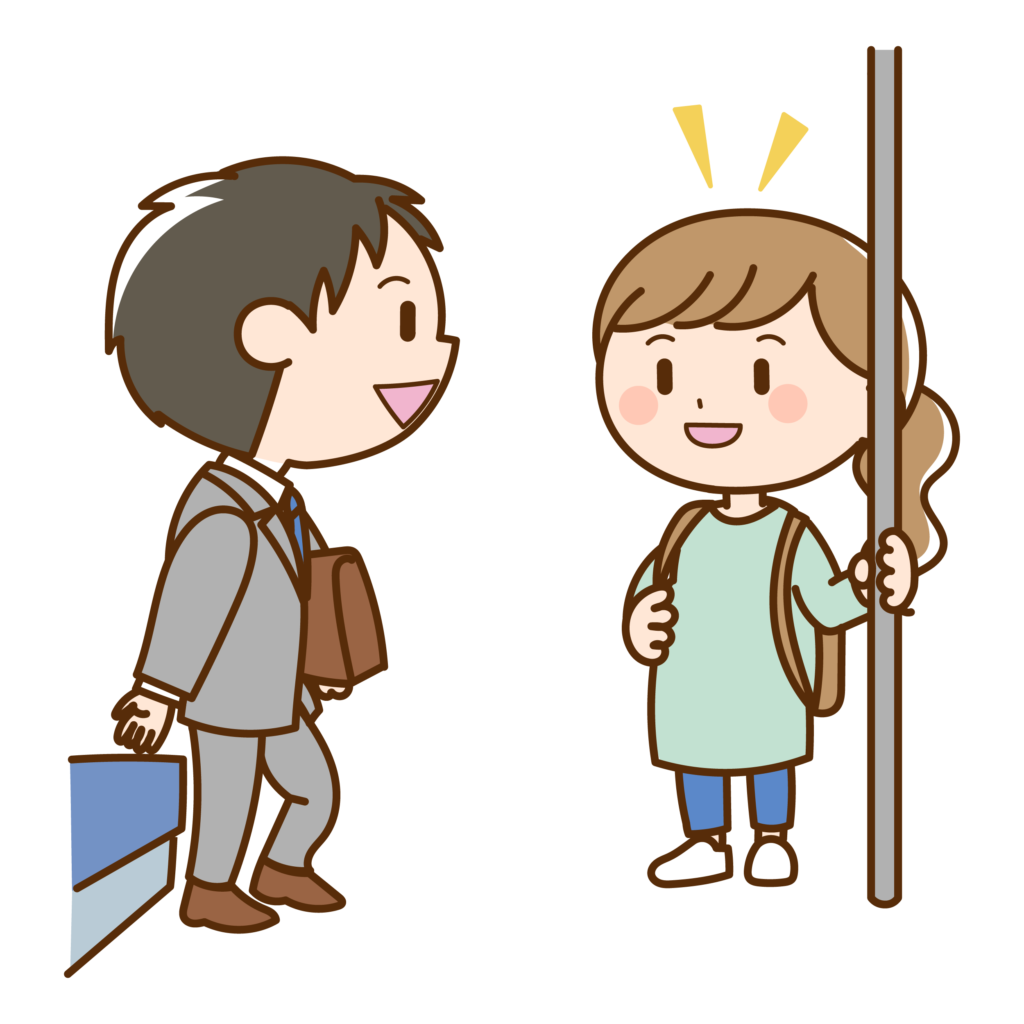
「いいことをしても報われないんじゃないか……」
そんな風に思ったことはありませんか?
でも、論語にはこんな言葉があります。
「徳は孤ならず、必ず隣あり」
これは、どんな意味なのでしょうか?
また、本当にそうなのか?
今回は、この言葉の意味を、たとえ話を交えながらご紹介します。
「徳は孤ならず、必ず隣あり」の意味と起源
この言葉は、孔子の弟子たちがまとめた『論語』(里仁第四)に出てきます。
「徳は孤ならず、必ず隣あり」
簡単に言うと、
「本当に徳のある人は決して孤独ではない。必ず共感し、助けてくれる人が現れる」
という意味です。
「徳」というのは、人徳や善い行いを指します。
誰も見ていなくても、誰かに評価されなくても、誠実で善い行いを続ける人は、やがてそれを認めてくれる仲間ができる、という教えなのです。
では、本当にそうなのか?
あるストーリーを通して考えてみましょう。
たとえ話
ある日の電車の中。
高校生のケンは、座席に座ってスマホをいじっていました。
ふと顔を上げると、おばあさんがつり革につかまりながら立っています。
「どうしよう……誰も席を譲らないな」
少し迷いましたが、ケンは意を決して立ち上がり、「どうぞ」とおばあさんに席を譲りました。
しかし、周りの大人たちはスマホを見ているだけ。
「ありがとうねぇ」とおばあさんは微笑んだけれど、なんとなく「なんで自分だけ?」という気持ちがよぎりました。
しかし、次の駅で乗ってきたサラリーマンが、ケンに声をかけました。
「君、えらいね。こういうのが本当の優しさだよ」
その人は、ケンに缶コーヒーを買って渡しました。
それを見ていた他の乗客も、次の駅で年配の人が乗ってくると、すっと席を譲る人が増えていきました。
ケンは思いました。
「僕ひとりじゃなかったんだ。ちゃんと見ている人がいるんだ」
「善い行いは、決して孤独じゃない」
この話のように、最初は一人だと思っても、誠実な行いはやがて誰かが気づき、共感し、広がっていきます。
最初に行動を起こすのは勇気がいることです。
でも、長い目で見れば、それは決して「孤独なもの」ではありません。
これこそが、孔子が言った「徳は孤ならず、必ず隣あり」の真意なのです。
まとめ:善い行いを続けよう
「こんなことしても、意味ないかも……」
そう思うことがあっても、本当に大事なことは、ちゃんと誰かが見ているのです。
最初は一人でも、やがてそれを認める仲間が増えていきます。
だからこそ、自分が信じる「善いこと」を続けていきましょう。
きっと、あなたの隣にも、同じ想いの人が現れるはずです。
それこそが、「徳は孤ならず、必ず隣あり」の教えなのです。
