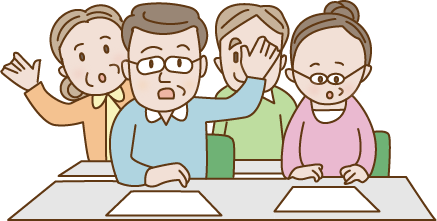
「学びは一生やめてはいけない」
子どもの頃は「勉強しなさい」と言われ、大人になると「もう勉強なんて…」と遠ざけがち。
でも、人生の中で本当に必要な「学び」は、むしろ年齢を重ねてからこそ深まるものかもしれません。
そんな“学ぶことの本質”を教えてくれるのが、この孔子の言葉です。
学は以て已むべからず
意味は、「学びは途中でやめてはいけない。一生続けるべきである」ということ。
これは、単なる“知識を増やす”ための勉強ではなく、「より良く生きるための学び」を説いた言葉なのです。
たとえ話
ある職人の話です。
Aさんは若い頃から技術を磨いて一流になりましたが、ある年を境に「もう十分だ」と学びをやめてしまいました。
一方、Bさんはベテランになっても「まだ知らないことがあるはず」と新しい素材や技術に触れ続けました。
数年後、時代が変わり新しいニーズが生まれたとき、Bさんの仕事は多くの人に求められるようになりました。
Aさんは時代に合わず、引退を余儀なくされたといいます。
この違いを生んだのは、「学びをやめたか、続けたか」。
まさに孔子の言葉を体現するようなエピソードです。
出典と解釈
この言葉は、『論語』の泰伯篇に登場します。
子曰く、学は以て已むべからず。青は之を藍より取りて藍よりも青く、氷は水これを為して水よりも寒し。木を瑩(みが)かざれば則ち不折(おれず)、金を礪(と)がざれば則ち不利なり。人の生くるや直し。学びて以てその道を成す。
孔子はこの中で、「学ぶことで人は素材以上の価値を持つ」と説いています。
- 染料の青は藍草から取るが、藍よりも青くなる
- 氷は水からできているが、水より冷たい
- 木や金属も磨かなければ本来の力を発揮できない
人もまた同じで、学ぶことで本来の能力を超え、輝きを増していく。
だからこそ、学びをやめてはいけないのです。
現代の視点で見る
今は時代の変化がとても早く、「一度覚えたこと」がすぐに通用しなくなることもあります。
- 技術の進化(AI・プログラミングなど)
- 社会の価値観の変化(働き方・暮らし方)
- グローバルな視野の必要性
こうした変化に柔軟に対応できるのは、「学ぶことをやめなかった人」だけ。
学び続けるという姿勢は、自分をアップデートし続ける力そのものです。
おわりに
孔子が伝えた「学は以て已むべからず」は、「学びとは人生そのものだ」というメッセージとも言えます。
- 本を読む
- 人の話に耳を傾ける
- 失敗から学ぶ
- 自分を見つめ直す
こうしたすべてが“学び”であり、それを続けることで、人として磨かれていく。
「もう学ぶことなんてない」と思ったときこそ、学びのスタートライン。
一生を通じて成長し続ける人でありたいですね。