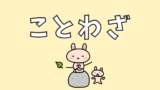「自分は何でもできる」
「一人で十分」
そう言い切れる人、あなたの周りにいませんか?
マルチなスキルを持つのは素晴らしいこと。
でも――それが時に、大きな落とし穴になることもあります。
孔子はそんな“万能タイプ”の落とし穴に、注意を促します。
「自分は多才だ」と思っている人ほど、真の成長が難しいと語るのです。
今回はその深い理由を、たとえ話や現代的な視点も交えて、やさしくひも解いていきましょう。
■ 論語の一節
「其の以て自ら多能とする者は、則ち難きかな」
(憲問〈けんもん〉篇より)
■ 意味をやさしく言うと…
-
自ら多能とする者:自分を「何でもできる人」と思っている人
-
難きかな:成長や向上が難しい、ということ
つまりこの言葉は、
「自分で“何でもできる”と思っている人は、それゆえに成長しづらい」
という意味になります。
■ たとえ話でイメージしてみよう
あなたの職場に、Aさんという社員がいます。
Aさんはプレゼンもできるし、資料も作れるし、プログラムも少しかじってる。
だから何でも一人でやってしまいます。
最初はすごいと思われていたけれど――
・部下に仕事を任せない
・周囲の意見を聞かない
・新しい学びにも興味を示さない
結果的に、成長が止まり、信頼も失ってしまいました。
「できることが多い」と思うと、謙虚さが失われる。
孔子が言いたいのは、まさにこうした落とし穴です。
■ 出典と背景
この章句は『論語』の「憲問篇」に記されています。
ここで孔子は、「あれもこれもできる」と自負している人に対して、真の賢者はもっと慎み深くあるべきだと警鐘を鳴らしています。
つまり、自分で自分を“万能”だと思った時点で、成長が止まってしまう――
それこそが“難しい”のだというのです。
■ 現代にどう生かせる?
-
「自分にはまだまだ学ぶことがある」と認識し続ける
-
他人の意見に耳を傾ける
-
得意な分野でも「完璧ではない」と思える柔軟性を持つ
-
周囲と協力し、チームの力を大切にする
スキルを広げることは素晴らしい。
でもそれを**「自分は完璧」と勘違いした瞬間から、進歩は止まる**のです。
■ まとめ
自信が成長の妨げになることもある。
本当に賢い人は、自分の限界を知っている。
「何でもできる」は素敵なこと。
でも、何でもできる“つもり”が、一番の敵になることもある。
孔子のこの言葉は、「謙虚に学び続ける姿勢」こそ、真に賢い人のあり方だと教えてくれているのです。