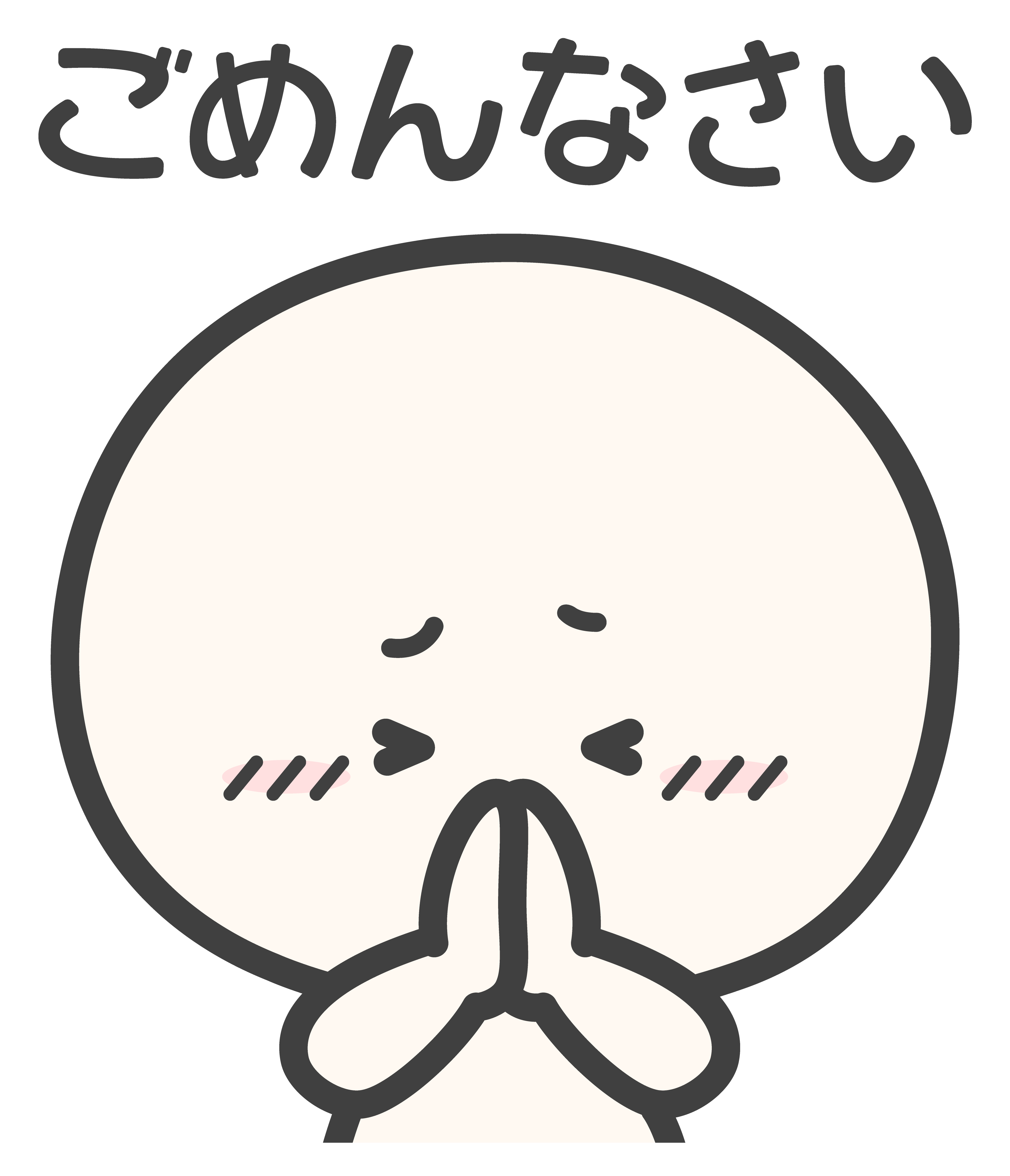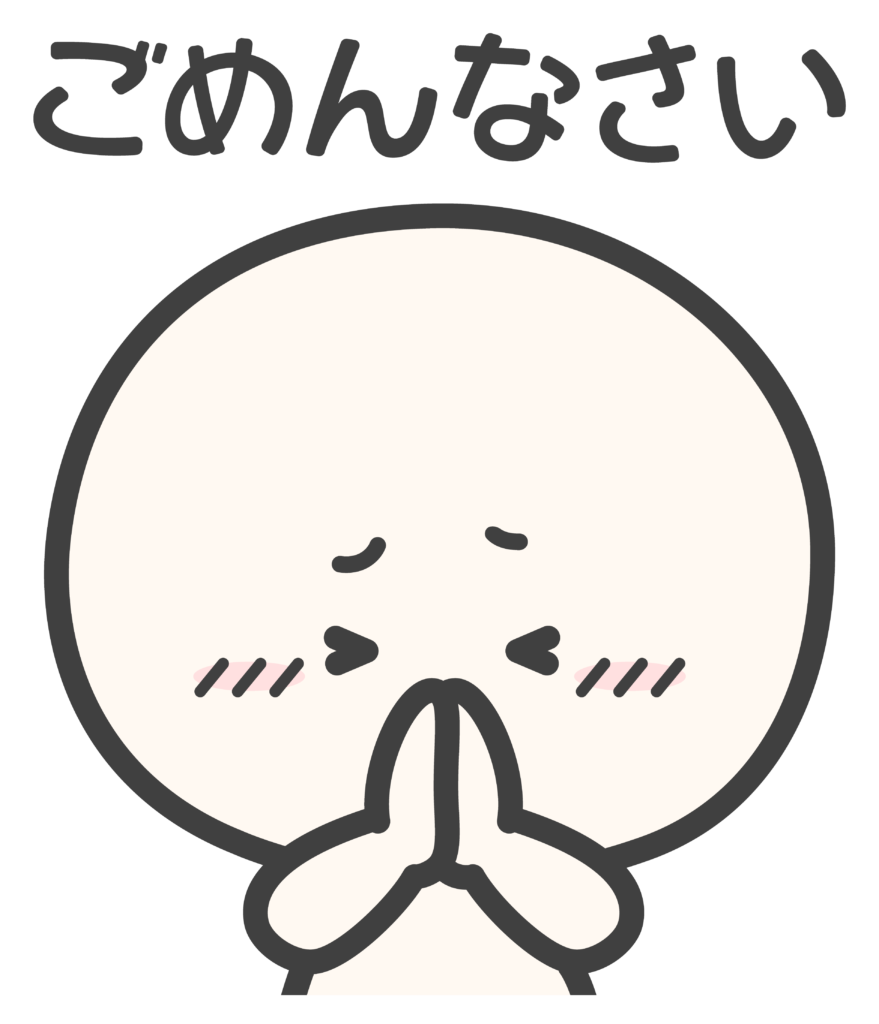
過ちは誰にでもある。だからこそ大切なのは…
人は誰しも、完璧ではありません。
仕事でのミス、友人とのすれ違い、無意識のうちに人を傷つけてしまった言動…。
「ああ、やってしまった」と落ち込むこと、きっと誰しも一度や二度ではないはずです。
でも、ここで大事なのは「そのあとの姿勢」です。
自分の過ちに気づいたとき、素直に認め、行動を改めること。
それこそが、人としての成長につながるのです。
そんな教えを、紀元前の中国の思想家・孔子は、こんなふうに表現しました。
論語の言葉
「過ちては則ち改むるに憚ること勿れ」
『論語』衛霊公篇より
意味:過ちに気づいたら、ためらわずにすぐに改めなさい。
たとえ話
ある日、小学生のタカシくんは、夕食の時間に誤ってジュースの入ったコップを倒してしまいました。
テーブルはベタベタ、床にもジュースが広がり、お母さんは少し困った顔をしています。
タカシくんは、一瞬「知らんぷりしようかな」と思いました。
でもすぐに「ごめんなさい!」と謝り、タオルを持ってきて一緒に片付けを始めました。
その姿を見たお母さんは、「ちゃんと謝って、自分で拭いてえらいね」とにっこり。
ミスをしない人はいません。
でも、「すぐに改めることができる人」は信頼され、成長します。
まさにこの言葉の精神が、タカシくんの行動には表れていたのです。
この言葉が生まれた背景
この言葉が収められている『論語』は、孔子とその弟子たちの言葉を集めた書物です。
「衛霊公篇」では、主に政治やリーダーシップについての教えが多く語られています。
この章で孔子が伝えたかったのは、「指導者であれ一般人であれ、間違いを恐れず、正すことを恐れるな」という姿勢です。
孔子は理想の人物像を「君子」と呼び、その君子の条件の一つとして、「過ちを改める素直さ」を何度も強調しています。
まとめ
過ちは恥ずかしいことではありません。
それよりも、
「間違いを認められないこと」
「改めるのを先延ばしにすること」
のほうが問題です。
この論語の教えは、現代のビジネスシーンでも、人間関係でも、子育てにも生かせる普遍的なもの。
間違えたときは、深呼吸して、「さあ、どう改めよう?」と一歩踏み出してみましょう。