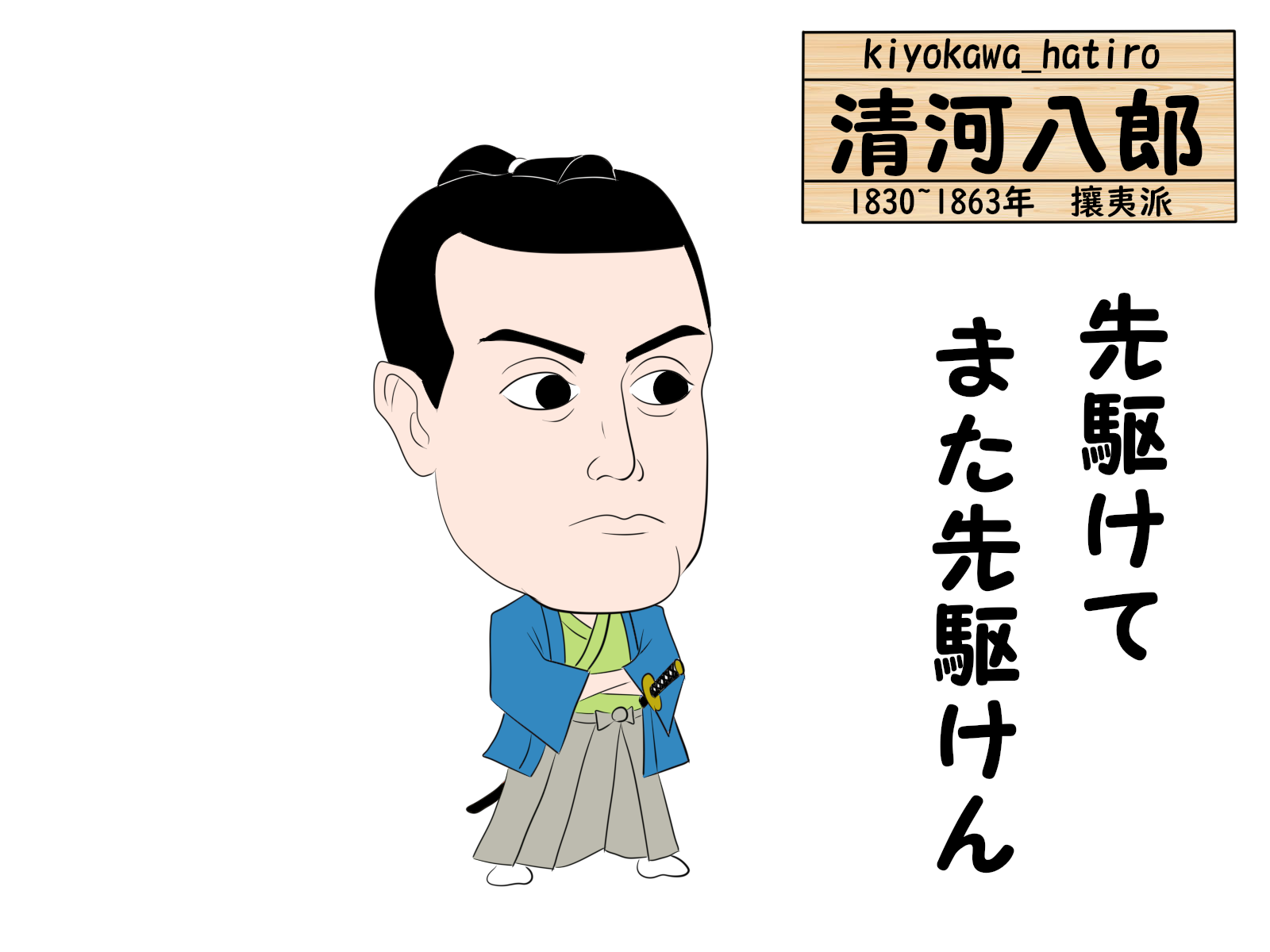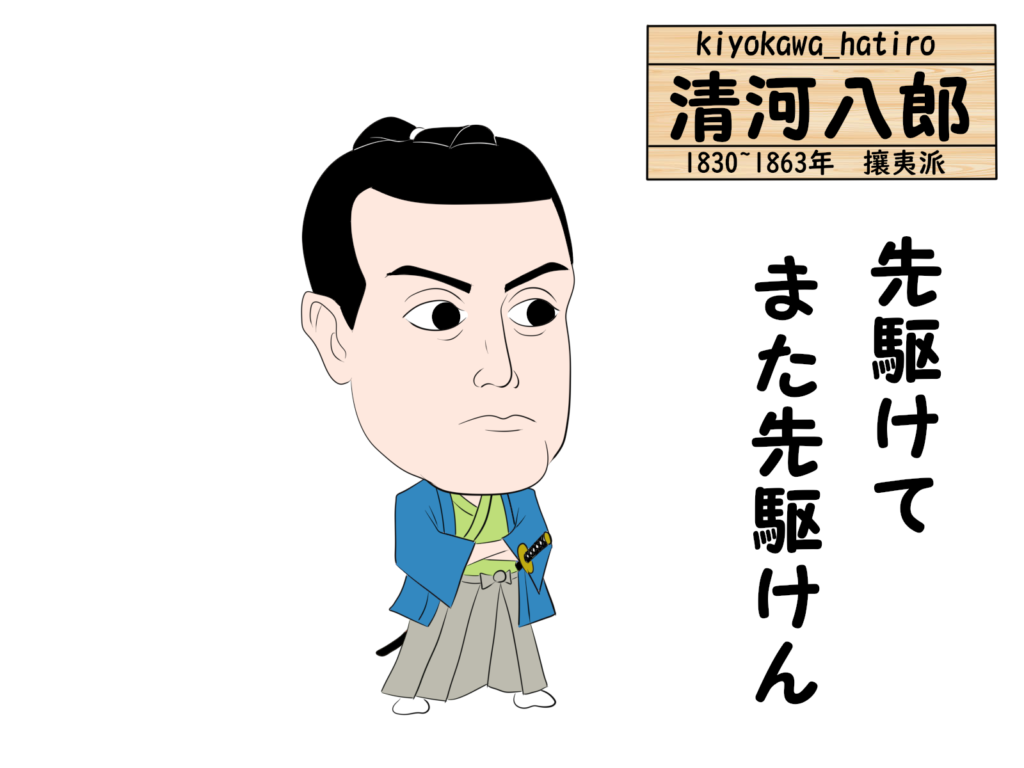
清河八郎。
幕末の動乱の中に、静かにして鋭く、その名を刻んだ男。
彼は浪士を集め、幕府に仕え、そしてその裏で、尊王攘夷を叫んだ。
信念か、策謀か。
その行動は、誰にも読めなかった。
けれど確かに、時代を動かす核のひとつだった。
出羽の国、貧しき庄屋の子として
1830年、出羽国(現在の山形県)に生まれる。
貧しい庄屋の家に育ちながら、幼い頃から学問に励んだ。
江戸に出て儒学を学び、次第に世の乱れと向き合うようになる。
彼の中に燃えていたのは、「国を憂う」熱だった。
その憂国の情は、やがて行動となって現れる。
勝海舟とも関わり、密かに攘夷を志す
剣も学び、思想も磨いた彼は、幕府の要人とも接点を持つようになる。
中でも勝海舟とは深く交流し、その知見を学んだ。
だが同時に、尊王攘夷の思想も胸に秘めていた。
幕府の中に入りながらも、倒幕を視野に入れる。
その二面性こそが、彼の行動を複雑にしていく。
浪士組を結成――その真の狙いは
1863年、清河八郎は幕府の命を受け、「浪士組」を結成。
浪士たちを率い、将軍警護の名目で京都へと向かう。
だが京都に着いた途端、彼はこう言い放った。
「我々の使命は、尊王攘夷である」
驚いたのは、幕府と共に来た浪士たちだった。
これに反発し、残った者たちがのちの「新選組」となる。
彼は意図して、幕府の中に尊王の種をまいたのだった。
暗殺――その死もまた、謎に包まれる
江戸に戻った彼は、朝廷との関係を深めるべく奔走する。
だがその最中、幕府の刺客によって暗殺された。
わずか33年の生涯。
その死には、複数の説がある。
「幕府に裏切られた」
「朝廷の信用を失った」
「ただ危険視され、消された」
誰のために、何を信じて動いていたのか――今も多くが語られる。
まとめ
清河八郎の一生は、短くも濃く、謎に満ちている。
裏切り者と呼ぶ者もいれば、先見の志士と語る者もいる。
彼の真意は、今も定かではない。
だが確かに、幕末という巨大なうねりの中に、彼はいた。
しかも、ど真ん中に。
策士か、志士か。
その両方だったのかもしれない。
たとえ理解されなくとも、彼は動いた。
日本のために、何かを変えようと。
それが――清河八郎。