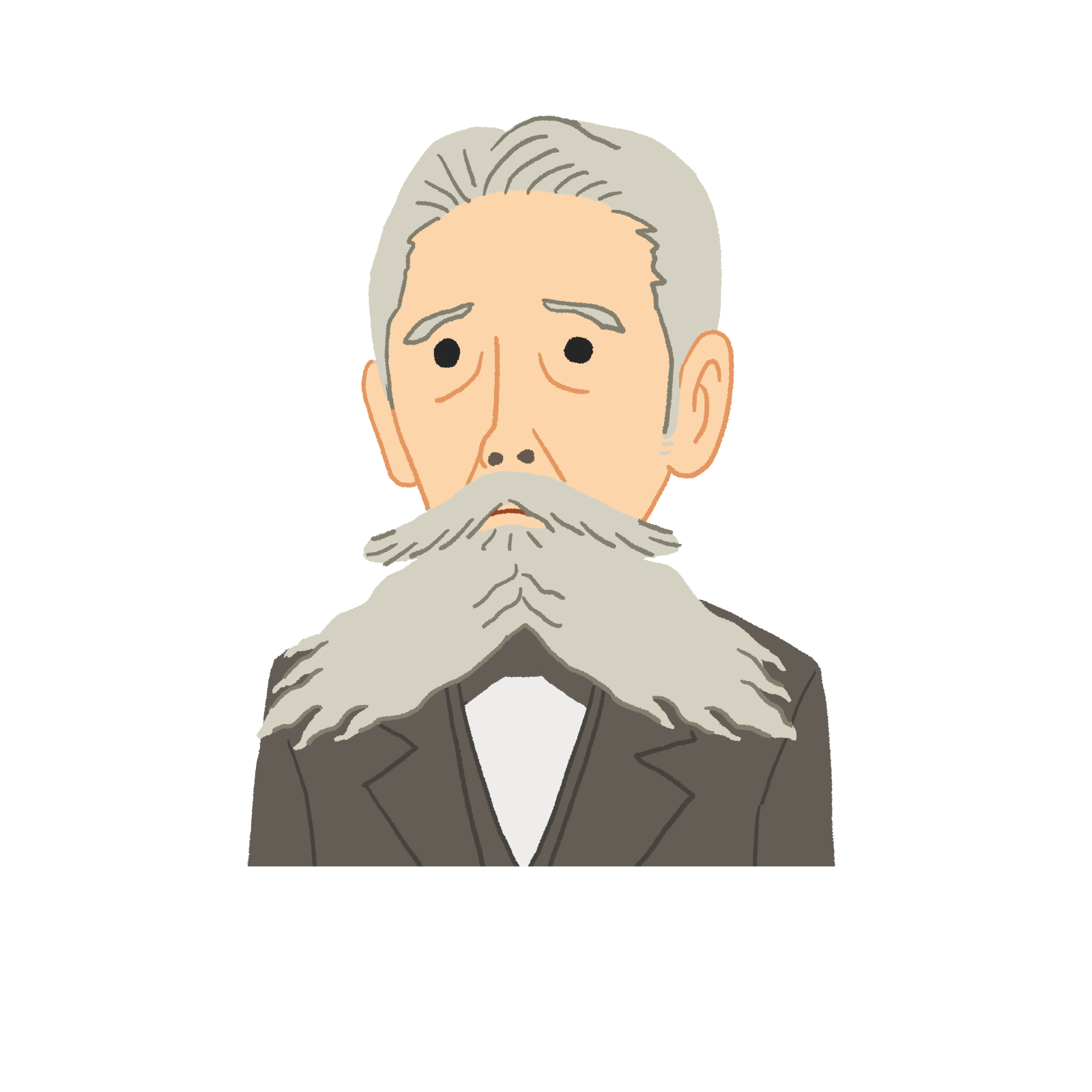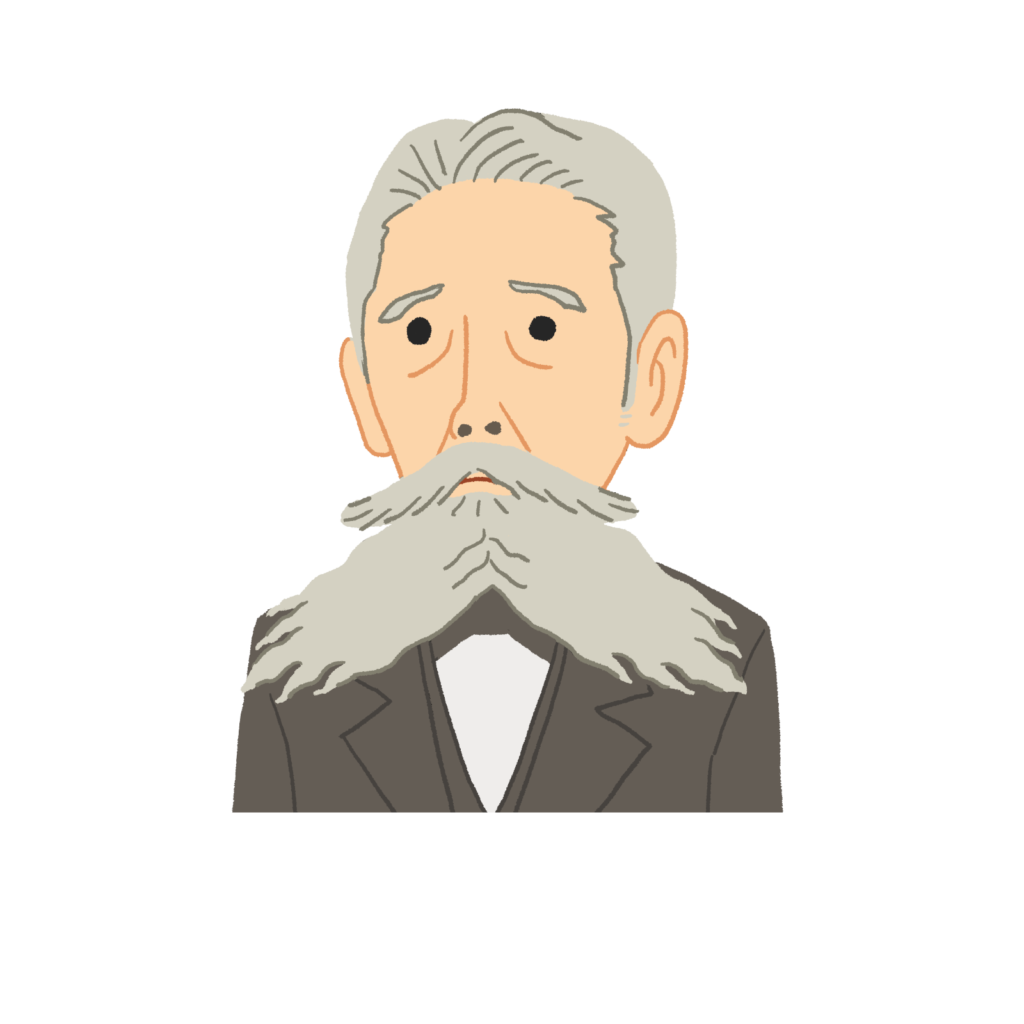
板垣退助。
土佐藩士として幕末を戦い抜いた男は、
明治になると、「自由民権」という新しい戦場へと向かった。
「人は、政府に従うだけでなく、自ら声を上げるべきだ」
そう信じた彼は、何度も立ち上がり、何度も退けられた。
それでもなお、叫び続けた。
自由を、民の力を、日本に根づかせるために。
土佐藩、戊辰戦争、そして維新へ
1837年、土佐に生まれる。
剣術を学び、藩の尊王攘夷派として頭角を現した。
幕末の動乱では、岩倉具視や西郷隆盛らと連携し、王政復古の立役者となる。
戊辰戦争では、政府軍の参謀として全国を転戦。
その功績で明治政府に迎えられる。
だが、彼の本当の戦いは、ここから始まった。
政府を飛び出し、民の側へ
明治新政府の中で、次第に大久保利通らと対立するようになる。
中央集権、官僚主導の政治に疑問を抱いた。
「民の声を、もっと政治に生かすべきだ」
1873年、征韓論をめぐる政争で政府を辞職。
その後、民間に身を置き、「自由民権運動」を始める。
街頭に立ち、演説をし、民衆と語り合った。
農民も、町人も、言葉を持つ時代を望んでいた。
彼のまわりには、若き志士たちが集まり始める。
演説中の襲撃――命を懸けた自由
1882年、岐阜での演説中。
突然、暴漢がナイフを振りかざし、彼を刺した。
血に染まりながらも、板垣退助は叫んだ。
「板垣死すとも、自由は死せず!」
その言葉は、民衆の心に深く刻まれた。
彼が命をかけて訴えたものの重さが、伝わった瞬間だった。
この事件を機に、自由民権運動はさらに全国に広がっていく。
民主政治の土台をつくった
やがて、大日本帝国憲法の公布、帝国議会の開設へと道は続く。
板垣自身も、初代内務大臣を務めた。
だが彼の心は、あくまで「民」の側にあった。
「国は、民のためにある」
その思想は、やがて後進たちへと受け継がれていく。
自由、選挙、言論、議会――
いま私たちが当たり前に享受しているその多くを、彼は命がけで育てたのだった。
まとめ
板垣退助の人生は、剣から言葉へ、戦から政治へと変わっていった。
だがどんな時も、信じていたものは変わらない。
「人には、自由があるべきだ」
その当たり前が、当たり前でなかった時代に、彼は声を上げた。
そして、その声が時代を動かした。
民の声を、国の力に。
それが――板垣退助。