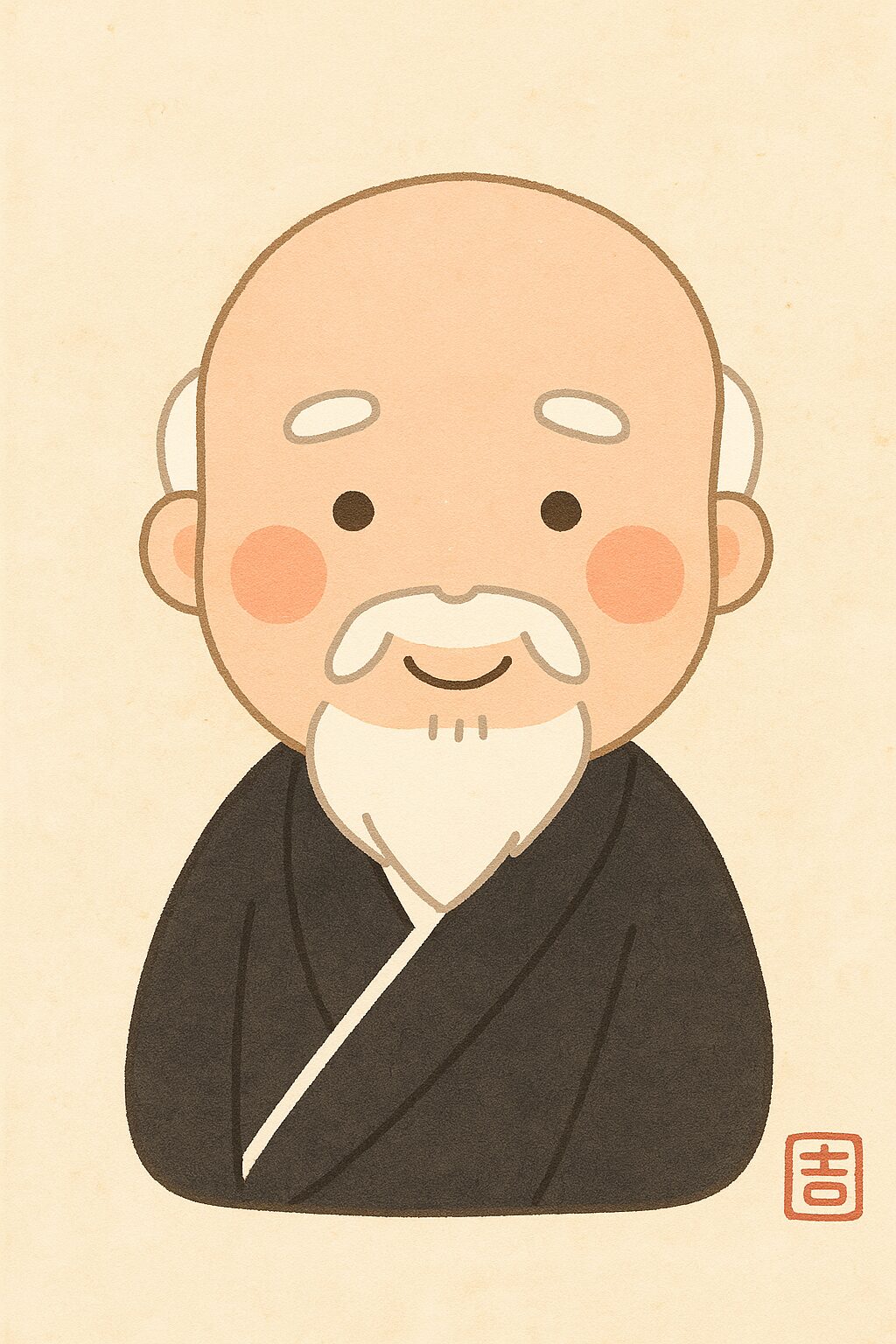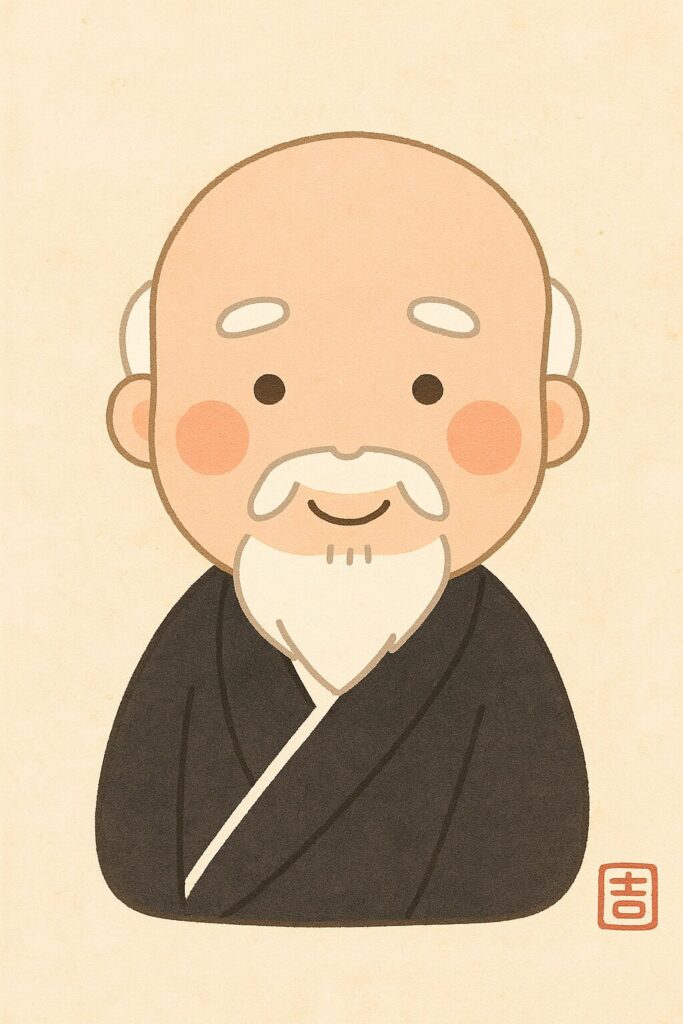
田中久重。
江戸時代の終わり、博多の町に一人の“機械の天才”が生まれた。
大工のせがれとして育ち、手先の器用さと知恵を武器に、
やがて「からくり儀右衛門」と呼ばれるほどの職人となる。
だが彼は、ただの“おもちゃづくり”に満足する男ではなかった。
蒸気機関、電信機、発電機――。
その目は、明治の夜明けを見据えていた。
江戸の庶民を驚かせた「からくり」の天才
1799年、筑前国(いまの福岡県)で誕生。
幼い頃から物づくりが好きで、見るものすべてを分解しては組み立てた。
やがて、江戸や大阪に出て、“からくり”を使った見世物で人気を集める。
特に有名なのが、「弓曳童子」や「文字書き人形」。
ただ動くだけでなく、「考えているように見える」その精巧さに、
見た人々は驚き、笑い、立ち止まった。
彼は、楽しませることが好きだった。
驚かせることが、何よりの喜びだった。
そしてその心は、やがて“日本の技術の礎”へと向かっていく。
黒船が見せた世界に、挑み続けた
1853年、ペリー来航。
蒸気船、測量機、電信――西洋の技術が、突如として日本の目の前に現れた。
多くの者が立ち尽くす中、田中久重は言った。
「自分でつくってみよう」
西洋の本もない、教科書もない。
だが彼は、自分の手と目で、蒸気機関の模型をつくり上げた。
電信機を試作し、長崎で開通実験も行った。
幕末の日本に、電気の時代が来ることを、彼は信じていた。
明治へ――「田中製作所」の誕生
明治に入り、政府の要請で上京。
1869年、東京・銀座に「田中製造所(のちの東芝)」を創設する。
彼の製作所では、蒸気機関や測量器、そして発電装置などが次々と生まれた。
「日本の手で、日本の未来をつくる」――その想いが、職人たちに受け継がれていった。
老いてなお、久重は現場に立ち続けた。
目を光らせ、若き技術者の中に混じって、黙々と工具を握っていた。
晩年、明治政府から感謝され、静かにその生涯を閉じる。
けれど彼の残したものは、いまも電気の中に、機械の中に、生きている。
まとめ
田中久重は、肩書きも学歴もなかった。
けれどその頭と手と心で、日本の近代技術を切り拓いた。
「職人」が時代を動かすことを、身をもって示した人だった。
そしてその志は、「東芝」という名の企業へと引き継がれていく。
からくりで笑わせ、機械で驚かせ、技術で未来をつくった。
それが――田中久重。