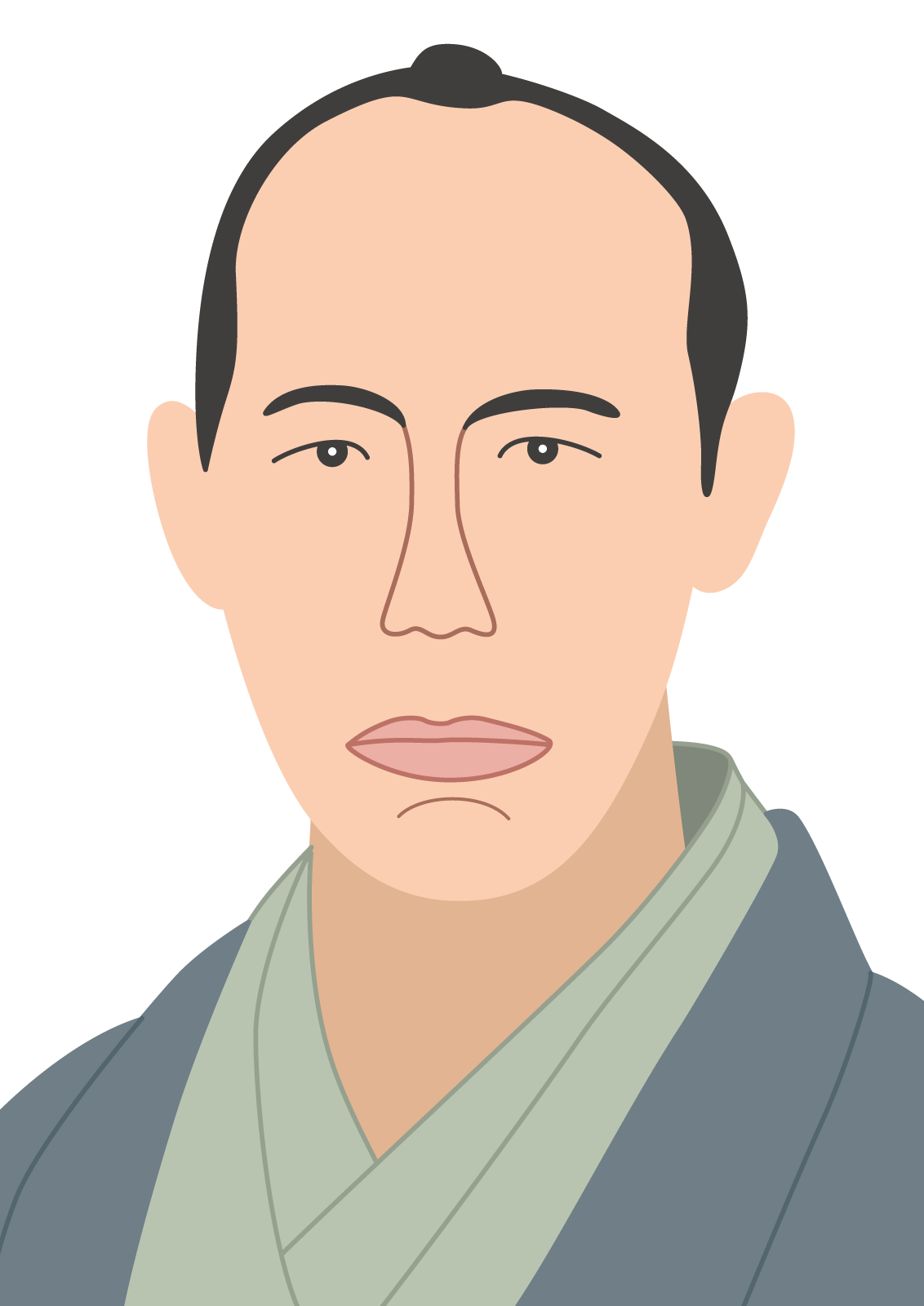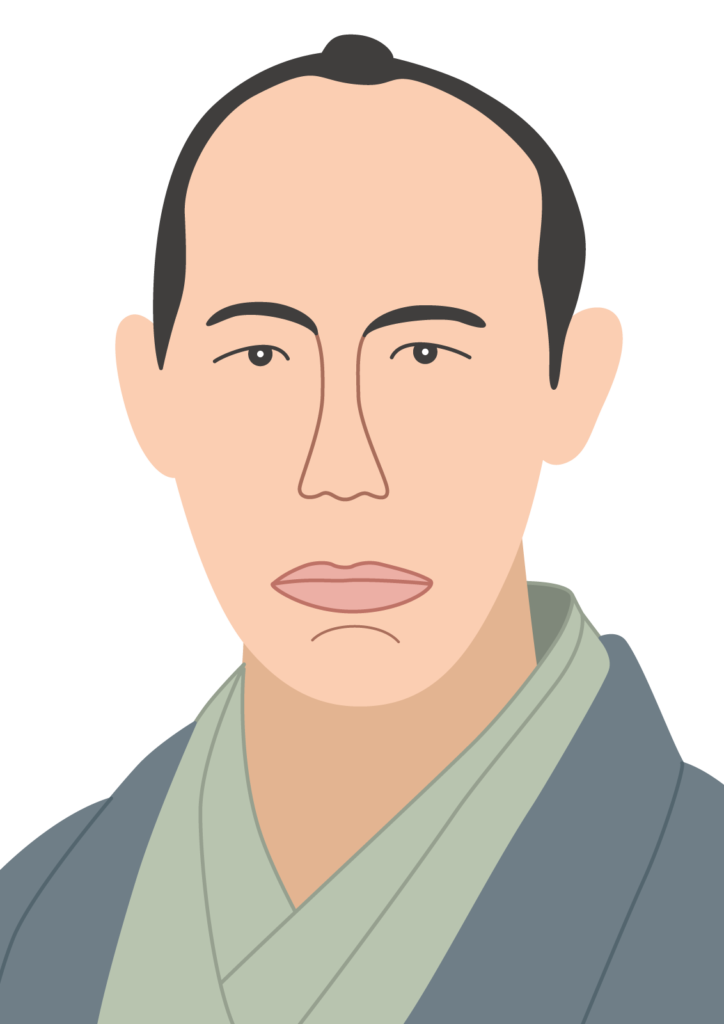
松平春嶽。
徳川一門でありながら、幕府にしがみつかなかった男。
将軍の座を狙わず、ただ、「日本のかたち」を案じ続けた。
開国か、攘夷か。
幕府か、倒幕か。
多くが剣を抜き、拳を握る中で、春嶽は静かに知恵を磨いた。
歴史の表舞台にはあまり出ない。
けれど、多くの“あの決断”の背後に、この男の影があった。
幕末の名門・福井藩主にして、徳川一門
松平春嶽は、1810年に江戸で生まれる。
将軍家とも縁の深い、徳川家の一族。
福井藩(越前松平家)を継ぎ、若くして藩主となった。
だが、その人生は安泰ではなかった。
藩財政は逼迫し、改革は待ったなし。
春嶽は、思い切った人材登用を進める。
橋本左内、由利公正――
のちの明治を支える若者たちに、自由に意見を言わせた。
彼にとって、家柄や年齢は問題ではなかった。
「今、必要な者を使う」
それが、春嶽の信念だった。
黒船と開国の衝撃。決断を迫られる幕府
1853年、ペリーが浦賀に来航。
幕府は開国か攘夷かで揺れた。
春嶽は考えた。
今の日本に攘夷などできる力はない。
ならば、開国と近代化。
ただし――日本の心を忘れぬままに。
彼はそう言って、国の方針に口を出し始める。
「越前の殿様」と呼ばれた春嶽は、やがて幕政の中枢へと引き上げられる。
一橋慶喜の将軍擁立、そして政治総裁職へ
将軍を誰にするか――。
幕府最大の課題に直面したとき、春嶽は、徳川慶喜(のちの十五代将軍)を推した。
「時代の目を持つのは、この男だ」
そう信じて、一橋派をまとめた。
そして彼自身も、幕政改革を担う「政治総裁職」に就任。
だが、改革は容易ではなかった。
守旧派の反発。
長州・薩摩の動き。
混迷の中、彼は静かに、政の裏を支えた。
最後まで「中庸」を貫いた政治家
幕府にも、倒幕にも寄りすぎない。
春嶽は最後まで「中庸」を目指した。
敵を作らぬように、ではない。
どちらにも偏ってはいけない――
それが、この国を守る道だと信じていた。
彼の姿勢は、時に“優柔不断”と揶揄された。
けれど、誰よりも先に、近代国家のかたちを描いていたのは、
松平春嶽だった。
まとめ
松平春嶽は、戦場に出ることも、血で血を洗う決断をすることもなかった。
けれど、彼がいたから救われた命があった。
彼がいたから、繋がった知恵があった。
将軍ではなかった。
だが、政のど真ん中にいた。
静かに、柔らかく、強く――
彼の生き方は、まさに「幕末のもう一つの理想」だった。