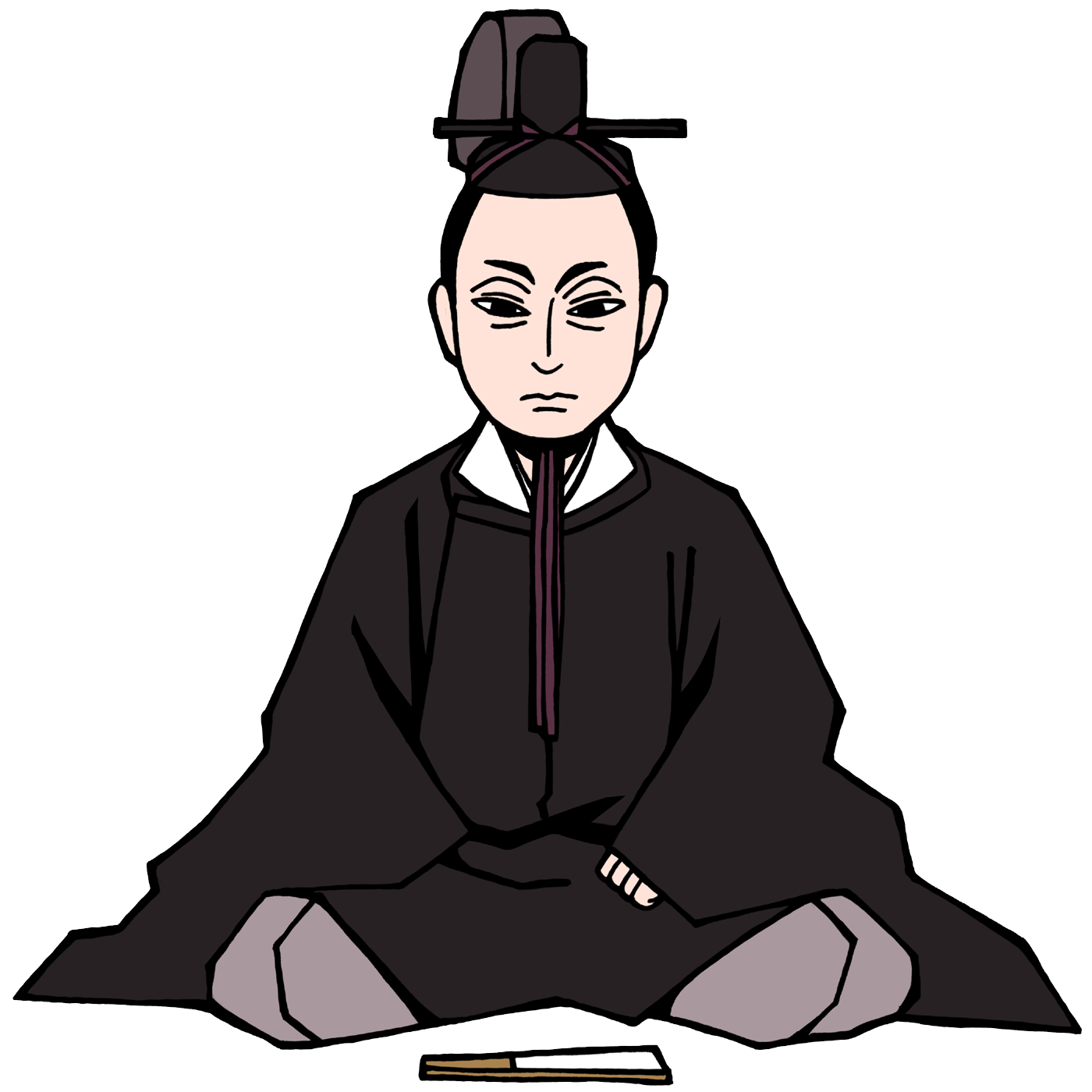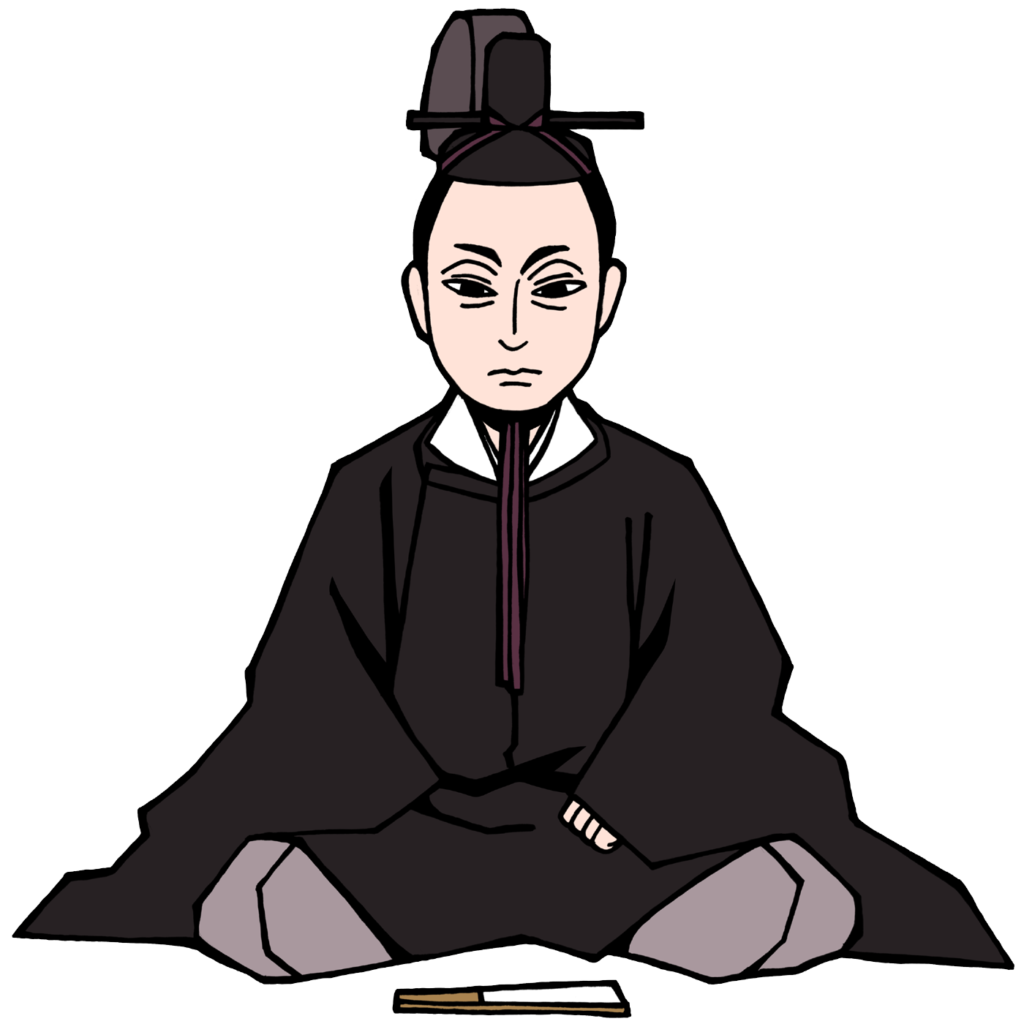
徳川慶喜。
将軍になったその手で、徳川を終わらせた男。
戦わずして退いた将軍。
逃げたとさえ言われたこともある。
だが、本当にそうだったのか。
彼の選択は、誰よりも重く、誰よりも現実的だった。
日本を守るために、「徳川」という名前を自ら手放した。
それが、最後の将軍・慶喜の生き方だった。
将軍の器と呼ばれた、若きプリンス
徳川慶喜は1837年、水戸藩主・徳川斉昭の七男として生まれた。
聡明で礼儀正しく、幼い頃からその器量は評判だった。
将軍家の血を引き、しかも頭が切れる。
次第に「将軍候補」として名が挙がるようになっていく。
当時の将軍・家定に後継がいなかったこともあり、
「次の将軍は誰か」を巡る政争が巻き起こる。
慶喜は「一橋派」の推す筆頭だった。
その後ろには、松平春嶽や島津斉彬といった実力者が並んでいた。
だが幕府内部の争いの中で、慶喜は表舞台から一度退く。
だがその静けさの裏で、彼は何度も機会を見ていた。
十五代将軍にして、最後の将軍
1866年、十四代・徳川家茂が若くして死去。
幕府の混乱の中、再び「慶喜」の名が浮上する。
同年、慶喜はついに第十五代将軍に就任。
だが、幕府の力はすでに落ちていた。
諸藩は幕府を支えようとせず、
薩摩・長州はすでに倒幕に向かって動いていた。
慶喜は考えた。
このまま戦を続ければ、民が死ぬ。国が割れる。
だからこそ、彼は「大政奉還」を決意する。
政権を朝廷に返すことで、徳川の名で戦を終わらせる。
慶応3年(1867年)、慶喜は政権を天皇に返上した。
それは、260年以上続いた江戸幕府の終焉だった。
戦わずして退く。誤解された背中
慶喜は、その後も静かだった。
戊辰戦争が始まっても、江戸から動かず、
静かに謹慎し、戦を止めようとした。
だが、その姿勢は「逃げた」「腰抜け」などと評された。
後世の一部では「戦うべきだった」とも言われる。
けれど、慶喜は知っていた。
戦っていたら、もっと多くの命が失われていただろう。
彼は「徳川」を守るより、「日本」を守る道を選んだ。
それが、彼なりの将軍としてのけじめだった。
晩年は静かに、自転車と写真と共に
明治の世になってから、慶喜は公職に就くことはなかった。
静岡で謹慎を終えたのち、東京に戻り、趣味に没頭する日々。
自転車に乗り、写真を撮り、書をたしなむ。
その姿は、かつての将軍とは思えぬほど穏やかだった。
彼のもとに多くの旧臣が訪ねてきたが、慶喜は多くを語らず、ただ微笑んでいたという。
最後の将軍として、誰よりも重いものを背負った男。
その静かな晩年は、平和の証だったのかもしれない。
まとめ
徳川慶喜は、戦わなかった。
けれど、それは勇気がなかったからではない。
戦わずして時代を引き渡す。
その重さと苦しみを、彼は引き受けた。
彼の静かな背中がなければ、
今の日本はもっと血に染まっていたかもしれない。
最後の将軍・徳川慶喜。
その決断の意味は、今も私たちに問いかけている。