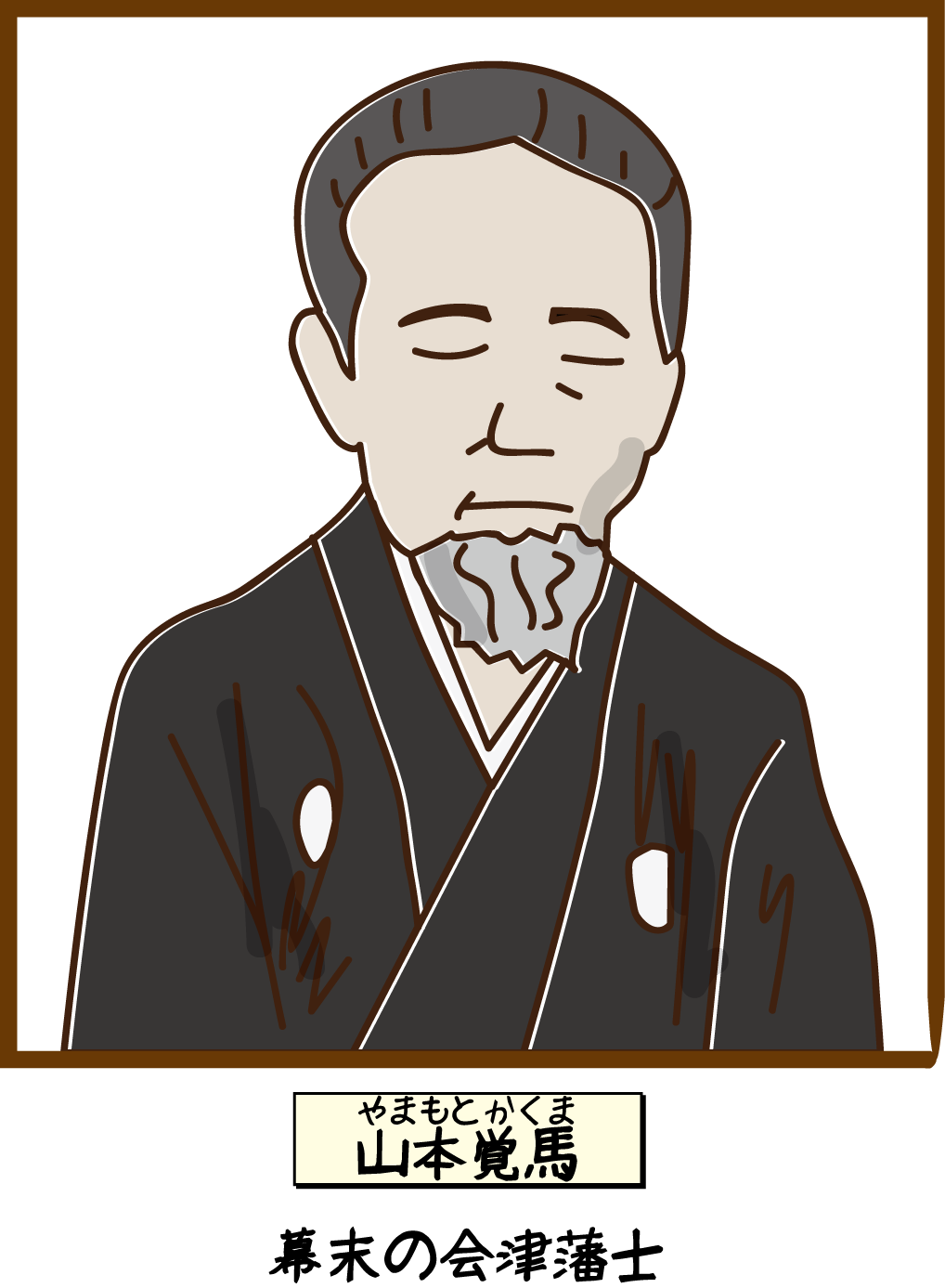山本覚馬。
会津藩の一藩士にして、思想家。
鉄砲に長け、西洋学に通じ、そして、やがて光を失いながらも、世の中の行く先を見つづけた。
彼が願ったのは、「誰もが学べる国」。
幕末から明治へ――
混沌の時代に、彼は静かに、確かに、未来を照らす光となった。
会津の鉄砲指南役として生まれる
1828年、会津藩士の家に生まれる。
家は代々、鉄砲の指南役。
幼いころから銃の技術に秀でていた。
だが、それだけではなかった。
彼は書物を好み、西洋の学問に強く惹かれた。
やがて江戸へ、京都へ。
そして長崎で蘭学、さらに洋式兵学を学ぶ。
「知」と「戦」の両面で、彼は頭角を現していった。
禁門の変と、目の病
1864年、長州征討をめぐり、京都は混乱に包まれる。
会津藩も出兵し、覚馬も出陣。
だが、その最中、彼の目に異変が起きる。
進行性の病――失明だった。
それでも、彼は引かなかった。
目は見えなくても、心の目は開いていた。
戦のあと、京都に残され、そこで彼の“もうひとつの生涯”が始まる。
新政府に身を投じる
明治維新が起きると、かつての会津藩士であるにも関わらず、新政府に参加。
京都府顧問として抜擢され、学校設立に尽力する。
彼が目指したのは、身分を問わず誰もが学べる国。
西洋の自由思想や産業育成を学びながら、
未来の日本の礎を築いていった。
視力を失っても、光を描き続けた
このころには、完全に視力を失っていた。
だが、覚馬の発する言葉には、希望があった。
彼の書いた『管見』という意見書は、新政府の制度設計にも影響を与えたと言われる。
見えないはずの男が、見通していた未来。
新島襄との出会い、そして妹・八重
覚馬は、同志社大学の創立者・新島襄と出会い、深く共鳴する。
教育を通じた国づくり。
それは、まさに覚馬の理想だった。
そして彼には、ひとりの妹がいた。
山本八重。
銃を手に会津を守り、「幕末のジャンヌ・ダルク」と称された女性。
覚馬は、彼女の未来を信じ、見守り続けた。
静かに、しかし大きく時代を変えた
政治家でもなければ、武将でもない。
だが、彼が残した影響は計り知れない。
教育の礎、女性の地位向上、西洋的自由の価値。
そのすべての“種”を、日本にまいたのが山本覚馬だった。
まとめ:光を失って、未来を見た男
山本覚馬は、目が見えなくなっても、
時代の先を見通していた。
戦を知り、学を知り、
そして、新しい国の形を考えた。
その姿は静かだが、凛として美しい。
見えぬ未来に、希望の光を。
彼の人生そのものが、幕末から明治をつなぐ灯だった。