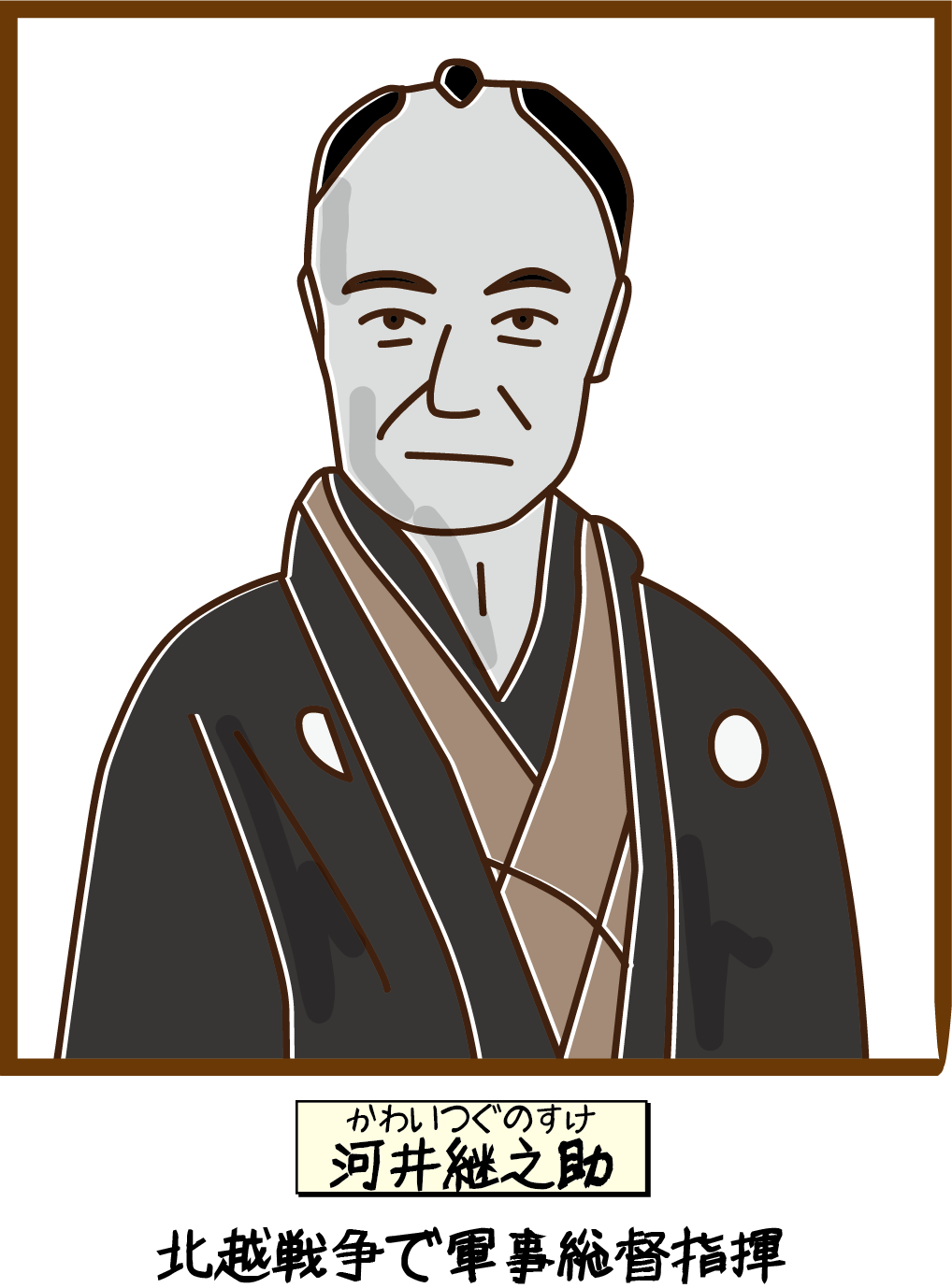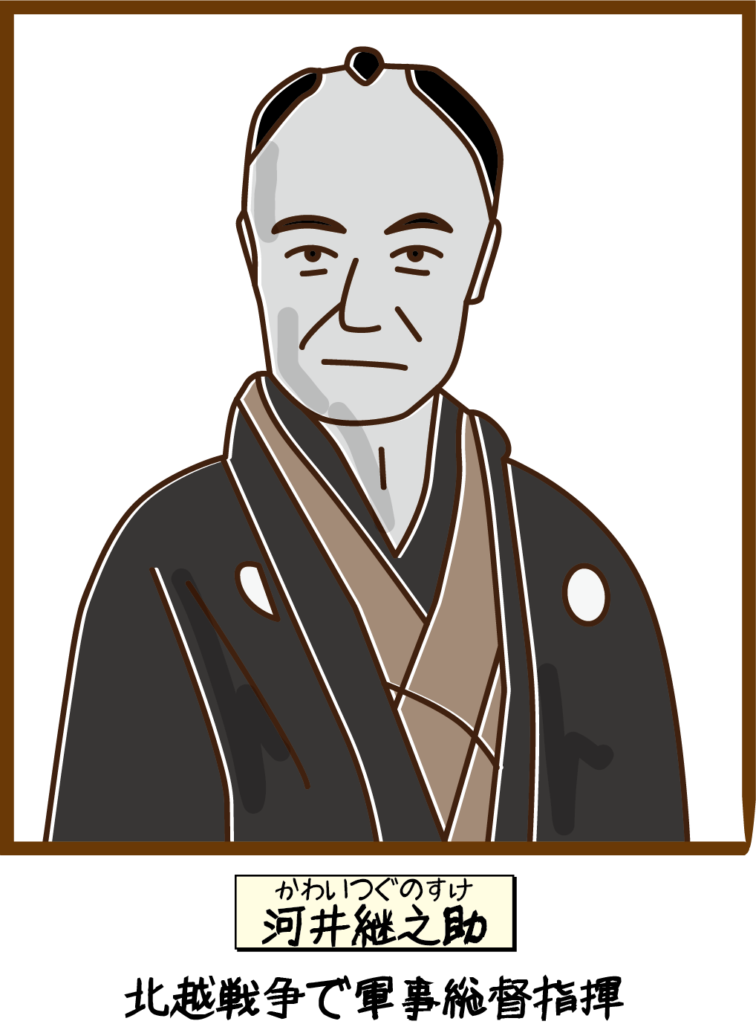
河井継之助。
越後長岡藩のひとりの藩士。
けれど彼の思想と行動は、ひとつの国を動かそうとしていた。
本を読み、世界を知り、
そして、鉄砲を手にした。
彼が選んだのは、「戦わずに護る」という、苦い戦いだった。
幼いころから学を志す
1827年、越後長岡に生まれる。
幼いころから頭の良さが光っていた。
寺子屋では手がつけられぬほど学問に熱中し、
やがて江戸へと遊学。
佐久間象山や横井小楠など、開明派の思想家に学ぶ。
そこで彼は、世界を知り、日本を見つめ直すことになる。
藩政改革に乗り出す
帰郷後、彼は家老にまで登りつめる。
長岡藩は小藩でありながら、財政は逼迫していた。
継之助はそこに大胆な改革を断行する。
質素倹約、財政再建、そして西洋式軍備の導入。
保守的な藩内では反発も多かった。
だが、彼の熱意と理想は、少しずつ人々を動かしていく。
戊辰戦争と中立の選択
1868年、戊辰戦争が勃発。
新政府と旧幕府――日本が真っ二つに割れたとき、
継之助は「どちらにも与せず」と宣言する。
長岡藩は中立を保とうとした。
戦ではなく、話し合いで国を動かす。
それが、彼の理想だった。
戦わざるを得なかった日
だが、新政府軍は中立を許さなかった。
「どちらでもない者」は、敵とみなされた。
やがて戦火が長岡に迫る。
継之助は決断する――やるなら、徹底的にやる。
彼はオランダ製の最新兵器「ガトリング砲」を導入。
小さな藩に、強大な火力を持たせた。
長岡城奪還、そして敗走
激戦の末、一度は落とされた長岡城を、彼は奪還する。
奇跡とも言われた反撃だった。
だが、それも束の間。
物量に勝る新政府軍に押され、長岡はふたたび陥落。
彼は負傷を負い、会津方面へと逃れる。
山中で静かに息を引き取る
傷は深く、出血は止まらなかった。
峠を越えたその先で、彼は静かに命を閉じる。
わずか40歳。
彼のポケットには、戦火の中でも大切にしていた本があった。
理想と現実のはざまで、最後まで知を手放さなかった。
まとめ
河井継之助は、変革の時代にあって、
戦わずして守るという、困難な道を選んだ。
けれど歴史は、その理想の重さを知っている。
戦場にあっても、彼のまなざしは未来に向いていた。
知と勇気と、静かな誇り。
それが、河井継之助という男だった。