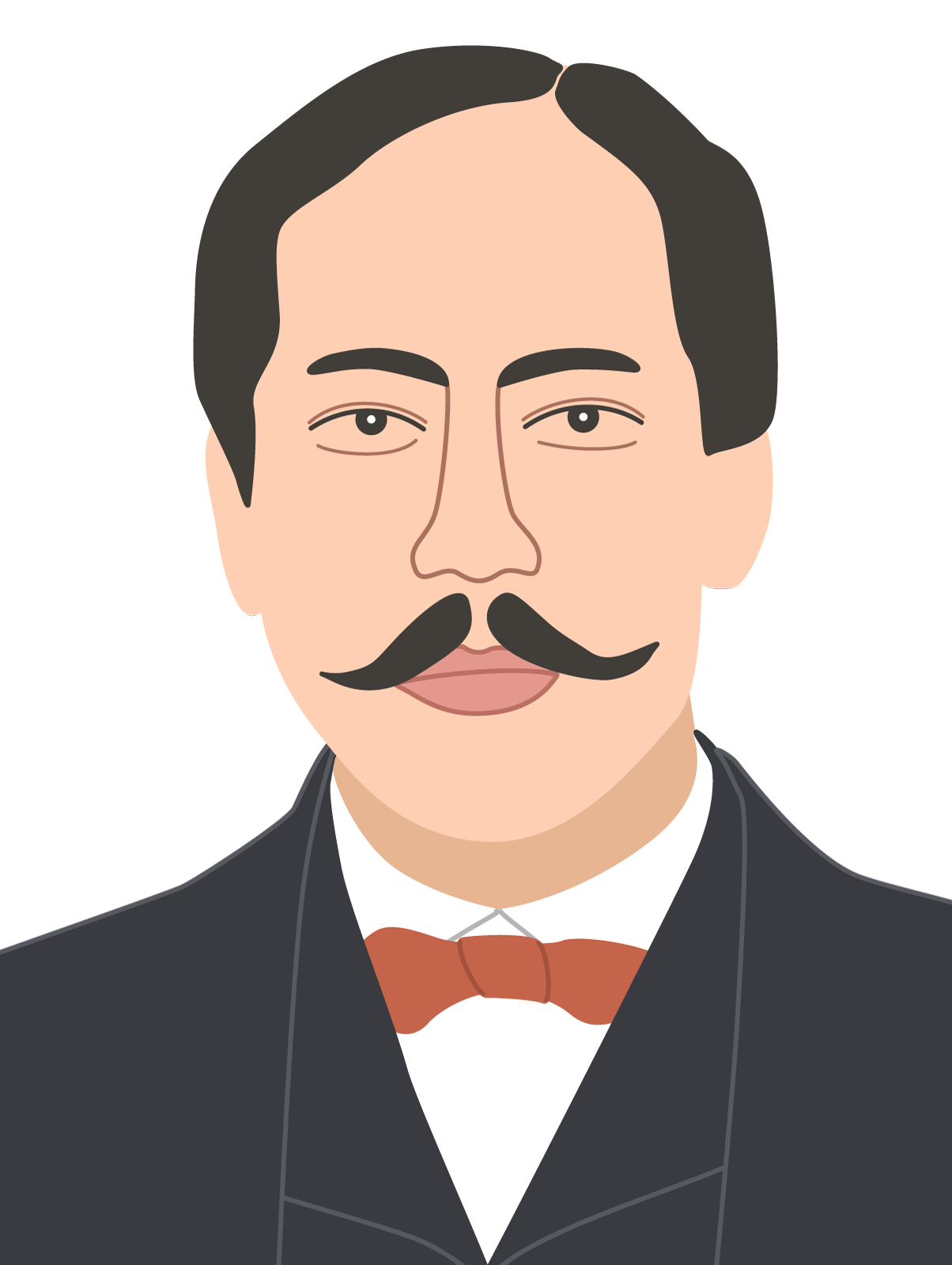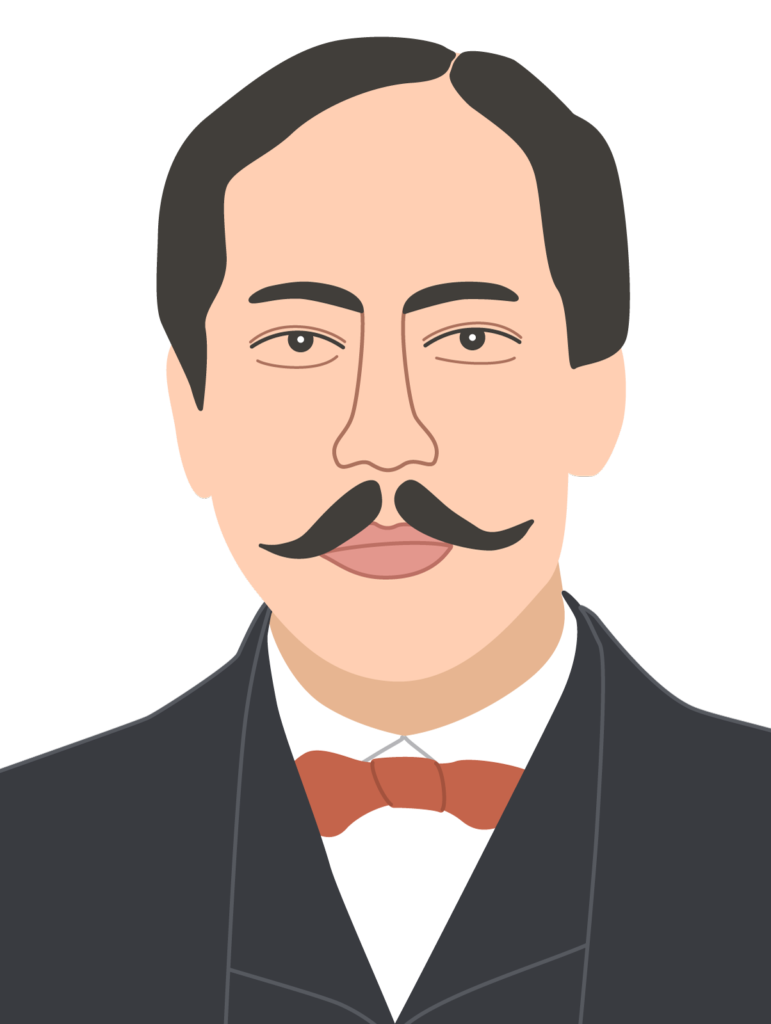
榎本武揚。
海を愛し、世界を見た男。
剣ではなく、知で闘った幕臣。
幕府が滅びようとも、彼は信念を手放さなかった。
そして敗れても、明治の世に新たな役割を見つけていく。
時代をまたぐ、不屈の外交官の物語が始まる。
蘭学と航海術を学んだ少年時代
1836年、江戸の下級武士の家に生まれる。
幼いころから聡明で、学問好きな少年だった。
幕府の海軍養成所「長崎海軍伝習所」で航海術を学び、
さらに幕命でオランダに留学。
当時としては最先端の教育を受け、世界を知ることになる。
その視野の広さが、のちの彼の運命を大きく左右していく。
幕府海軍の中核として
帰国後は幕府海軍の中枢で活躍。
語学、科学、軍事に通じた異色の幕臣として重用された。
黒船来航から十数年、幕府は海軍力の整備に本腰を入れていた。
榎本は、その先頭に立つ若きエリートだった。
その名は、幕府内外に響いていく。
戊辰戦争と「蝦夷共和国」
1868年、戊辰戦争が勃発。
新政府軍が勢いを増す中、徳川慶喜は恭順。
だが、榎本は引き下がらなかった。
最新鋭の軍艦「開陽丸」を含む艦隊を率い、
幕臣らとともに北へ――蝦夷地(北海道)へと向かう。
そこで彼が築いたのが「蝦夷共和国」。
日本で初の選挙による政体であり、榎本はその総裁となる。
函館戦争――五稜郭の最期
だが、新政府軍もまた北海道に上陸。
1869年、函館戦争が始まる。
榎本らは西洋式の戦術で応戦するも、物量と兵力の差は歴然。
最後の拠点、五稜郭に立てこもる。
そして敗北。捕えられ、死刑も覚悟した。
しかし、彼は生き延びる。
明治政府へ――異例の抜擢
明治新政府は、榎本の才能を見抜いていた。
敵であったにも関わらず、彼に役職を与える。
以後、彼は外交官として、日本の近代化に尽力。
ロシアとの国境交渉や条約締結、教育行政にも関与する。
「敗者が新時代をつくる」という前例を、彼は体現していた。
晩年まで国を支えた男
政治家としても活躍し、文部大臣や逓信大臣も歴任。
死の直前まで、国の発展のために働いた。
海軍時代の誇りと、函館での敗北を忘れることはなかった。
だが、それを引きずることもなかった。
彼は常に前を見ていた。
まとめ
榎本武揚は、知識と行動で道を切り開いた。
時代の変わり目に、何を選ぶか。
彼の選択は、幕府への忠義と、国家への奉仕だった。
剣を振るわず、知を武器に。
負けても、なお立ち上がる。
それが、榎本武揚という男だった。