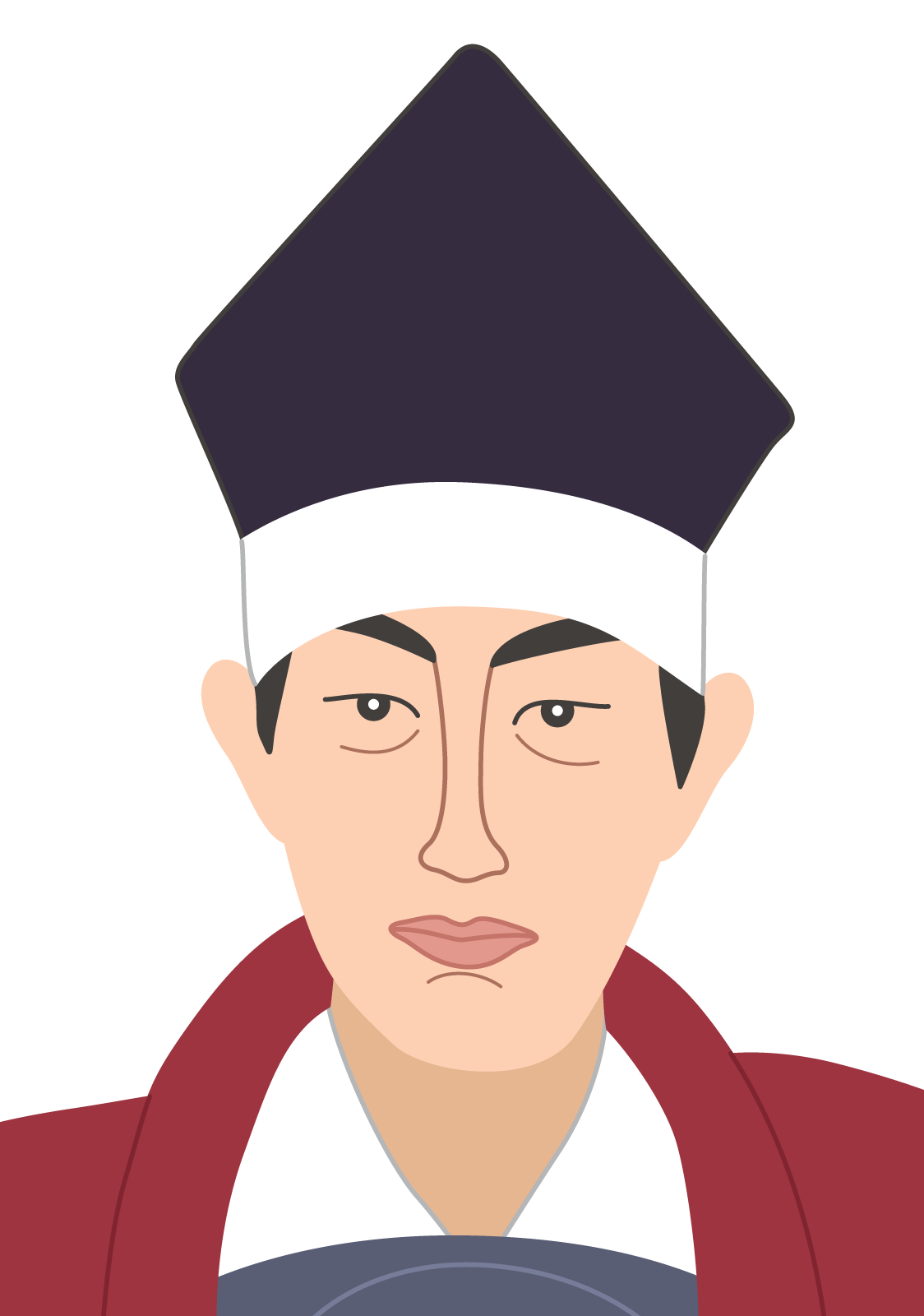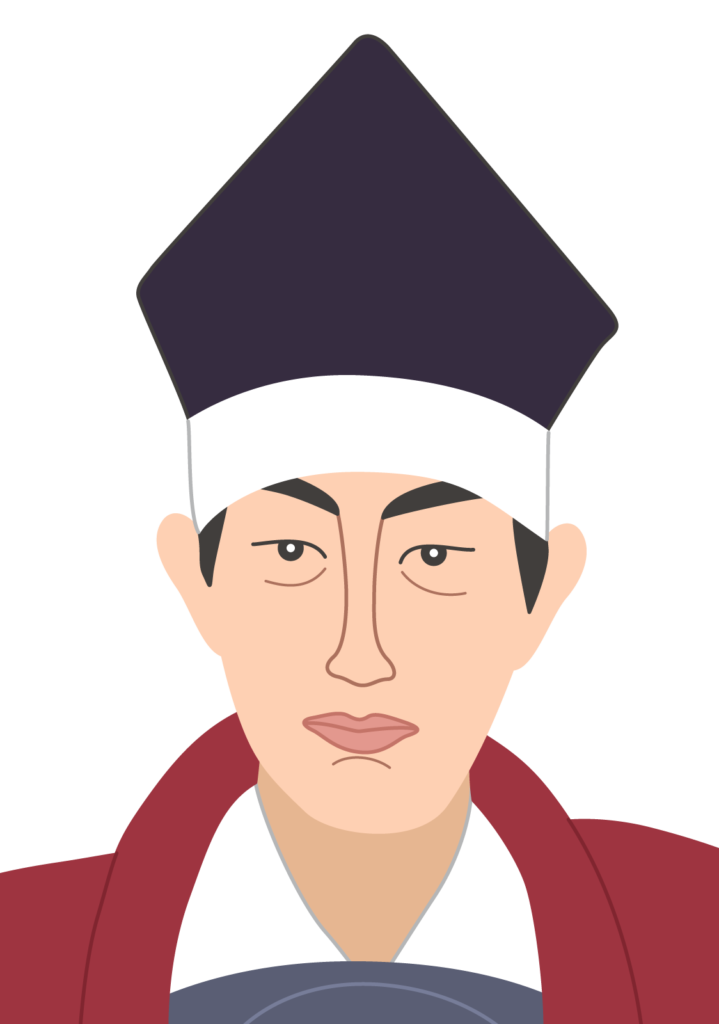
松平容保。
若くして会津藩の藩主となり、時代の激流に身を投じた男。
幕末の動乱の中で、彼は一つのことを守り続けた。
それは「義(ぎ)」。
己の損得ではなく、正しいと信じた道を貫き通した。
その覚悟が、会津を戦火に巻き込み、やがて悲劇へと向かわせていく。
幼くして徳川の家に迎えられる
1836年、京都で生まれる。
父は越前藩主・松平春嶽の異母弟。
やがて一橋家、そして将軍家にもつながる、名門の血筋だった。
幼いころから礼儀正しく、文武に優れた少年だった。
その評判は江戸まで届き、容保は徳川家の家門として取り立てられていく。
会津藩主に就任――若き殿の決意
1862年、26歳の若さで会津藩主となる。
武士道を重んじる会津藩は、質実剛健、藩士たちも厳格だった。
その中にあって容保は、誰よりも真面目に「主君」としての役割を果たそうとした。
彼の信念は、幕府に忠義を尽くすこと。
つまり、徳川のために生きることだった。
京都守護職――火中の任を引き受ける
時はまさに幕末。
尊王攘夷の志士たちが、京都で暴れ回っていた。
朝廷のある京都の治安は乱れ、幕府は手を焼いていた。
そこで白羽の矢が立ったのが、松平容保。
「京都守護職」という新設の役職に、会津藩ごと任命される。
困難で、誰もやりたがらない任務。
それでも容保は受けた。
「徳川のためになるならば」
新選組を支え、京の治安を守る
京都守護職としての容保は、会津藩兵だけでなく、
近藤勇らが率いる新選組を取り立て、壬生浪士たちに権限を与える。
新選組は尊攘派の取り締まりを行い、「池田屋事件」などで活躍。
だが、同時に恨みも買っていく。
容保の名は、「攘夷派の敵」として刻まれていくのだった。
忠義と現実のはざまで
やがて時代の流れは倒幕へと向かっていく。
徳川慶喜が将軍職を辞し、大政奉還がなされた。
容保はその動きに従うも、朝敵の汚名を着せられてしまう。
「徳川に忠義を尽くしただけなのに」
そう叫びたくなるような展開が、彼を待っていた。
戊辰戦争、会津戦争へ――悲劇の開幕
1868年、鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍が敗れ、
明治新政府軍の攻勢が始まる。
東北諸藩は連携し、「奥羽越列藩同盟」を結成。
その中核にあったのが、会津藩だった。
会津戦争が始まる。
容保は籠城を決意し、若松城で最後まで戦う。
民衆も子どもも含め、会津は一丸となって抵抗した。
白虎隊――悲しみの象徴
戦いの中で生まれた、悲劇の象徴が「白虎隊」。
若干16〜17歳の少年たちが、自刃する姿が世に知られた。
彼らの忠義と無念が、会津の名とともに後世に伝わっていく。
容保もまた、全てを背負って敗戦を迎えることになる。
敗戦、謹慎、そして晩年
戦後、容保は謹慎処分を受け、謀反人の汚名を着せられた。
命こそ助けられたが、会津藩は大幅に減封され、名家は没落した。
しかし容保は一切の恨み言を語らず、静かに晩年を送った。
会津の復興に尽力し、やがてその誠実さが再評価されていく。
まとめ
松平容保は、不器用なほど真っ直ぐだった。
幕府に仕え、会津を守り、義を貫いた。
その結果、多くを失った。
けれどその生き様は、後世の人々の心に強く残った。
幕末という時代において、「義」という言葉の重さを教えてくれた男。
それが、松平容保だった。