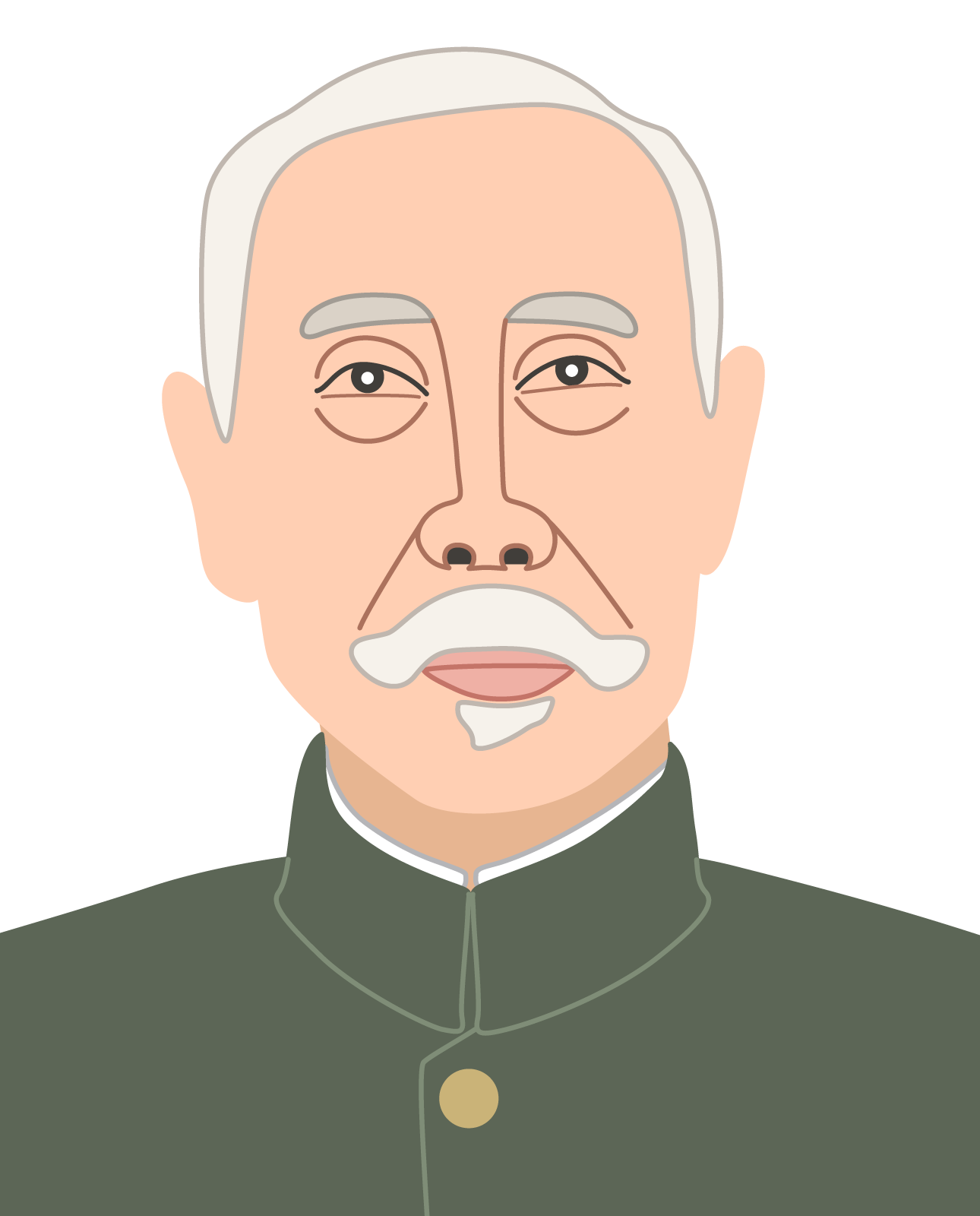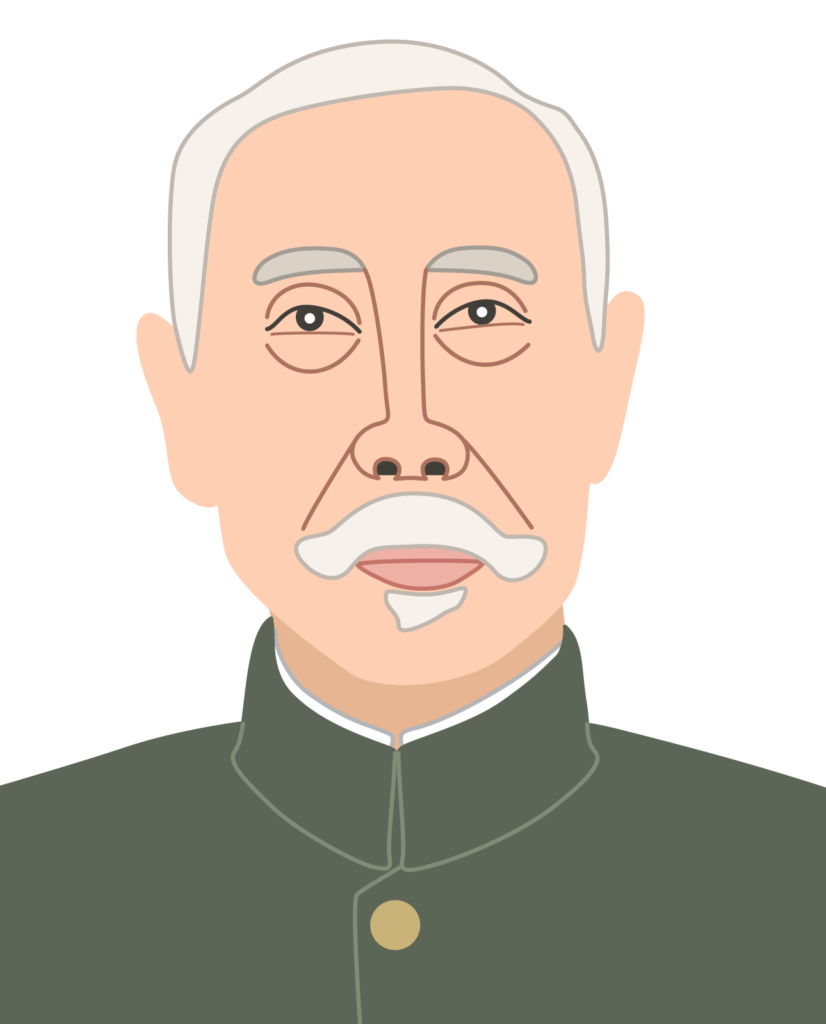
山県有朋。
侍から軍人へ、軍人から政治家へ。
時代の裏も表も知り尽くし、明治という巨大な変革の波を泳ぎ切った。
「表に出る将ではない」――そう言われながらも、
その手は、国家の骨格をつくり続けていた。
冷徹な合理主義者。
だが、その奥には、国を思う激しい炎があった。
長州藩・無名の下級藩士から
1838年、長州・萩に生まれる。
藩士とはいえ、身分は下級。
幼いころから学問と武術に励み、のちに吉田松陰の松下村塾に入る。
松陰の思想と熱に触れたことで、山県の中に何かが点火した。
「日本を変える」――その思いが静かに芽生えていく。
志士として、兵士として
幕末、尊王攘夷の気運が高まる。
山県は奇兵隊に参加。
その戦いぶりで頭角を現す。
剣ではなく、組織と戦略で勝つ――それが山県の信条だった。
禁門の変、長州征伐、戊辰戦争。
戦火の中で、生き残るだけでなく、軍を動かす才覚を磨いていった。
明治の軍を創った男
明治政府樹立後、山県が担ったのは「軍」の創設だった。
彼はドイツ式の軍制を学び、帰国後に近代的な徴兵制度を導入する。
「藩ではなく、国家の軍隊を」
これが山県の目指す姿だった。
敵を作る制度でもあったが、彼は迷わなかった。
国を守るには、武士ではなく国民全体が戦うべきだと信じていたから。
政治の世界へ、影の実力者として
やがて山県は政治の世界にも足を踏み入れる。
内務大臣、首相、枢密院議長。
名だたる役職を歴任し、そのたびに実務をこなした。
派手な理想は語らない。
だが、予算、法制度、人事――あらゆる国家の裏側で、山県が動いていた。
政党政治を嫌い、官僚による統治を重視。
この姿勢が、後の「山県閥」を生むことになる。
民意との軋轢
山県は、民衆による政治には懐疑的だった。
「衆愚政治になる」
それが彼の持論だった。
その結果、自由民権運動や政党からは強く批判される。
「山県は古い」
「民の声を聞かぬ独裁者だ」
それでも、山県はぶれなかった。
国が安定し、守られるには、理想だけでは足りないと信じていた。
晩年と、山県の残したもの
晩年、山県は政治の表舞台から離れる。
だが、政府の中には依然として彼の影があった。
後継者を育て、人脈を広げ、
「国家」という仕組みが崩れないように目を配っていた。
1922年、病に倒れ、その生涯を終える。
享年84。
激動の時代を、無骨に、冷静に、生き抜いた男だった。
まとめ
山県有朋は、カリスマでもなければ、革命家でもない。
だが、彼がいなければ、日本の軍も、行政も、存在しなかったかもしれない。
派手な言葉ではなく、静かな実行力。
誰よりも現実を見据え、誰よりも責任を背負った。
侍の誇りを胸にしまい、近代国家をつくった男。
それが山県有朋という存在だった。