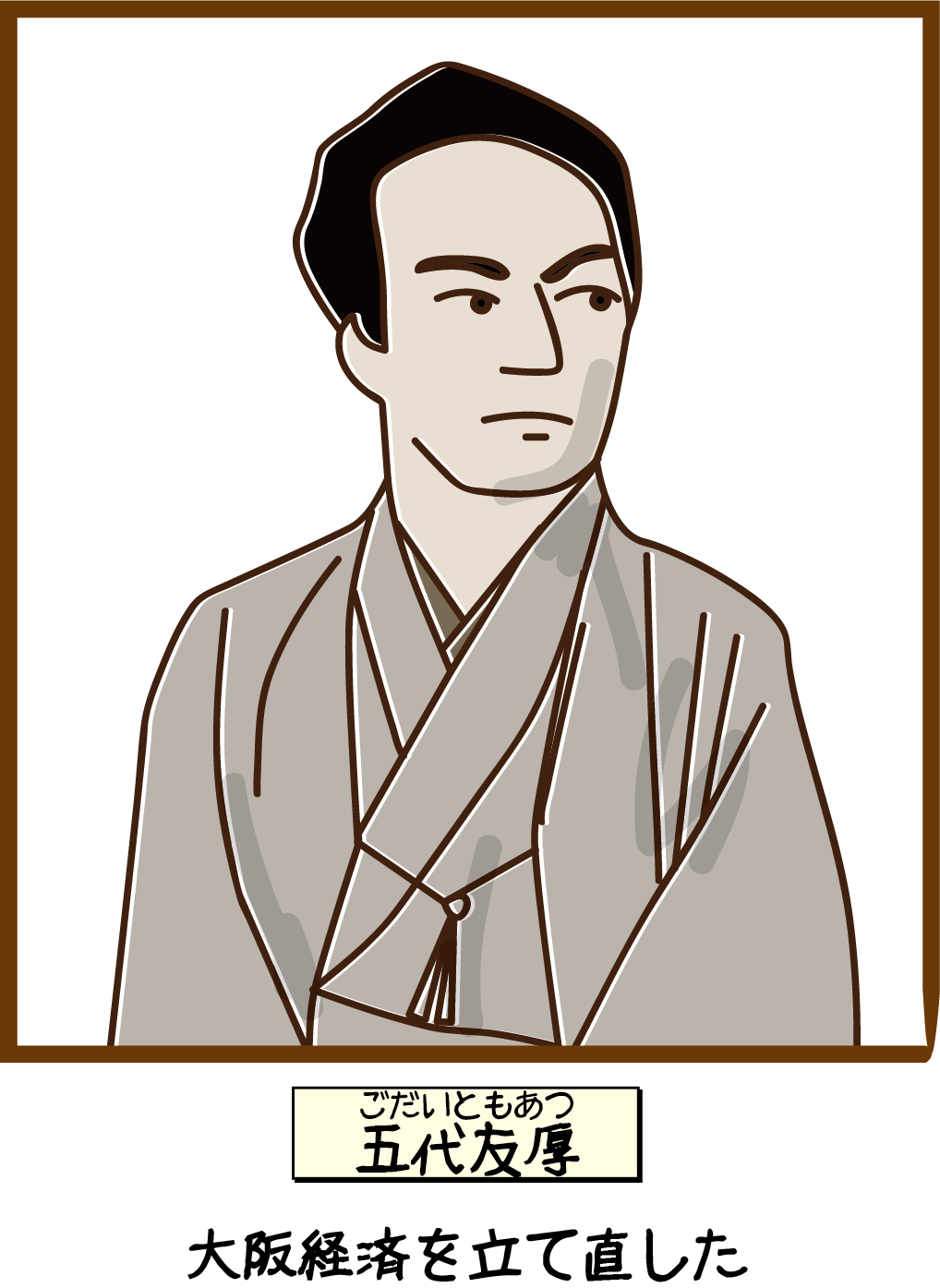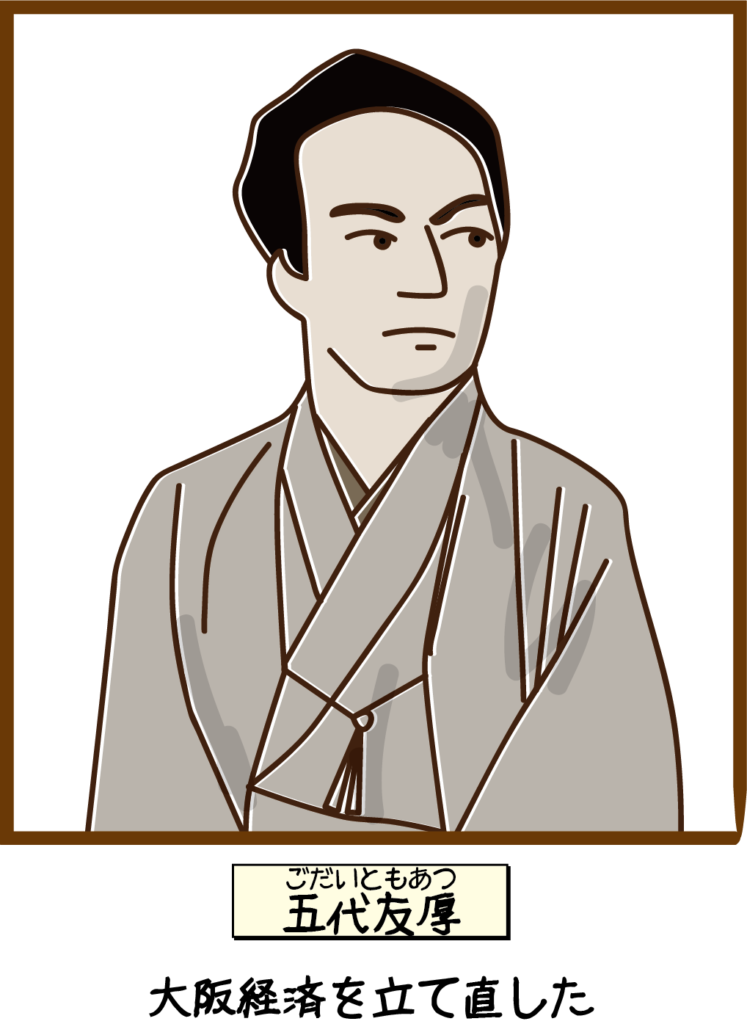
五代友厚。
薩摩藩出身の志士であり、維新後の日本経済の礎を築いた男。
政治家ではない。軍人でもない。
けれど彼なくして、日本の近代は語れない。
混乱の幕末を駆け抜け、明治の世に「商業国家・日本」の未来を見ていた。
西郷でも、大久保でもなく。
この男が、大阪の未来を背負った。
若き日の薩摩藩士
1836年、薩摩藩に生まれた五代友厚(幼名・徳夫)。
学問に秀で、早くから異国の文化にも関心を持っていた。
幕府が鎖国をゆるめるなか、彼はイギリス行きを志す。
そして藩命を受け、長崎でオランダ語を学び、上海・ヨーロッパを歴訪する。
時代の最前線で世界と出会った青年は、帰国後、「この国には経済の力が要る」と痛感する。
倒幕の裏で動いた頭脳
討幕戦争が激化する中、五代は表立って剣を振るうことはなかった。
だが、諸外国との交渉や、情報収集、資金調達――そのすべてに関わっていた。
イギリス商人グラバーとの関係も深く、薩長同盟の影の立役者ともいわれる。
五代は常に「戦の後」を見ていた。
国を動かすためには、経済の仕組みが必要なのだと。
大阪経済の父になる
明治維新後、五代は大阪に移り住む。
衰退していた商都・大阪を「再び日本一の経済都市に」と立ち上がる。
大阪株式取引所の創設、商法講習所(後の一橋大学)の設立、鉄道事業や銀行設立など、
彼が関わった近代化の基盤は、数えきれない。
実業家として、教育者として、そして街づくりの先導者として。
五代は、大阪の人々に「商いの誇り」を取り戻させた。
静かに、しかし確かに去る
華やかな役職に就くことなく、五代は志を貫いた。
政争には加わらず、常に市井に生き、街を見つめていた。
1885年、49歳で急逝。
その死は静かだったが、彼が遺したものは今も大阪に息づいている。
まとめ:維新の影にいた未来人
五代友厚は、剣でも政でもなく、「経済」で国を支えた。
明治の混乱のなか、唯一「未来」を見ていた人物かもしれない。
「商いが、この国を豊かにする」
そう信じ、静かに行動した五代。
今、大阪証券取引所の前には彼の銅像が立っている。
その姿は、今も未来を見据えているかのように――。