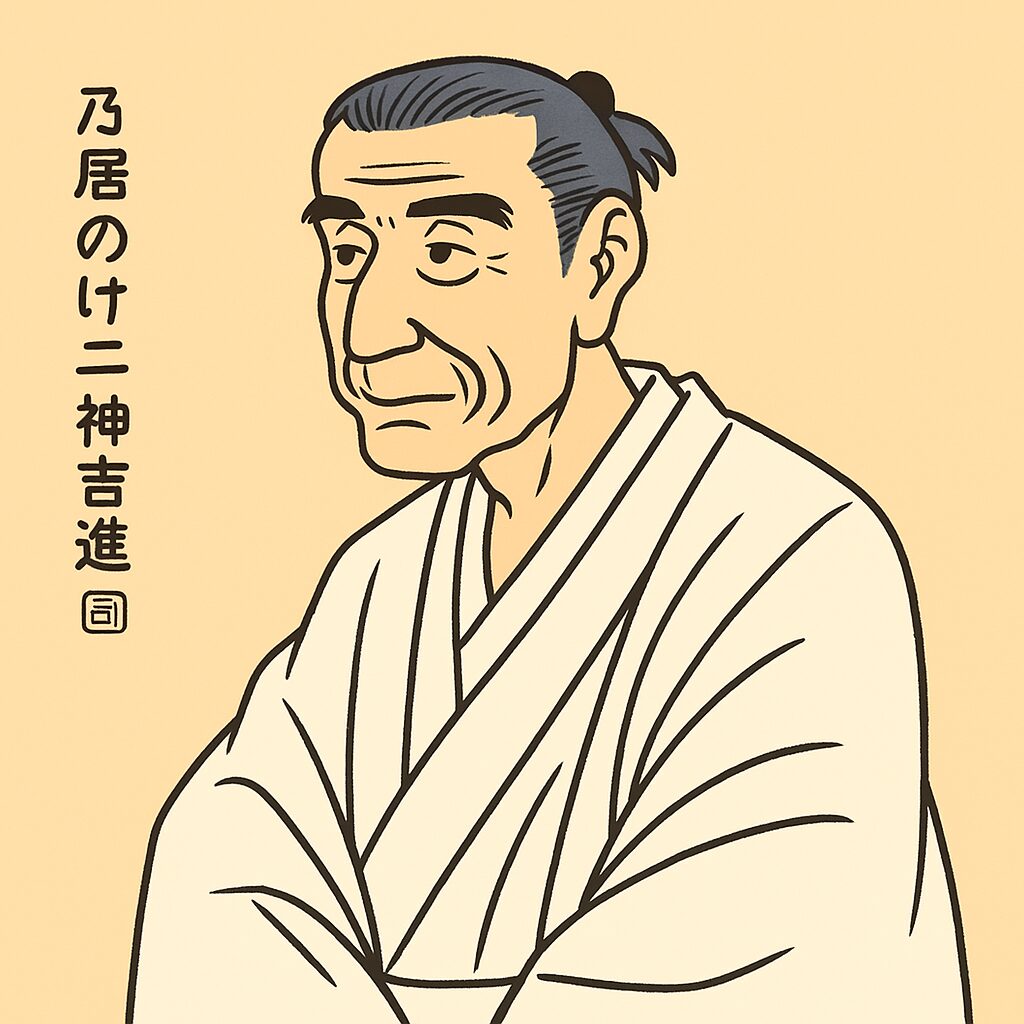
橘曙覧。
福井藩の下級武士でありながら、幕末の京にその名を知られた歌人。
彼の人生は、決して華やかではなかった。
だが、一首一首に込めた言葉は、時代を超えて響く。
「たのしみは〜」から始まるその短歌は、天皇の心をも打った。
慎ましく、まっすぐに、彼は詠んだ。
人の世の幸せとは何かを。
学問と詩の道
橘曙覧は、文化8年(1811年)、越前国福井に生まれた。
若くして学問に目覚め、国学や和歌、漢詩に親しんだ。
だが、その道は険しかった。
家は裕福ではなく、職も定まらず、失意のうちに隠棲。
それでも彼は筆を止めなかった。
日々の暮らしの中に、歌を見出していった。
たのしみは、の歌人
「たのしみは〜」で始まる一連の歌。
それは曙覧の暮らしの中での、小さな喜びの記録だった。
「たのしみは 朝起きいでて昨日まで 無かりし花の咲ける見るとき」
「たのしみは 妻子むつまじくうちつどひ 頭ならべて物をくふ時」
そこには虚飾もない、強がりもない、ただ素直な“よろこび”がある。
幕末という不安定な時代において、その穏やかさは人々の心を癒した。
後年、この歌を明治天皇が愛読し、曙覧の名は不朽のものとなる。
福井の庵から、世界へ
曙覧は生涯、福井の草庵で暮らした。
「独楽吟」と名付けた自作の歌集に、自らの生き方を投影した。
それは派手な維新の活躍とは対極にあった。
けれど、そこにこそ“人としての誇り”があった。
やがて時代が明治へ移ると、彼の歌は“日本人の心”として見直されていく。
まとめ:小さな幸せを、堂々と
橘曙覧は、歴史の表舞台には立たなかった。
だがその詠んだ言葉は、どんな英雄の言葉よりも、まっすぐだった。
「たのしみは」――それは彼自身の生き方そのもの。
日々を愛し、人を愛し、自分を誇る。
彼は、誰もが持つ“静かな幸せ”に気づかせてくれる。
橘曙覧の歌は、今もなお、多くの人の胸にしみ渡っている。