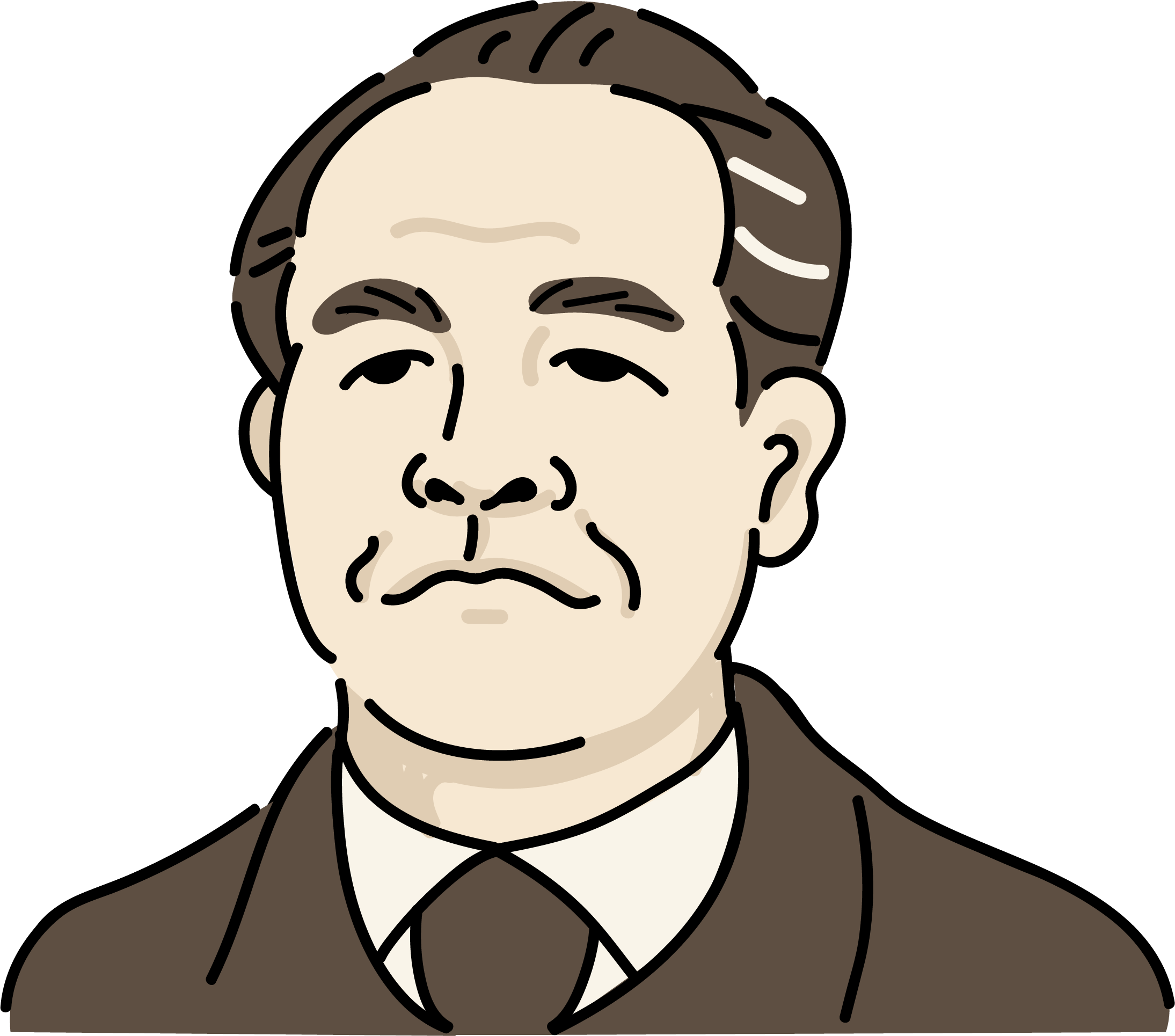渋沢栄一。
日本で初めて「銀行」をつくった男。
約500の企業、600を超える社会事業に関わった“近代日本経済の父”と呼ばれる人物だ。
だがその出発点は、武士でも政治家でもない。
藍をつくる農家の長男だった。
貧しさと向き合い、志士として倒幕を目指し、やがて経済で国を変えようと決意する。
彼の人生は、静かに、そして力強く、日本のかたちを変えていった。
農家に生まれた学問好きの少年
1840年。
現在の埼玉県深谷市にある血洗島村で、渋沢栄一は生まれた。
家は農家だが、藍玉の製造と販売である程度の富を持っていた。
幼いころから読書が好きで、「論語」など儒学の書を好んで読んだ。
特に「義」を重んじ、「私利私欲を抑える」という教えに強く心を惹かれた。
このとき学んだ哲学が、後の人生に深く根を下ろすことになる。
志士として倒幕を目指す
青年期に入ると、栄一は尊王攘夷の思想に染まっていく。
幕府の腐敗と、不平等な条約に憤り、「この国を変えなければ」と強く思うようになった。
同郷の仲間とともに、高崎城を襲撃するという計画も立てた。
だが、直前になって計画は中止。
このままでは追われる身になると悟った栄一は、江戸に逃れ、縁を頼って一橋家に仕官することとなる。
パリで見た世界の広さ
1867年。
一橋慶喜の弟・昭武に随行し、パリ万博を見学するためフランスへ渡る。
この海外経験が、彼の価値観を根底から覆す。
パリの街並み、整った法律、整備された金融制度、産業の発展――
日本とのあまりの違いに、彼は驚き、そして学び取った。
「武力ではなく、経済と制度で国は変わる」
帰国した彼は、倒幕という考えを捨て、文明開化に身を投じていく。
経済で国を変える決意
明治政府に仕官し、大蔵省で制度作りに携わる。
だが官の世界に違和感を覚え、すぐに辞職。
明治6年には第一国立銀行(現・みずほ銀行)を設立し、日本に銀行制度を根づかせる。
以後、製紙・鉄道・保険・証券・商社など、近代産業の数々に関わり、民間の立場から日本経済を支えていく。
その数、およそ500社。
栄一は経済人として、日本の未来を信じて歩み続けた。
利益よりも、正しい道を
渋沢栄一が一貫して大事にしたのは「論語」の教えだった。
利益は大切。
しかし、それ以上に「人として正しいか」を常に自分に問いかけていた。
だからこそ、教育・福祉・医療・女子支援といった社会事業にも力を注ぐ。
600以上の公益活動に関わり、多くの学校や病院、孤児院の設立を支援した。
利益と道徳を両立させる――それが、彼の信念だった。
最後まで現役を貫いた人生
91歳で亡くなるまで、栄一は第一線に立ち続けた。
朝早くから新聞を読み、日課のように各所へ顔を出し、相談に乗り、講演を行った。
死の前日まで、講演の予定が入っていた。
「生涯現役」という言葉を、彼はまさに体現していた。
まとめ
渋沢栄一は、刀で戦うことを選ばなかった。
武士としての誇りより、民間人としての使命を取った。
数字や利益を追うだけでなく、その先にいる“人”を見つめていた。
「経済は人を幸せにするもの」
その考え方は、今なお色あせることがない。
――“お金”に向き合う姿勢を変えた男。
それが、渋沢栄一という人物なのだ。