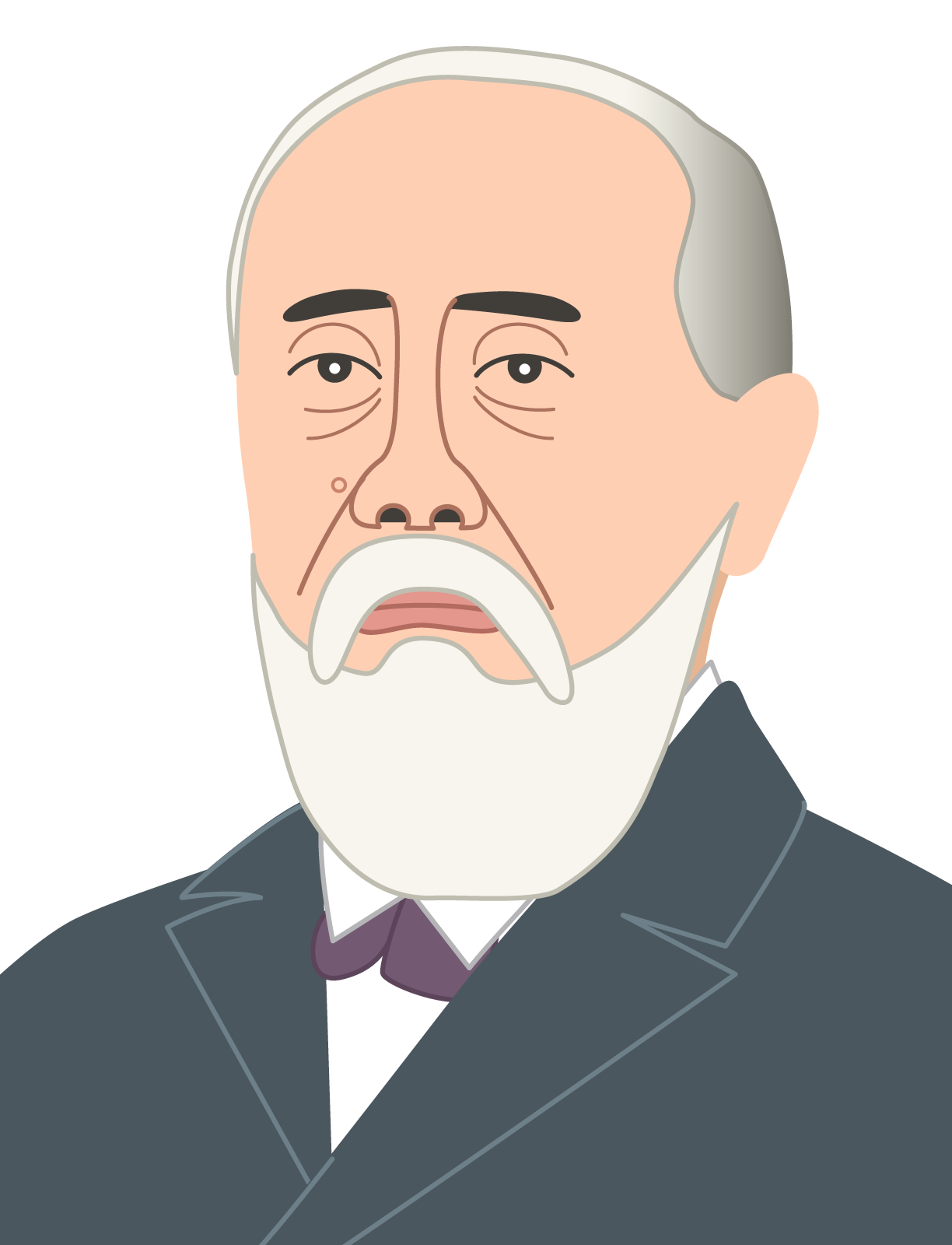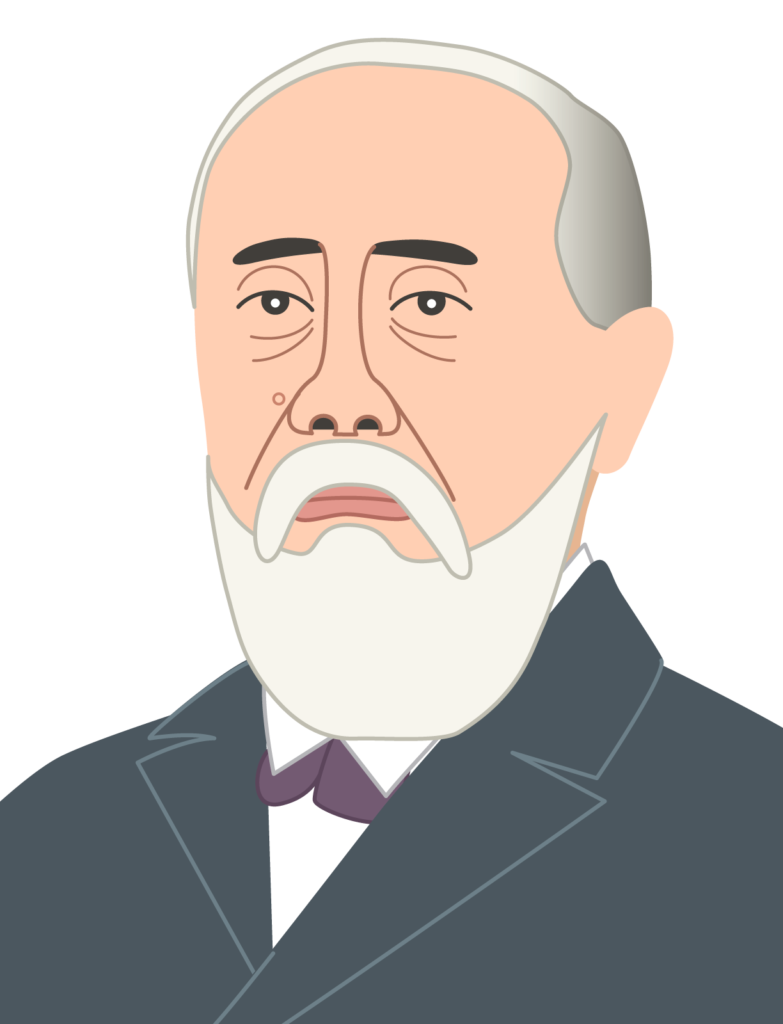
「日本の総理大臣、最初は誰か知ってる?」
そう聞かれて、「伊藤博文」と答えられる人は多いでしょう。
でも――
その名前の裏に、どんな物語があるかを知っている人は、きっと少ない。
貧しい農家に生まれた少年が、なぜ国家のトップにまで上り詰めたのか。
なぜ、明治という激動の時代を駆け抜け、日本のかたちをつくったのか。
今回は、伊藤博文という男の「人間らしい一面」とともに、その波乱万丈な生涯を、柔らかく、わかりやすくご紹介します。
武士になりたかった百姓の子
伊藤博文は1841年、現在の山口県・長州藩にあたる地域で、農民の家に生まれました。
幼名は「利助」。
家は貧しく、決して恵まれた環境とは言えません。
しかし、彼には子どもの頃から「武士になりたい」という強い願いがありました。
勉強が好きで、頭の回転も速く、やがて長州藩士・吉田松陰の松下村塾に入門。
ここで高杉晋作、久坂玄瑞、桂小五郎(後の木戸孝允)と出会い、若き志士たちと交流する中で、彼の中に「自分はこの国を変える」という強い志が芽生えていきます。
イギリス留学と、西洋文明との出会い
幕末の動乱期、博文は藩命を受けてイギリスへ密航留学します。
船に揺られ、見知らぬ異国の地で目にしたもの――それは、科学、技術、法、経済……すべてにおいて先を行く西洋文明でした。
驚きと同時に、危機感が彼を突き動かします。
「このままじゃ、日本は列強に飲み込まれてしまう」
帰国後、彼は尊王攘夷から「開国と近代化」へと思想を転換。
倒幕後の新政府に参加し、若くしてその中心人物になっていきます。
憲法をつくった男
明治時代、伊藤博文の名を一気に知らしめたのが「大日本帝国憲法」の制定です。
憲法とは、国家のルールの“設計図”。
当時、日本にそんな概念はなく、彼は再びヨーロッパへ渡り、憲法のあり方を一から学びました。
「日本に合う、日本のための憲法をつくるんだ」
何年もかけて練り上げたその成果が、1889年の憲法発布につながり、日本は“近代国家”への一歩を踏み出します。
同時に、彼は「内閣制度」を導入し、なんと日本で初めての内閣総理大臣に就任。
ここに、“宰相・伊藤博文”が誕生しました。
権力者として、策士として
伊藤博文は、一見すると“まじめな官僚タイプ”に思われがちですが――
実は、とっても人間味あふれる人物でもありました。
愛嬌があり、酒好き、女好きで、冗談もよく飛ばす。
ときには、周囲を煙に巻くような策略家の顔を見せながら、その裏では「日本の独立を守る」ために必死で外交にあたっていたのです。
明治の元勲として、4度の総理大臣を務め、韓国併合問題にも関わる中、彼は常に「国家」と「民」の未来を見据え続けました。
志半ばの凶弾
1909年、韓国・ハルビン駅にて、伊藤博文は朝鮮独立運動家・安重根の凶弾に倒れます。
享年68。
「私は日本を、アジアを、守るつもりだった」
その思いが伝わらないままの死――
けれど、彼の残した制度、思想、憲法の土台は、今の日本にも脈々と受け継がれています。
まとめ
伊藤博文は、政治家であり、革命家であり、外交官であり、策士であり、そして何より“情熱家”でした。
偉人と聞くと、どこか遠い存在に思えてしまうけれど、彼の人生には「人間くささ」と「泥くささ」があふれています。
百姓の子が、学び、悩み、笑い、怒り、時に遊び、時に泣きながら、この国のかたちを必死につくっていった――
そんな伊藤博文の姿は、今を生きる私たちに問いかけてくれるようです。
「君は、自分の手で未来を変える気があるかい?」