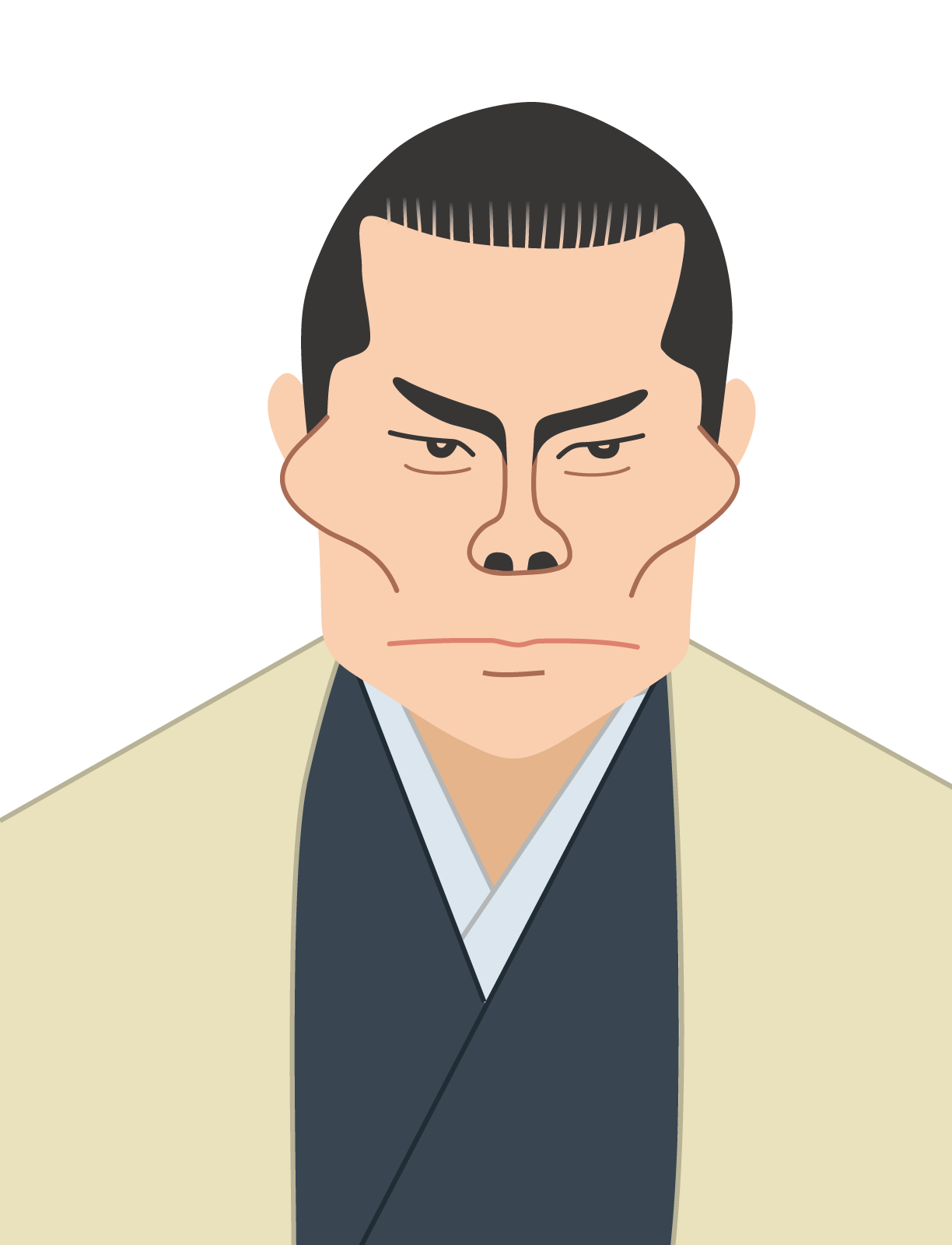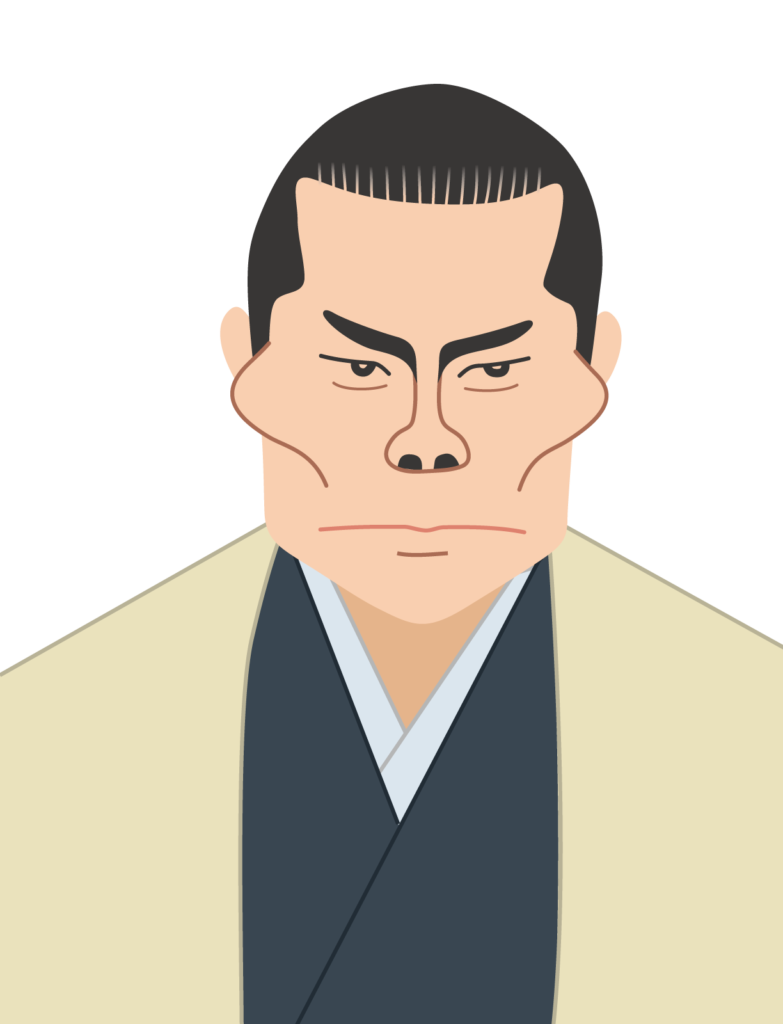
幕末。
世は刀と銃が入り乱れる混沌の時代。
その渦中で、「武士ではなかった男」が、命を賭して“武士道”を生き抜いた――それが、近藤勇でした。
華やかな英雄ではないかもしれない。
けれど、信念を持ち、仲間を守り、最後までその道を貫いた近藤の姿は、今なお多くの人の胸を打ちます。
今回は、そんな彼の生き様を、柔らかく、わかりやすく紐解いていきましょう。
武士に憧れた“百姓の子”
近藤勇は1834年、武蔵国多摩郡(現在の東京都調布市付近)に生まれました。
実は彼、生まれは百姓。つまり、武士ではありません。
けれど幼い頃から「剣の道」に憧れ、天然理心流という剣術道場に通い詰め、ついにはその道場の養子となり、免許皆伝を得ます。
この頃から、彼の中には明確な目標がありました。
「ただ剣が強いだけでは意味がない。俺は、武士になりたいんだ」
貧しい農家に生まれながらも、“志”ひとつで武士を目指した近藤。
その目は、いつもまっすぐ前を向いていました。
新選組という戦場
1863年、幕府の命で上洛した浪士隊の一員として、近藤は京都へ向かいます。
ここで、土方歳三、沖田総司、山南敬助らと共に、後の「新選組」を結成。
新選組は、京都の治安維持を担う武士集団――けれど、ただの“警察”ではありません。
彼らは、倒幕派や過激な攘夷志士と命がけでぶつかる、まさに“命のやりとり”の日々。
中でも近藤は、常に最前線に立ち、自ら剣を振るいました。
「武士たるもの、命を惜しむな。誠を貫け」
新選組の旗に刻まれた「誠」の文字――それは、近藤の生き様そのものだったのです。
名を上げた池田屋事件
1864年、京都で起きた「池田屋事件」。
尊王攘夷派の志士たちが集まり、京都で大規模な放火を計画していたこの事件。
それを未然に防ぎ、一網打尽にしたのが新選組でした。
近藤はこの作戦の中心となり、自ら数名の手勢を率いて斬り込みます。
彼の果敢な戦いぶりにより、京都の町は守られ、一躍「新選組」の名は広まりました。
けれど――これが彼らにとっての“頂点”であり、同時に“終わりの始まり”でもあったのです。
時代の波に抗って
時が経ち、倒幕の流れはますます加速。
新政府軍が勢いを増す中、近藤たちは旧幕府側として闘い続けました。
慶応4年(1868年)、鳥羽・伏見の戦いで敗れた新選組は江戸に退き、さらに北へと落ち延びていきます。
それでも近藤は諦めませんでした。
「武士の誠とは、主君に最後まで忠義を尽くすことだ」と。
しかし、その逃避行の中、彼は新政府軍に捕らえられてしまいます。
最期の言葉
1868年5月17日――
近藤勇、斬首。享年34歳。
そのとき、彼の口から洩れたのは、こんな言葉だったと伝わります。
「武士として死ねることを、誇りに思う」
百姓の子として生まれ、剣を磨き、仲間を守り、命を懸けて生き抜いた。
その生涯に一片の悔いなし――そう言わんばかりの、堂々たる最期でした。
まとめ:真っ直ぐな“誠”を生きた男
時代は変わり、幕府は消え、新政府が誕生しました。
けれど、近藤勇が貫いた“武士道”は、今も色褪せていません。
どんな立場に生まれても、信じる道を貫く。
それがどれほど困難で、報われなくても――
「俺は、武士になりたかった」
その願いを、最後の最後まで貫き通した男、近藤勇。
彼の“誠”は、現代に生きる私たちにも、静かに語りかけているようです。――「お前の信じる道を、ちゃんと歩いてるか?」と。