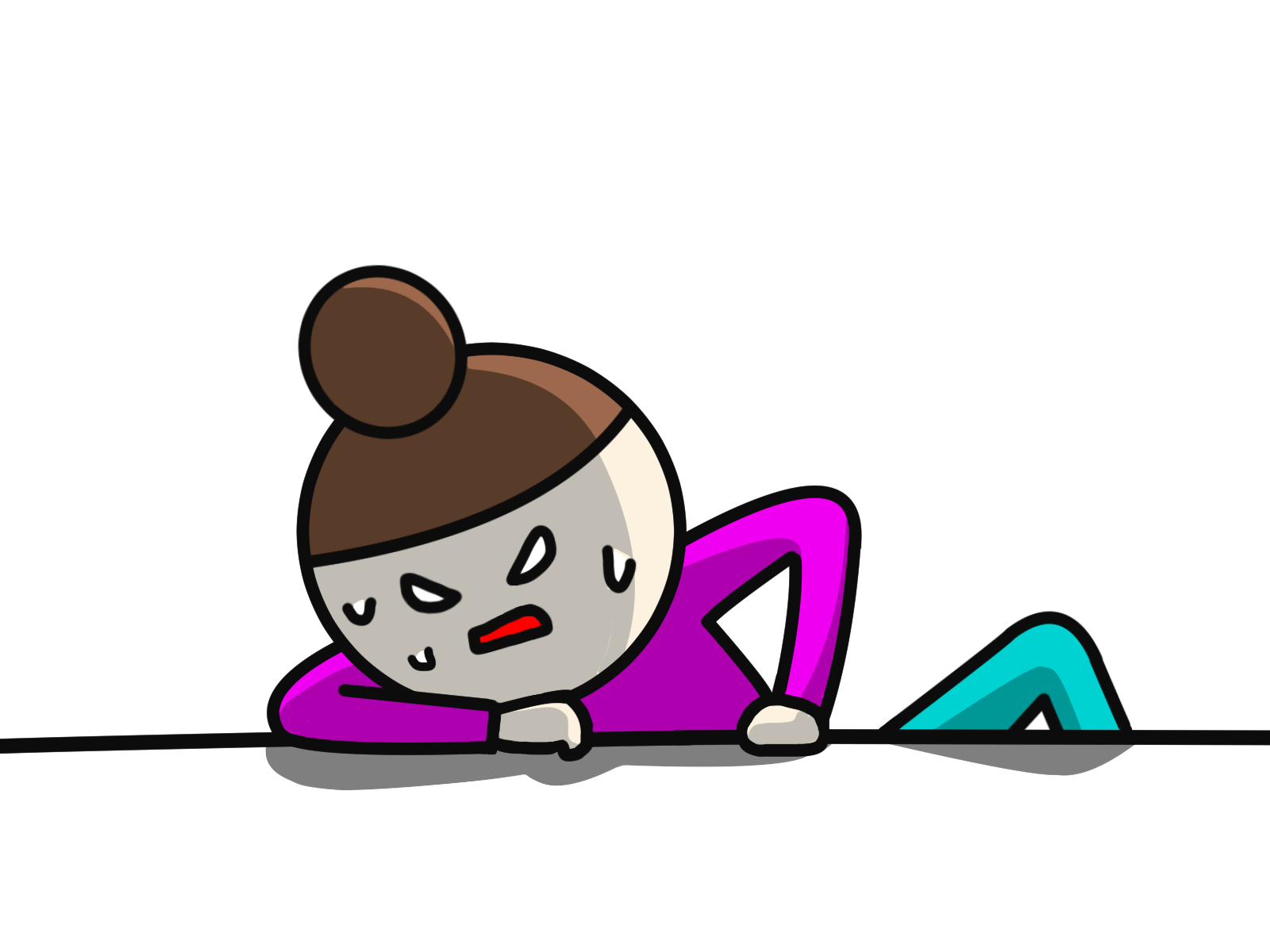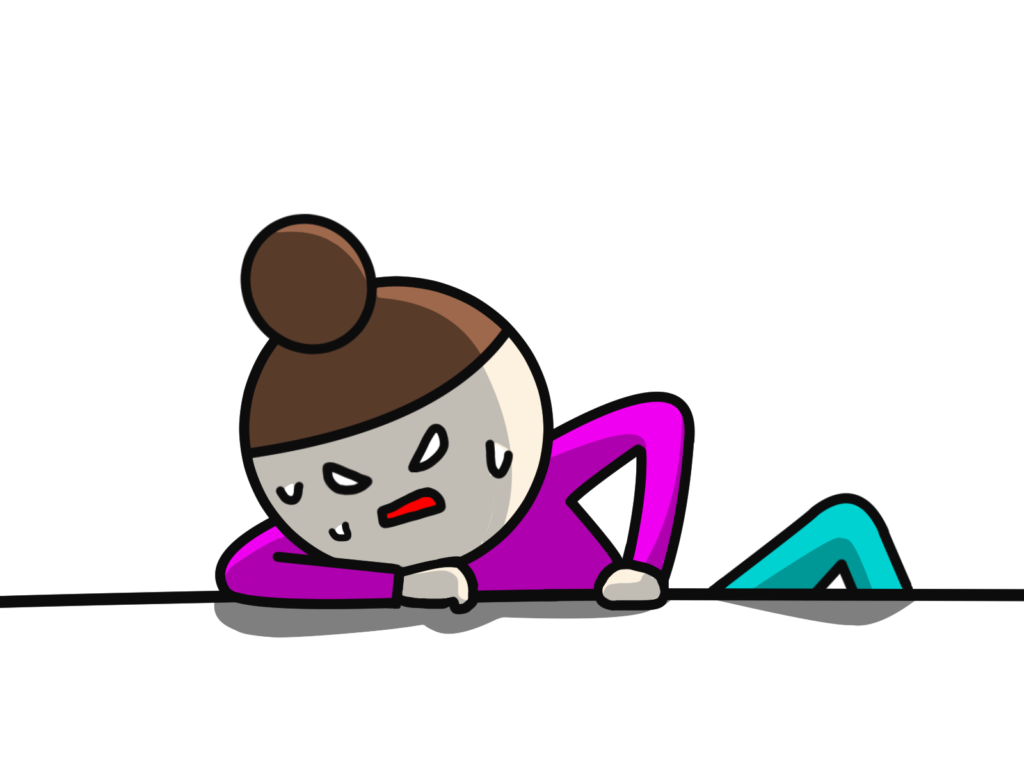
こんにちは!
今日ご紹介する四字熟語は、心がくじけそうなときに、静かに背中を押してくれるような力強い言葉――
それが 「堅忍不抜」 です。
地味だけど、心にグッとくるこの言葉。
今回はたとえ話を交えながら、しっかりご紹介していきます。
「堅忍不抜」とは?
「堅忍不抜」 とは、強い意志を持って、どんな困難にも耐え抜き、決して心を動かさないこと。
- 「堅忍」=かたく我慢すること(辛抱強く耐える)
- 「不抜」=気持ちが揺らがない、くじけない
つまり、「自分が信じた道を、何があっても動じずに貫く姿勢」を表す四字熟語です。
たとえばこんな話
ある地方の木工職人、ユウジさん。
30年近く、ほとんど機械を使わず手作業で家具を作り続けてきました。
時代は流れ、安価な海外製品が大量に出回り、ユウジさんの仕事は減る一方。
「もう時代遅れじゃないの?」
「そんな手間かけて、意味あるの?」
という声も。
それでもユウジさんは、
「手で作ることにしか出せない“温もり”がある」
と言って、黙々と木と向き合い続けました。
5年、10年と経つうちに、ユウジさんの家具は“本物”を求める人の間で評価され、今では予約数年待ちの人気職人に。
この話、まさに 「堅忍不抜」 の精神そのものです。
流されない。諦めない。貫き通す。 その強さが、人生を変えるんですね。
「我慢するだけ」じゃない
「堅忍不抜」は、ただじっと耐えるだけの言葉ではありません。
本当の意味は、“信念をもって動じないこと”。
苦しくても逃げない。
不安でもやめない。
「これが自分の信じた道だから」と、内に強さを秘めて立つ人の姿を表します。
起源と歴史
「堅忍不抜」は、もともと中国の古典にそのルーツがあります。
特に、儒教や兵法書などの中で、「堅忍」は君子の徳(理想的な人物像)として語られてきました。
日本では、江戸時代の武士道や教育の中で重視され、「信念を持って耐えることこそ、強さの証」として広く知られるようになります。
明治以降は、政治家や経営者の言葉としても多く使われ、たとえば明治の元勲・木戸孝允が座右の銘にしたとも言われています。
■ まとめ
「頑張っても報われない」
「努力が無駄に思える」
そんなときこそ、思い出したいのが「堅忍不抜」という言葉です。
表には出さなくても、心の中でしっかりと立ち続ける。
それだけで、もう十分すごいことなんです。
今日も、静かに戦っているあなたへ。
「堅忍不抜」で、一歩ずつ前へ。
次回の四字熟語も、どうぞお楽しみに!