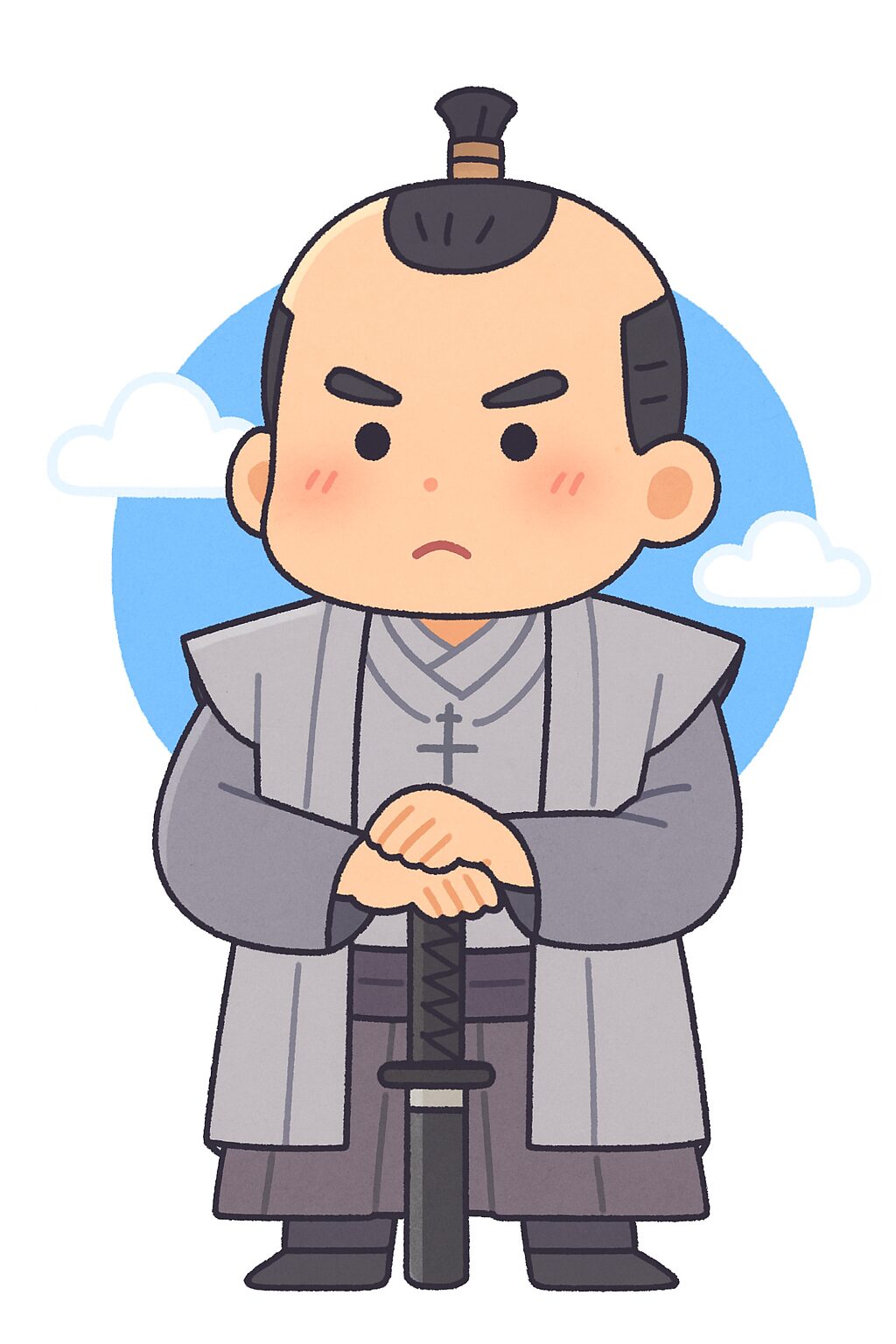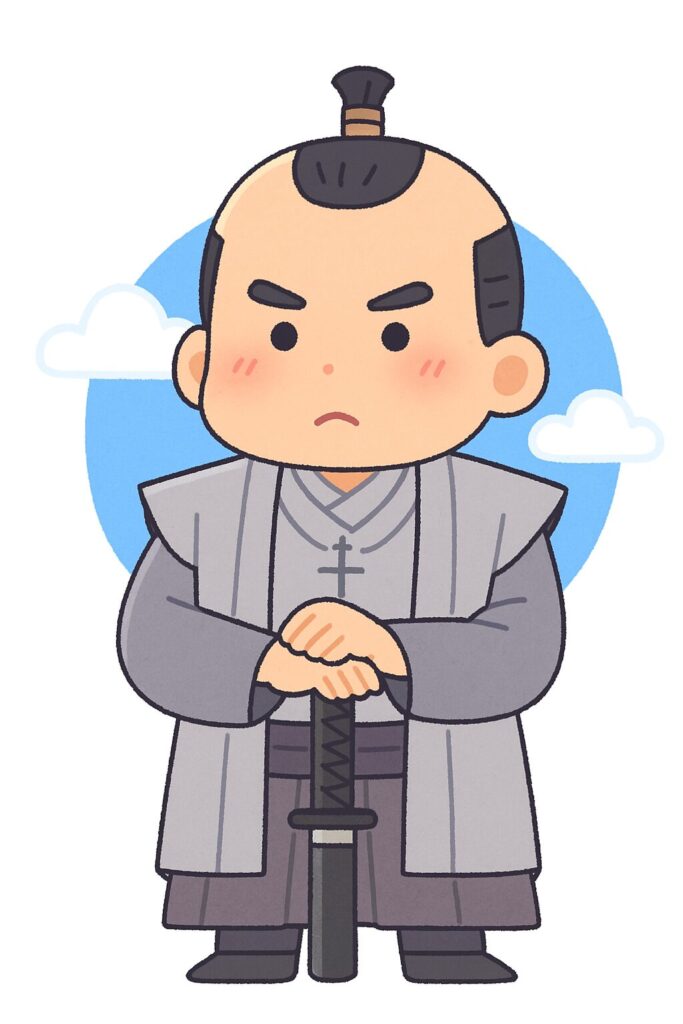
戦国時代の武将といえば、甲冑をまとって戦場を駆ける“ザ・侍”のイメージが強いですよね。
でもその中には、異文化に興味を持ち、海を越えて活躍したグローバル系武将もいたんです!
その代表格が――小西行長。
キリシタン(キリスト教徒)としても知られる彼は、信仰とビジネス、戦と外交を自在に行き来したユニークな武将。
今回はそんな行長のドラマチックな人生を、ポップにやわらかくご紹介します♪
海商の家に生まれ、商才でのし上がる!
行長は1555年頃、摂津国(現在の大阪府)で薬種商の家に生まれたとされています。
父親は貿易で財を成した海商で、幼いころから海外の文化や商売のセンスに触れて育ちました。
その後、肥後(熊本)の有力者である小西隆佐の養子となり、武士としての道を歩み始めます。
そして、商才を活かしながら豊臣秀吉の九州征伐や朝鮮出兵に従軍し、ぐんぐん出世!
やがて肥後の半国、14万石を領する大名にまでなったのです。
キリスト教に心酔、信仰と共に生きた武将
小西行長の特筆すべきポイントのひとつは、熱心なキリシタン(キリスト教徒)だったこと。
洗礼名は「アウグスチヌス」。
当時の日本ではまだ珍しかったキリスト教を受け入れ、家臣たちにも布教を広めていきました。
戦だけでなく、文化や信仰を重んじたスタイルが彼の個性を際立たせています。
また、南蛮(ヨーロッパ)との交易ルートを活かし、外交や貿易のセンスでも秀吉に信頼されていたのです。
朝鮮出兵で見せた軍才と悲劇
1592年、秀吉の命により始まった朝鮮出兵(文禄の役)。
小西行長は、加藤清正と並ぶ先陣として朝鮮に渡ります。
初期の快進撃は目覚ましく、一時は首都・漢城(現在のソウル)を占領!
外交や交渉にも長けていた行長は、朝鮮側との講和工作にも関わりました。
しかし戦況は次第に悪化し、やがて帰国。
そして秀吉の死後、天下分け目の関ヶ原が迫ります――。
関ヶ原で西軍の先鋒となるも…
1600年、徳川家康と石田三成が対立し、関ヶ原の戦いが勃発。
行長は三成と親しく、西軍の一員として参戦します。
彼は先鋒として奮戦しますが、味方の裏切りなどもあり、西軍は敗北。
捕らえられた行長は、戦後処理で斬首されるという悲劇的な最期を迎えました。
その死に際もまた、信仰深い彼らしく――
「キリスト教徒として、信念を曲げなかった」と語り継がれています。
おわりに
小西行長は、戦国武将の中でも異彩を放つ存在。
戦場だけでなく、貿易や外交、そして信仰の世界でも活躍した多才な武将でした。
ときに大胆で、ときに誠実。
時代の荒波のなかで“信じるもの”を持ち続けた彼の生き方は、現代の私たちにもどこか響くものがあります。
静かに燃える情熱と、世界へ目を向ける広い視野。
そんな小西行長の物語、あなたもぜひ胸に刻んでみてくださいね。