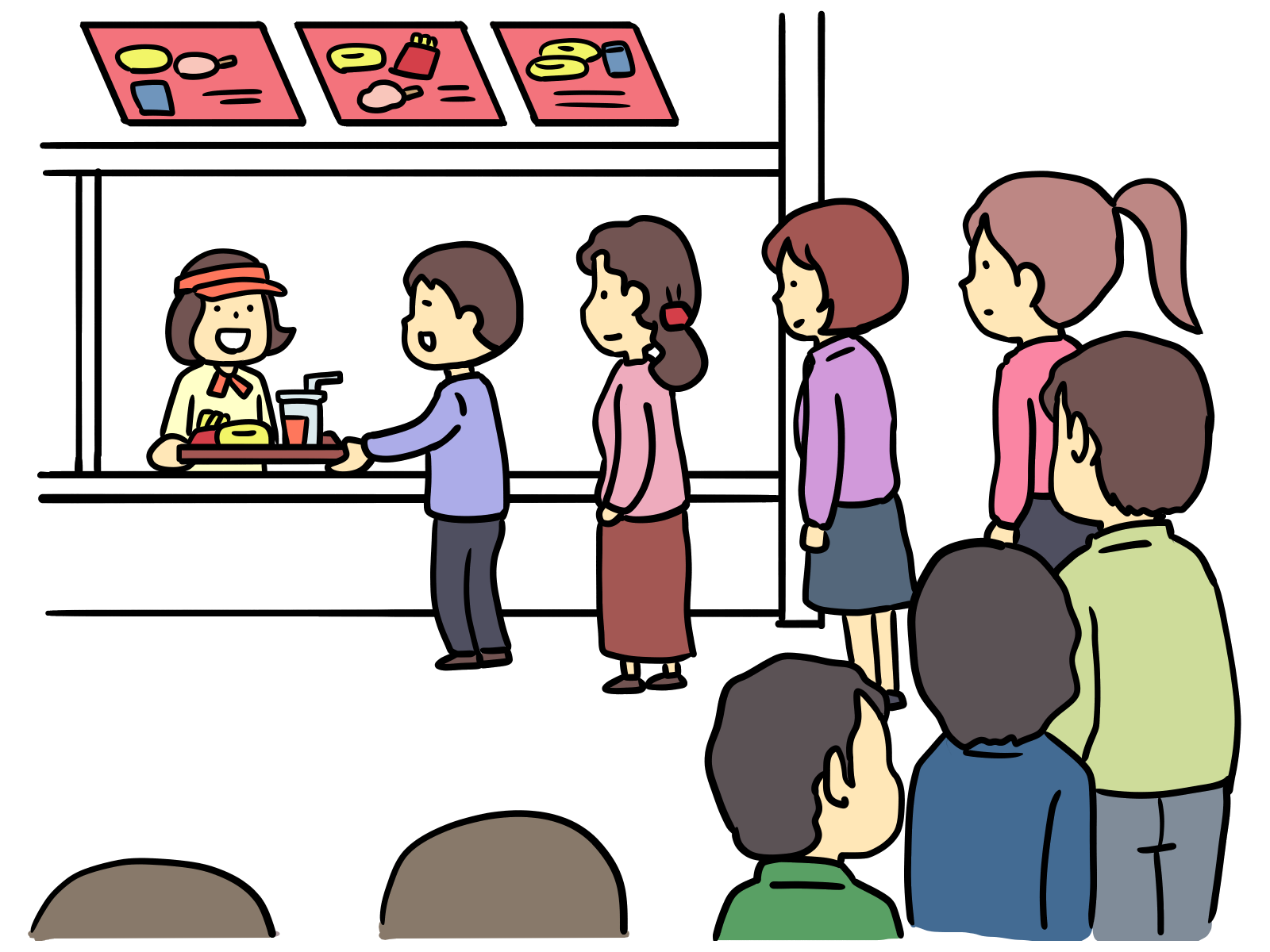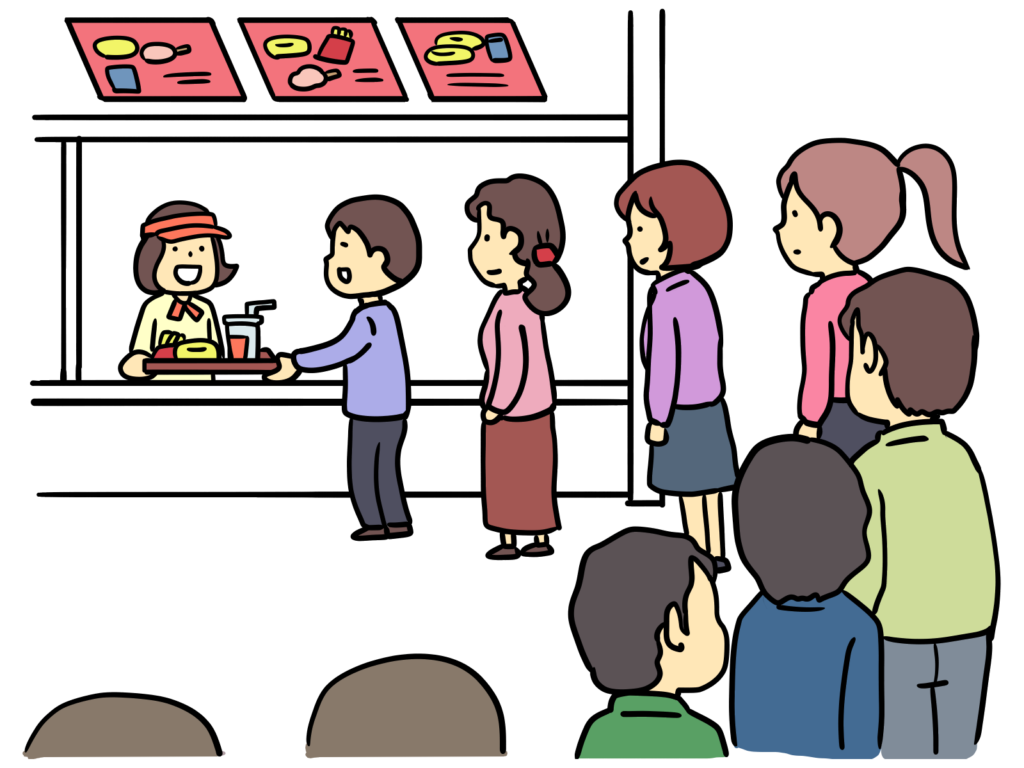
「最近、似たようなお店がどんどんできてるな…」
「新しいアイドルグループが次から次へとデビューしてる…」
そんな“次々と現れるもの”を表すときにぴったりなことわざが、これです。
「雨後の竹の子」
自然界のたとえが、現代の社会現象にまで通じる――
今回は、このことわざの意味や背景、現代での活用まで、やさしく解説していきます。
💡「雨後の竹の子」とは?
このことわざの意味は、以下の通りです。
雨が降ったあとに、竹の子が一斉に地面から生えるように、物事や人が次々と勢いよく現れること。
つまり、何かが次から次へと湧き出る様子をあらわすたとえです。
特に、流行りモノや新しいものが一気に出てくるときによく使われます。
🎋たとえ話
昔、山あいの村では、雨が降った翌日になると、
畑のあちこちから竹の子がにょきにょき顔を出すのが恒例でした。
それを見た旅人が「すごいな、いっぺんにこんなに出てくるのか!」と驚くと、
村の長老はこう言いました。
「目に見えるのは一瞬でも、土の下ではずっと育つ準備をしておった。見えるのは“今”、だけど力は“前から”育っておるのじゃ。」
この村では、その現象から何かが急に増えることを「竹の子みたいやな」と例えるようになったそうです。
🧬起源・由来
「雨後の竹の子」は、古くからの自然観察に基づいたことわざで、
中国の古典『荘子』や『詩経』にも似た表現が見られます。
日本でも、特に竹林が多い地域では、
- 雨が降った後に
- 地面から突然にょきにょきと
- しかも数十本単位で竹の子が出てくる
という現象が広く知られており、それが転じて「物事が一斉に現れる」たとえとして使われるようになりました。
📱現代での使い方
- 「雨後の竹の子のように、○○系のカフェが急増している」
- 「雨後の竹の子のように、新しいVTuberがデビューしている」
- 「SNSでの情報商材ビジネスが雨後の竹の子状態になっている」
など、“ブーム化したものの急増”や“流行りの波に乗って出てくるもの”を表すときにぴったりです。
ただし、肯定的にも否定的にも使えるため、文脈に注意して使いましょう。
🔖まとめ
- 意味:雨が降った後に竹の子がいっせいに生えるように、物事が次々と現れることのたとえ
- たとえ話:竹の子の村では、土の中で育っていた力が雨とともに一気に姿を見せた
- 由来:自然現象を観察して得られた表現。中国・日本の古典にも似た思想が
- 現代での使い方:流行りモノやビジネス、サービスの急増などに使える
新しいものが次々と現れる社会で、私たちは何を“土の中”で育てているでしょうか?
一気に花を咲かせるような日が来るために、今できることを大切にしていきたいですね。
「雨後の竹の子」――その勢いの裏には、見えない準備がある。