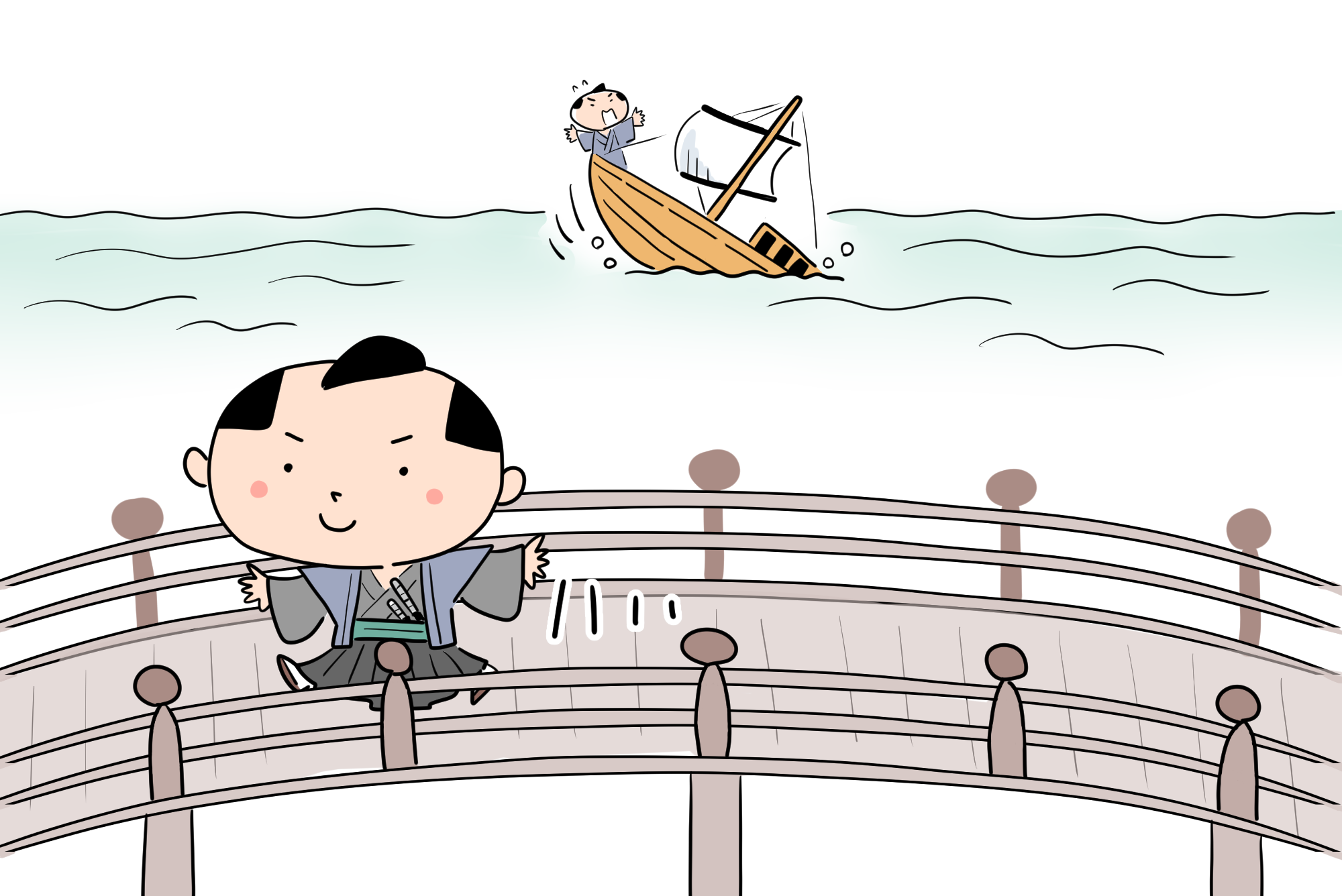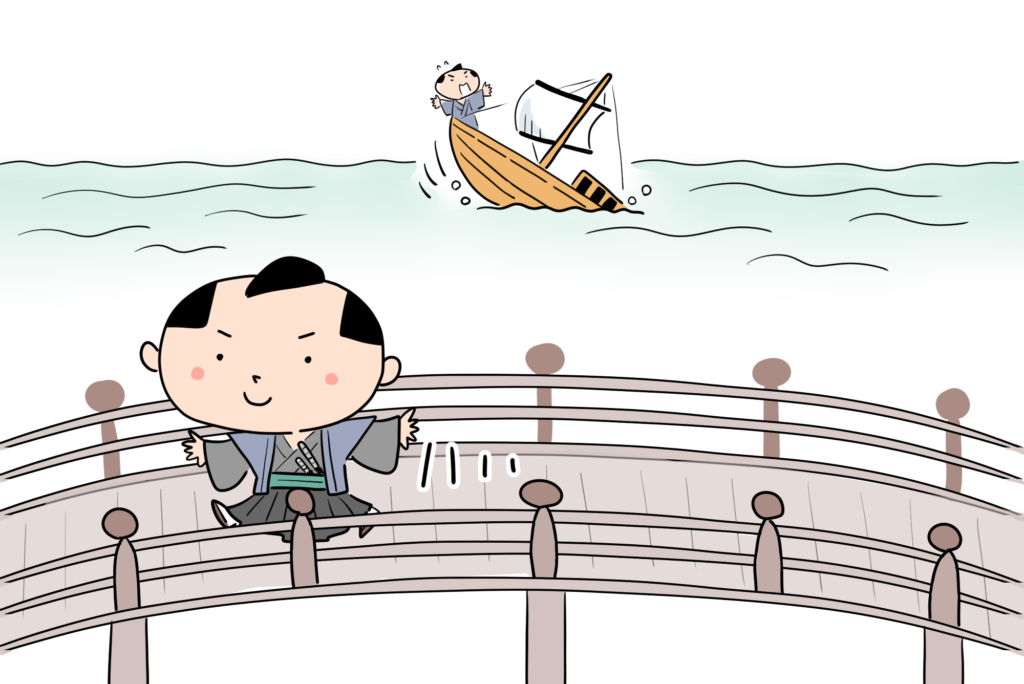
何かを急いでいるとき、最も近道に見えるルートを選びたくなりますよね。
でも、近道には落とし穴があるかもしれません。
結局、遠回りしたほうが安全で確実にゴールできることもあるのです。
そんなときに思い出したいのが「急がば回れ」ということわざ。
今回は、その意味をわかりやすいたとえ話を交えて紹介しつつ、起源についても触れていきます!
たとえ話
昔々、とある村に住む旅人の太郎は、遠く離れた町に急ぎの用事がありました。
太郎が村を出発すると、道は二つに分かれていました。
まっすぐ進めるけれど、古くて壊れかけの橋を渡る近道
少し遠回りになるが、しっかりした丈夫な橋を渡る安全な道
「時間がないし、近道の橋を渡ろう!」と太郎は思い、壊れかけの橋へ向かいました。
しかし、渡る途中で橋が崩れ、川に落ちてしまいました。
ずぶ濡れになったうえ、川を渡るのに時間がかかり、結局、予定より遅く町に到着してしまいました。
一方、もう一人の旅人の次郎は「急ぎたいけど、安全な道を行こう」と考え、遠回りの橋を渡りました。
その結果、着実に歩みを進め、太郎よりも先に町に到着できたのです。
まさに「急がば回れ」。
焦って近道を選ぶと、かえって時間がかかることもあるのです。
起源
このことわざの起源は、室町時代の連歌師・宗長が詠んだ和歌にあるとされています。
「急がば回れ、近道すれば、遠回り」
当時、京都から江戸(今の東京)へ向かうには、琵琶湖を渡るルートがありました。
しかし、琵琶湖の波は荒れやすく、無理に渡ると遭難する危険がありました。
そのため、遠回りでも陸路を行ったほうが安全で確実だったのです。
この経験から、「急いでいるときほど、安全で確実な道を選ぶべきだ」という教訓が生まれました。
まとめ
「急がば回れ」とは、焦らず安全な道を選んだほうが、結果的に早く目的を達成できるという教えです。
現代でも、たとえばプログラミングを学ぶときに「基礎を飛ばしてすぐに難しいことをやろう」とすると、途中でつまずくことがあります。
一方、基礎をしっかり学んでから進めば、結果的にスムーズに習得できるのです。
何かを急いでいるときこそ、この言葉を思い出してみてくださいね!