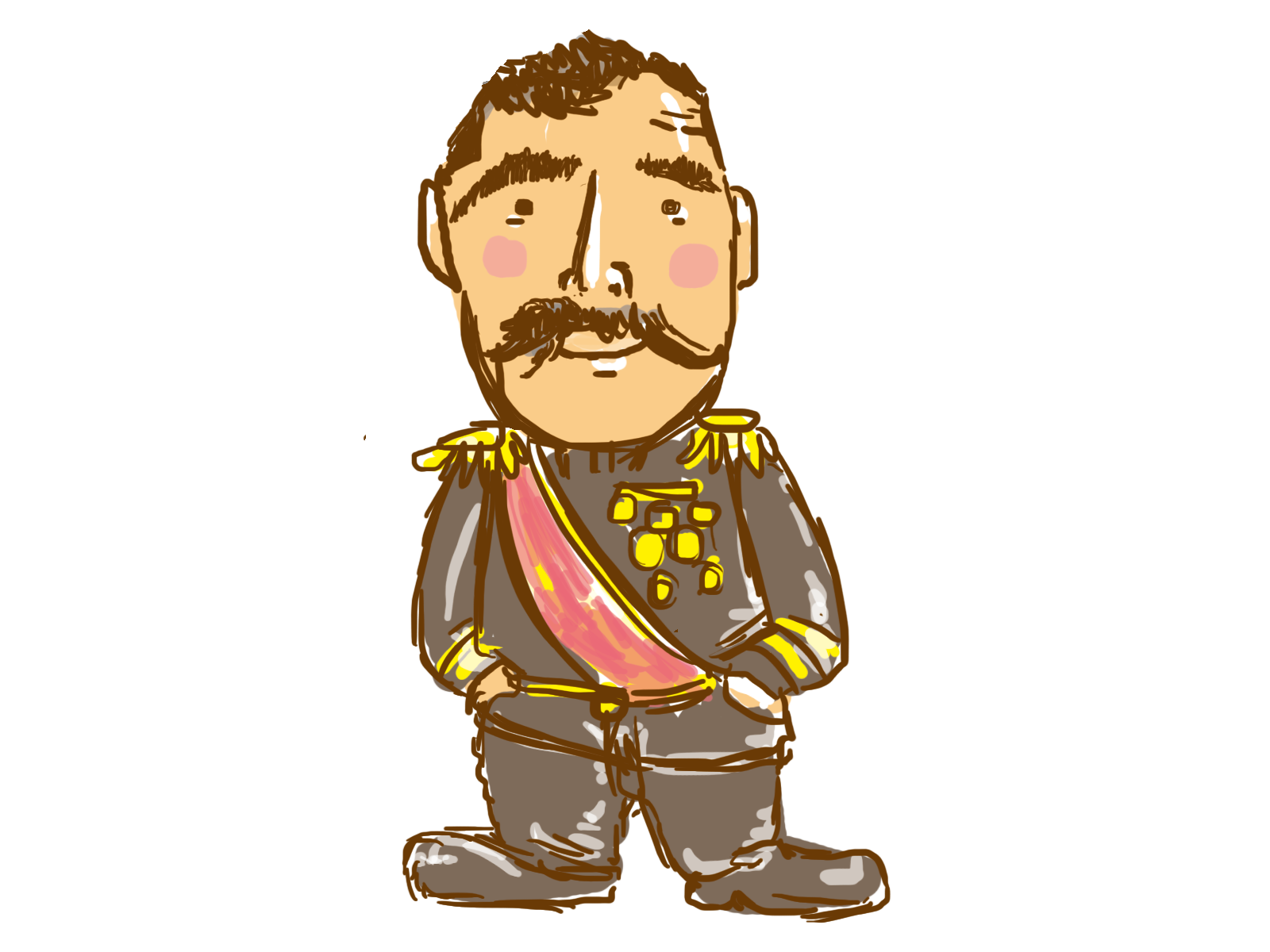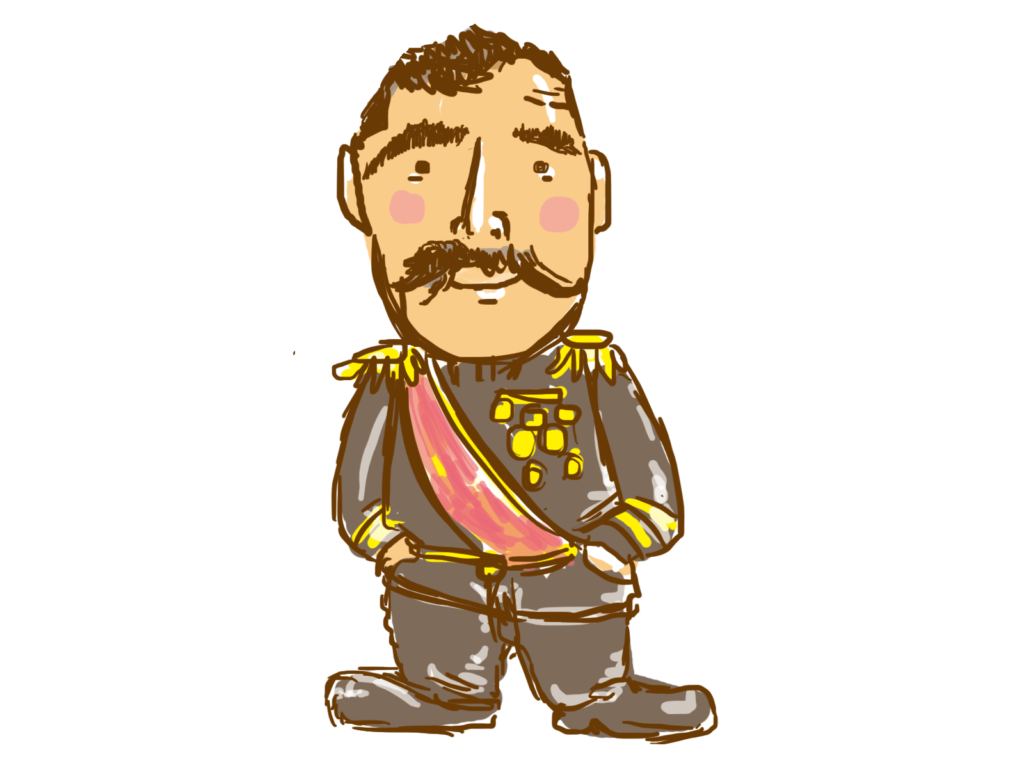
西郷従道。
あの西郷隆盛の弟である。
けれど彼の人生は、「弟」という言葉では語りきれない。
薩摩藩士として、維新の立役者として、そして明治政府の柱として。
彼は静かに、しかし確かに、日本を動かしていた。
兄とは違う形で――。
武士として生まれ、兄と共に立ち上がる
1843年、薩摩・鹿児島に生まれる。
西郷家の次男として、兄・隆盛に育てられるようにして成長。
少年時代から文武両道で、実直な性格だった。
やがて幕末、兄とともに薩摩藩の志士として活躍。
倒幕の動きが激しくなる中、従道もその渦中に身を置く。
ただし、常に兄の背中を見つめながら、自分の役目を探していた。
明治維新の立役者として、冷静な現実主義者
明治維新のあと、兄が下野する一方で、従道は政府に残る。
海軍卿、陸軍大臣、内務大臣などを歴任。
薩摩出身ながらも派閥に偏らず、政敵とも協調した。
兄・隆盛が西南戦争で命を散らす時、従道は政府側にいた。
苦しかったはずだ。だが、それでも彼は職責をまっとうした。
国家の未来を、兄とは違うやり方で支えようとしていた。
人柄は温厚、けれど妥協なき行政官
従道の性格は、豪胆だった兄とは正反対。
穏やかで柔和、それでいて筋の通らぬことには一歩も譲らない。
海軍の近代化では、イギリス式の徹底導入を進めた。
軍だけでなく、鉄道、教育、衛生など、広く国の仕組み作りに貢献。
そして何より、官僚の規律や責任を重んじた。
表には出ないが、まさに「屋台骨」としての働きだった。
最後まで兄を想い、兄を超えなかった男
従道が何よりも心に抱えていたのは、兄・隆盛の存在だった。
西南戦争のあとも、兄の名誉回復に力を尽くした。
晩年、元老として政界に影響を与えつつも、決して前面には出なかった。
その控えめな姿勢が、兄と比較されることも多かったが――
彼は、彼のやり方で、時代をつないでいた。
1902年、病に倒れ、静かにこの世を去る。
享年59。
まとめ:兄の光と共に歩んだ、もう一つの偉大
西郷従道は、兄・隆盛の影にいた。
けれど、その影はただの影ではなかった。
国を支え、制度を整え、人を守った。
乱世に剣を振るう者がいれば、治世には柱となる者が必要だった。
従道はまさに、その柱だった。
激しさではない。静かさと誠実で、明治という時代を作った男。
もう一人の、西郷。
その名は、歴史の静けさの中で今も息づいている。