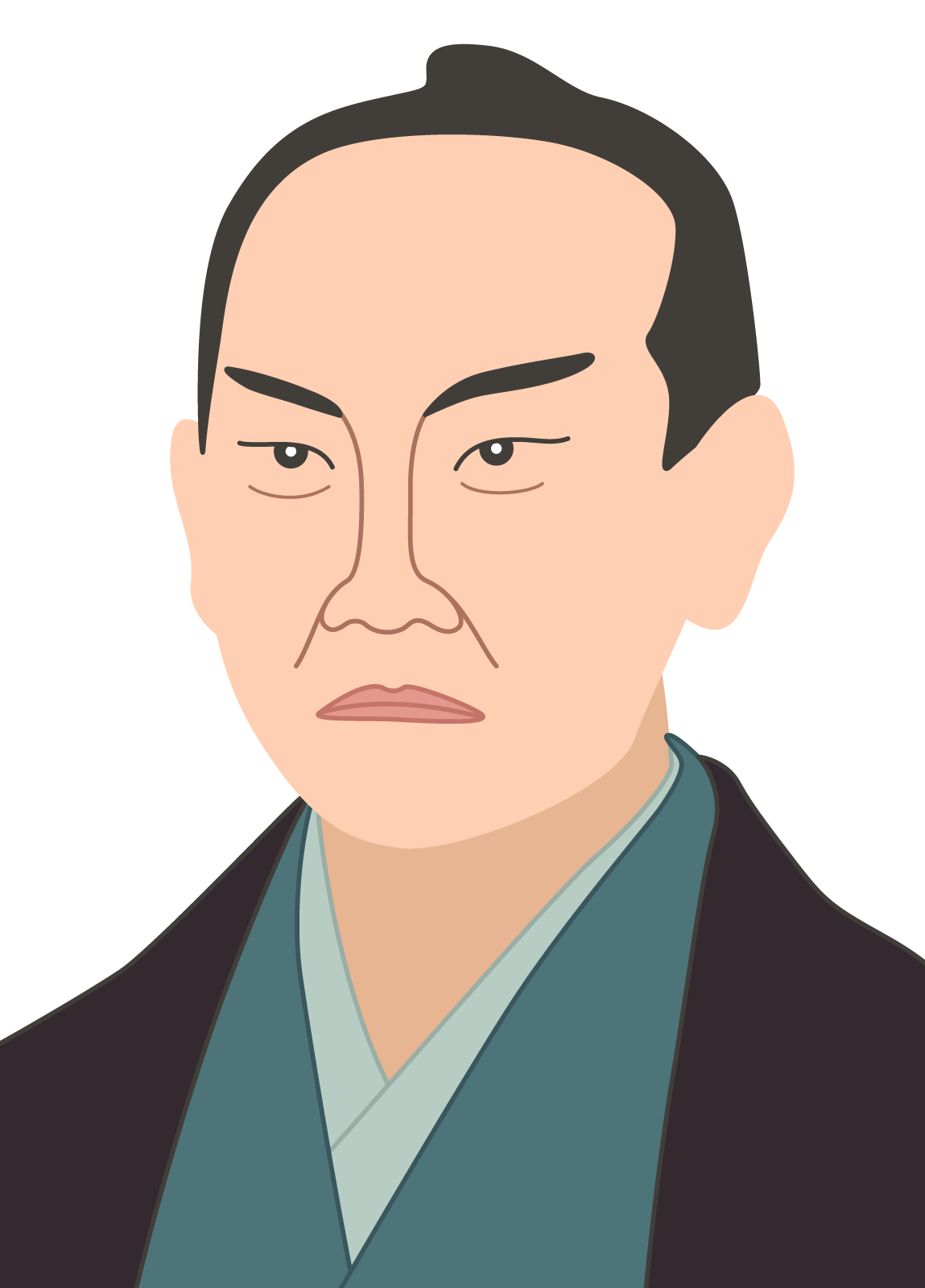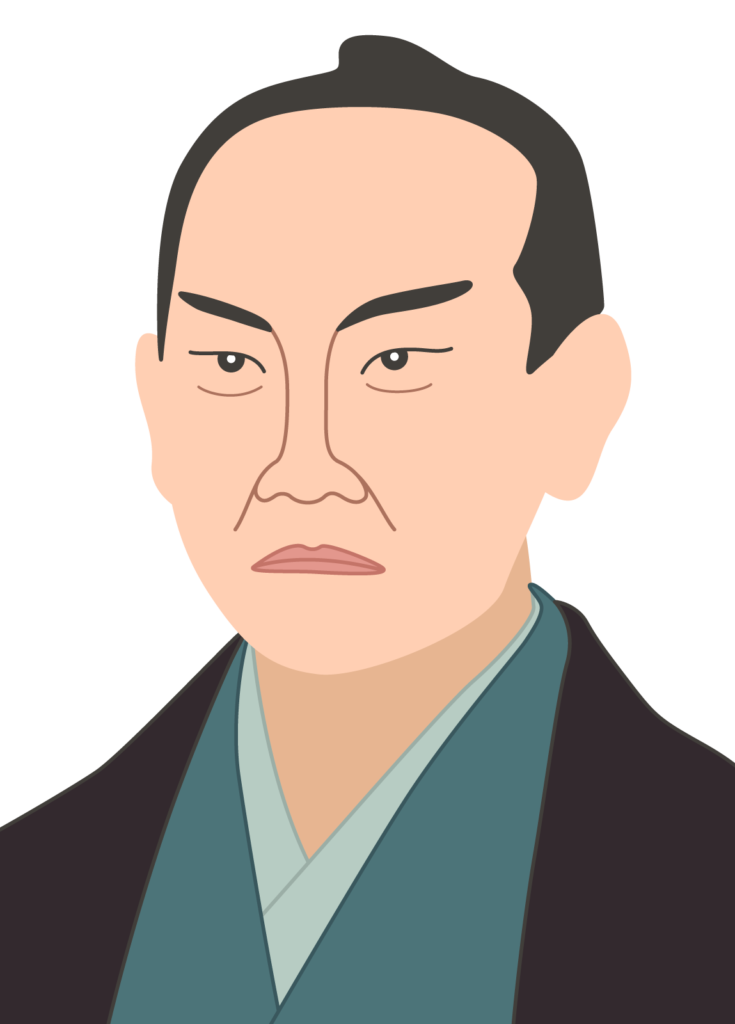
橋本左内。
若くして藩政を動かし、幕政にまで意見を言った男。
志と理想に生きた天才だった。
その言葉は鋭く、けれど優しかった。
気づいていた。国が変わらなければならないことを。
でも、変えるには犠牲がいることも知っていた。
そして、たった26年の命で、彼はその犠牲になった。
神童と呼ばれた少年時代
1834年、越前藩(現在の福井県)に生まれる。
医者の家に生まれ、幼い頃からとにかく勉強熱心だった。
8歳で医学書を読み、11歳で漢詩を詠む。
人々は彼を「神童」と呼んだ。
そのまま医者になると思われたが、彼の関心はもっと広く深かった。
「この国を良くしたい」――そんな想いが、胸の中で芽を出していた。
「啓発録」に込めた決意
左内は15歳のとき、『啓発録』という著作を書いている。
自分自身を奮い立たせるための、いわば「誓いの書」だった。
内容は驚くほど成熟していた。
「大志を抱け」「知識を深めよ」「人に負けぬ精神を持て」
若干15歳の少年が、自分に言い聞かせた言葉は、
まるで幕末の青年たち全体へのメッセージのようだった。
この志が、後に彼を藩主・松平春嶽の側近へと導いていく。
松平春嶽のブレーンとして
越前藩主・松平春嶽は、若き左内の才能を見抜いた。
そして藩政改革に抜擢する。
左内は、財政改革だけでなく、開国や教育政策にも口を出した。
彼の思考は常に「日本全体」の未来を見据えていた。
やがて、藩の外にまで名が知られるようになり、
幕政にも関わるようになる。
若干20代前半にして、政の中枢へ。
まさに“若獅子”と呼ぶにふさわしい存在だった。
開国を支持し、敵を作る
左内は、ペリー来航以降の日本にとって、開国は避けられないと考えていた。
だからこそ、早く西洋から学ぶべきだと主張した。
だが、それは保守派から見れば「裏切り」だった。
攘夷派の志士たちからは敵視され、幕府内部にも反発の声があった。
政治の渦の中で、左内は次第に危険な存在とみなされていく。
そして、悲劇は起こる。
安政の大獄、そして処刑
1858年、大老・井伊直弼が反対派を弾圧する「安政の大獄」が始まる。
橋本左内もその標的となった。
理由は、「一橋慶喜を将軍に推したから」。
そして、「開国派として動いたから」。
罪とは名ばかりの理不尽な処分。
彼は捕らえられ、若干26歳の若さで処刑される。
その死は、多くの人に深い衝撃を与えた。
とくに松平春嶽は、長く悔しさを抱え続けたという。
まとめ
橋本左内は、まっすぐに生きた。
誰よりも早く国の未来を考え、誰よりも若く散った。
その知性と志は、今もなお響いている。
もし彼がもう10年生きていたら、
日本の形は、少し違っていたかもしれない。
その“もしも”を思わせるだけの力を持っていた。
それが、橋本左内という人物だった。