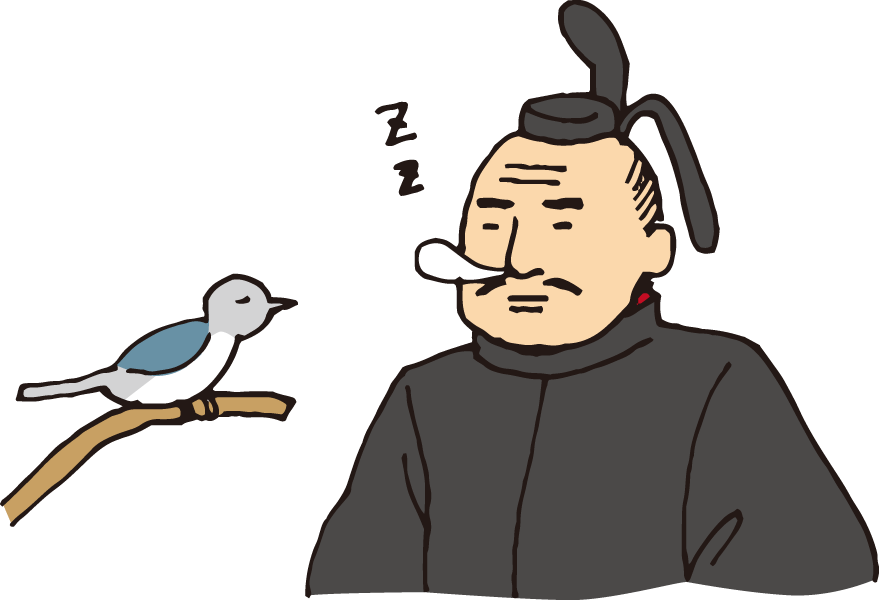
こんにちは。
人生は、思い通りにいかないことの連続ですよね。
「なんで今じゃないの?」
「どうして動いてくれないの?」
──そんなふうに、もどかしい気持ちになること、ありませんか?
そんなときに思い出したいのが、こちらの有名な句です。
「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」
この句は、一見ただの風流な一句のように見えますが、実はとても深い“人間力”を表した言葉なんです。
この句の意味とは?
「ホトトギスが鳴かないなら、無理に鳴かせようとはせず、鳴くまで待つ」という意味。
つまり、
「状況が整うまで焦らず待とう」
「相手が動くまでじっと我慢しよう」
といった“忍耐”と“信じる心”を表しています。
急がず、焦らず、時が満ちるのを待つ
──簡単なようで、実は一番難しい“待つ力”がここに込められています。
たとえ話
ある少年がホトトギスを飼っていました。
ある日からそのホトトギスは、なぜか鳴かなくなってしまいました。
心配になった少年は、いろんな人に相談します。
「火を近づけてみろ」
「脅してやれば鳴くかも」
「別の鳥を連れてこい」
そんなアドバイスをたくさんもらいました。
でも少年は言いました。
「きっと、今は鳴きたくないだけ。そのうち、また鳴く日が来るよ」
毎日エサをあげて、声をかけて、そっと見守る日々。
やがて春になり、ホトトギスは朝の光の中で、再び「ホトトギス」と鳴きました。
少年は何もしていないようで、何よりも大事なことをしていたのです。「待つこと」を。
起源・由来について
この句は、実は歴史上の有名な人物にちなんだ川柳風のたとえ句なんです。
ホトトギスを題材に、三英傑――織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の性格をあらわしています。
三者三様のホトトギス
| 武将 | 句 | 性格 |
|---|---|---|
| 織田信長 | 鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス | 短気で結果主義 |
| 豊臣秀吉 | 鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス | 機転が利き、工夫するタイプ |
| 徳川家康 | 鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス | 忍耐強く、時を待つタイプ |
この中で「鳴くまで待とうホトトギス」は、徳川家康の精神を象徴する言葉とされています。
家康は天下統一を果たすまでに、幾多の困難を乗り越え、何十年も耐え続けた人物。
その姿勢がこの句にぴったり重なるため、後世の人々がこう表現したのです。
おわりに
現代は「すぐに答えが出る」ことが求められる時代。
でも、ときには“待つ”ことが最大のチカラになることもあります。
焦らず、急かさず、信じて待つ。
「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」
──この言葉が、心の支えになる瞬間が、きっとあなたにもあるはずです。

